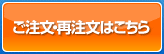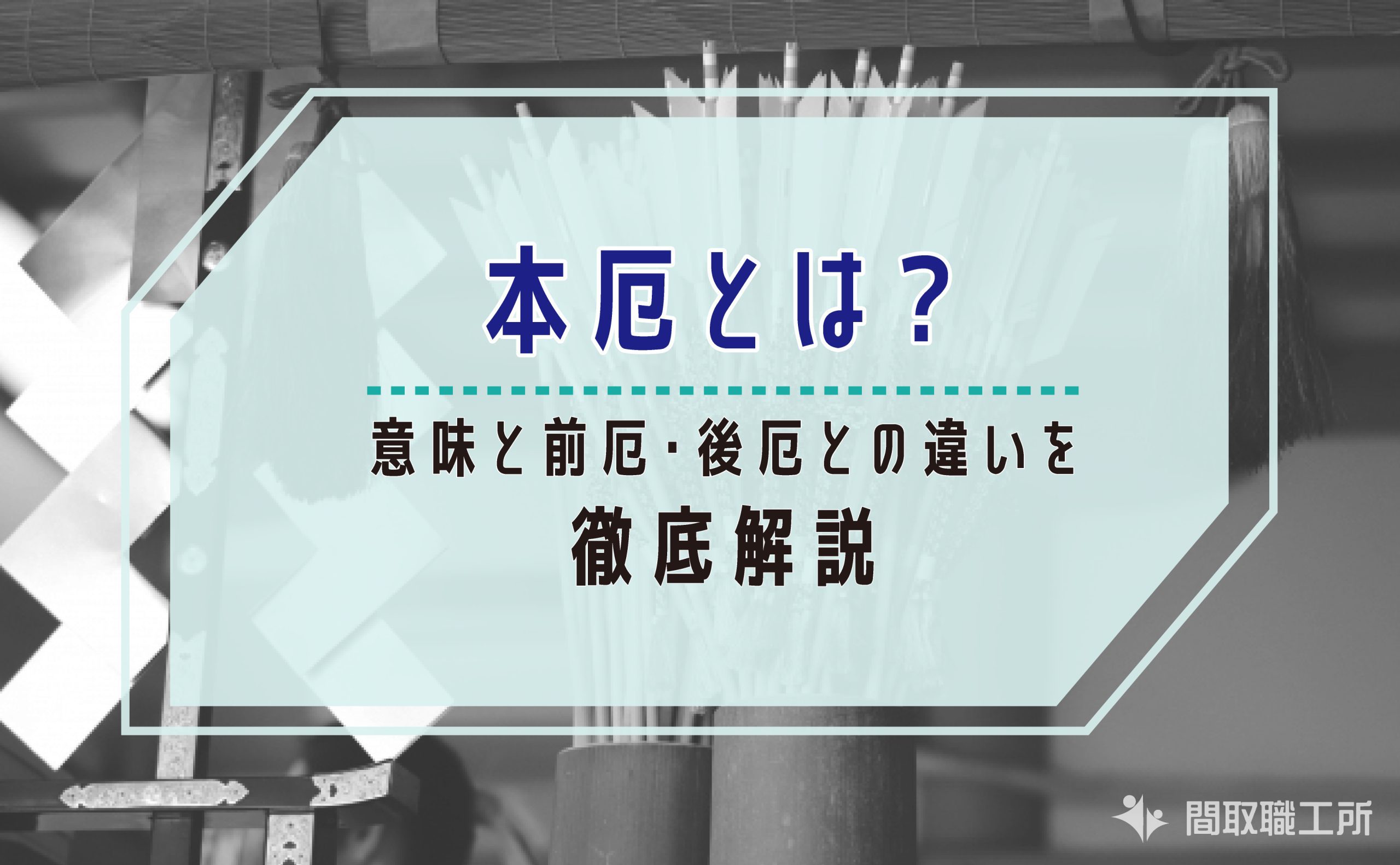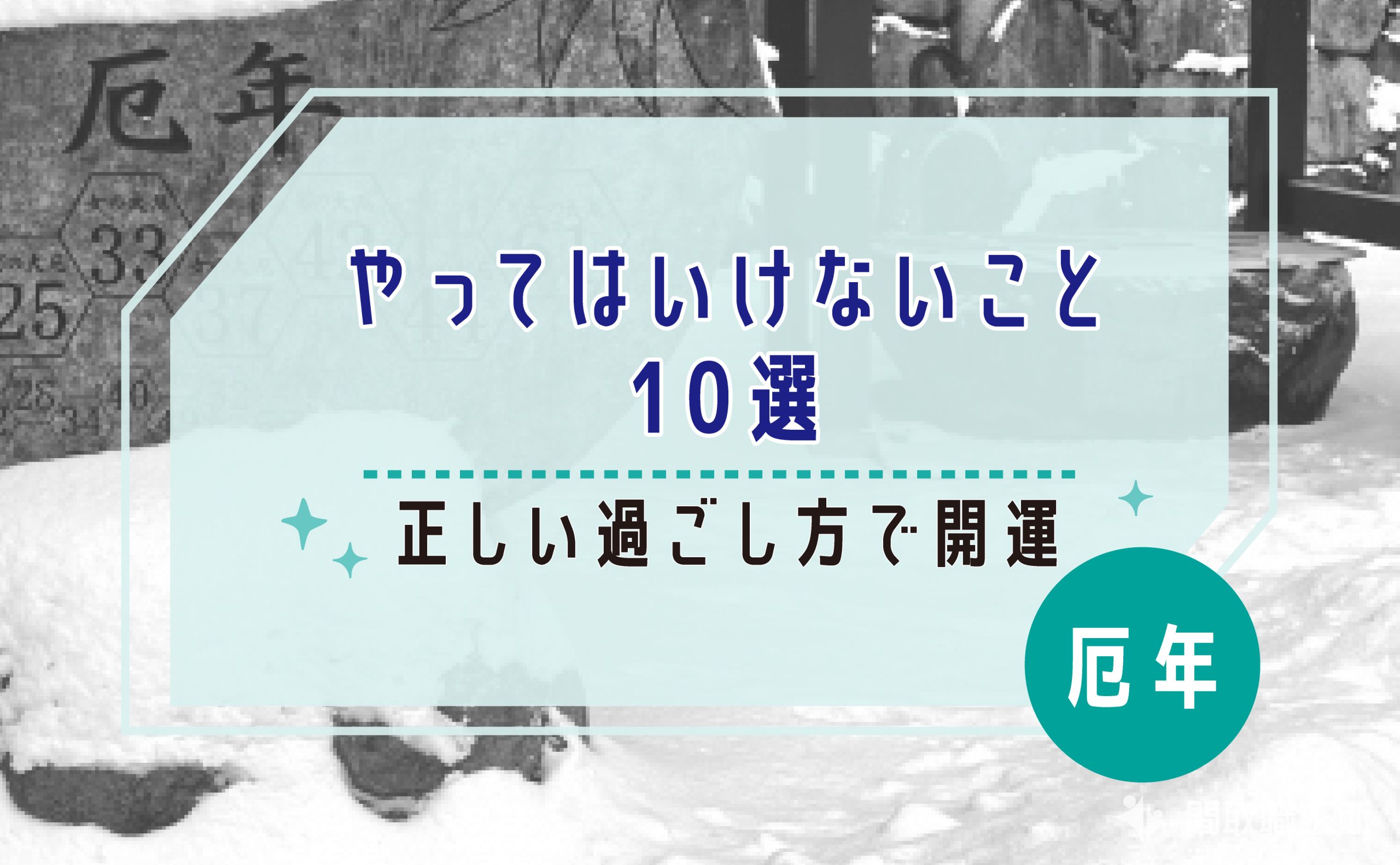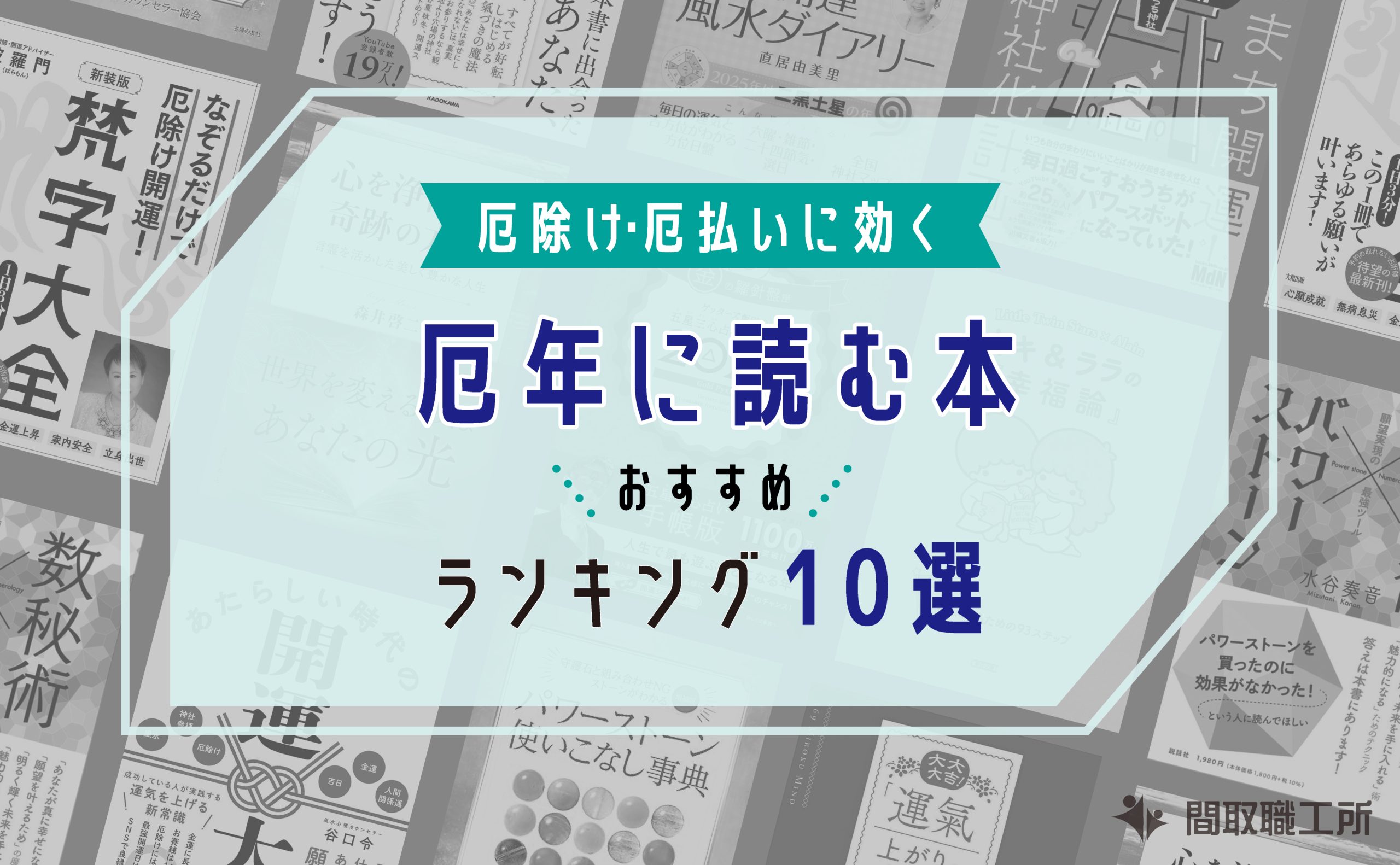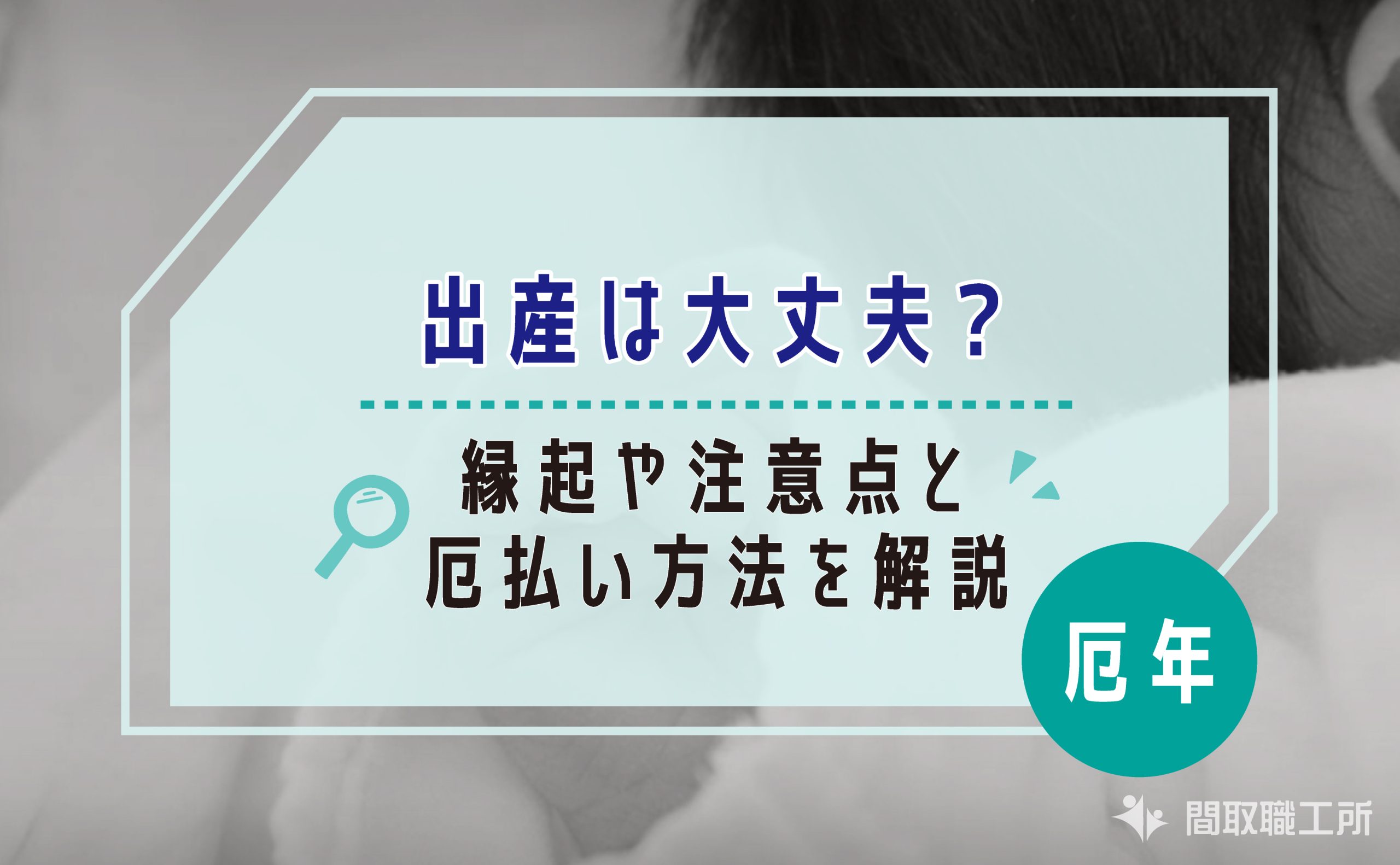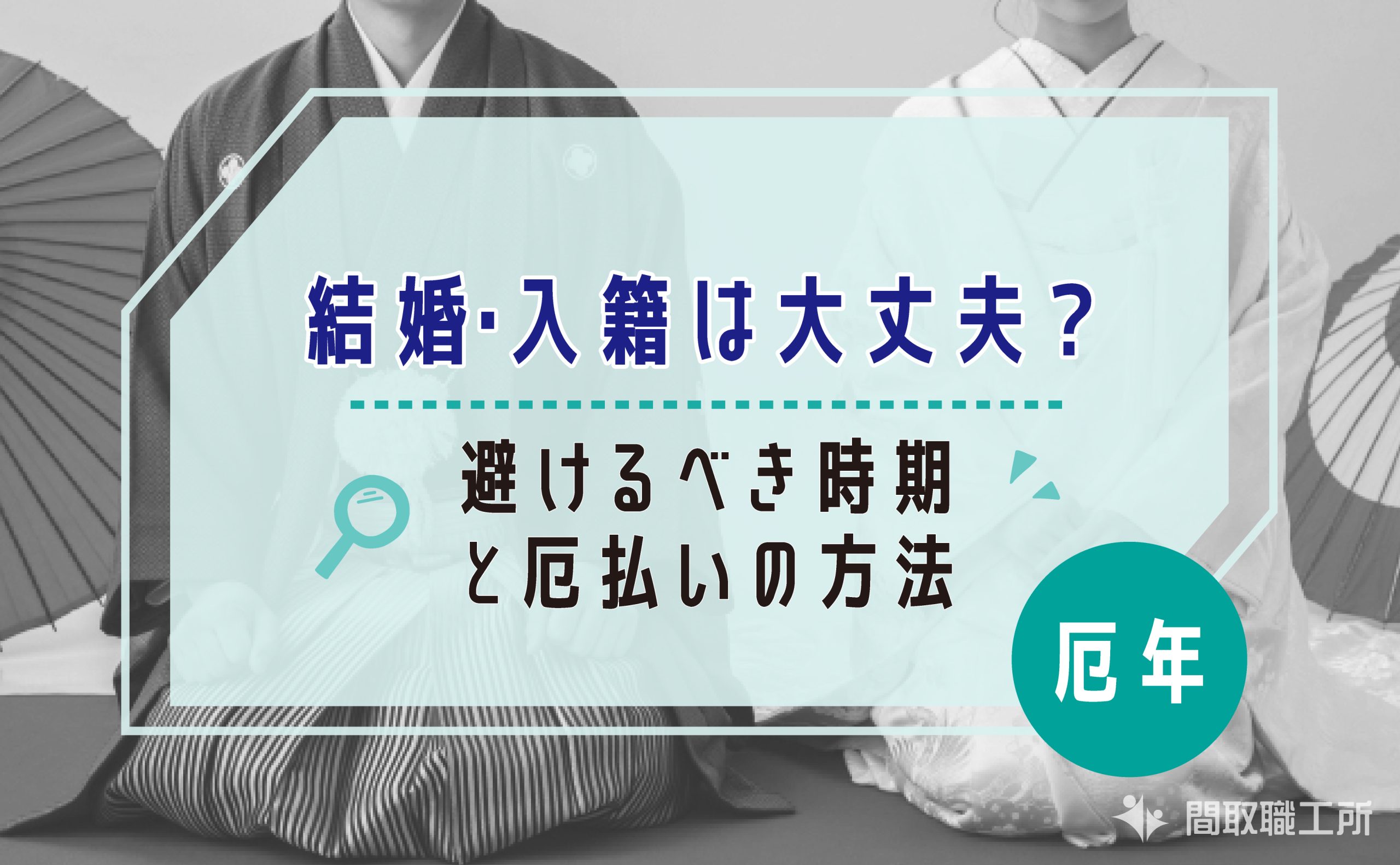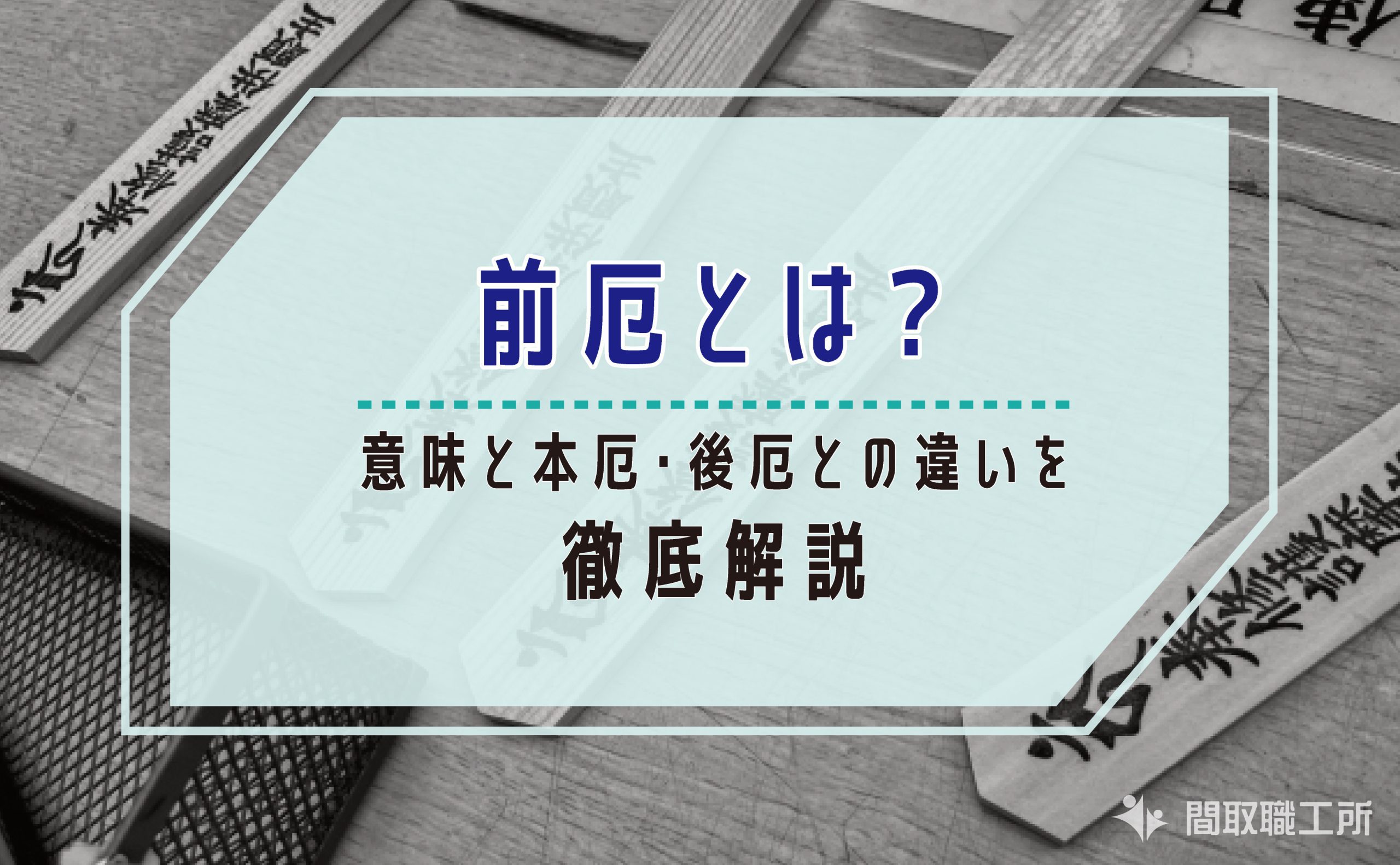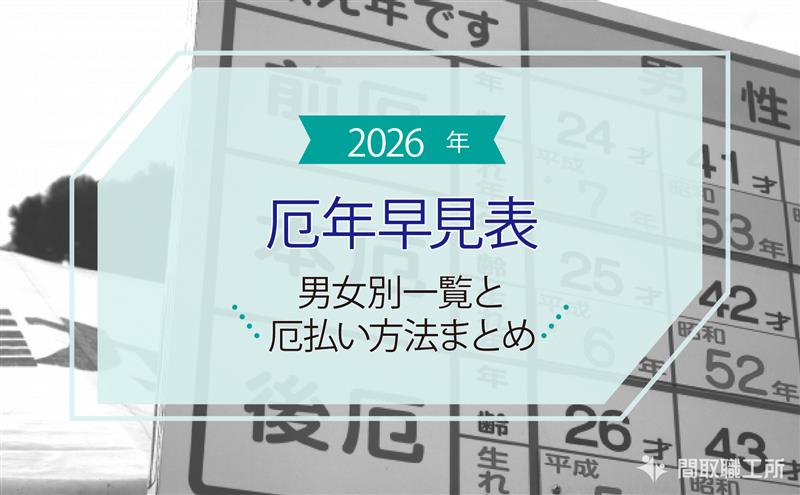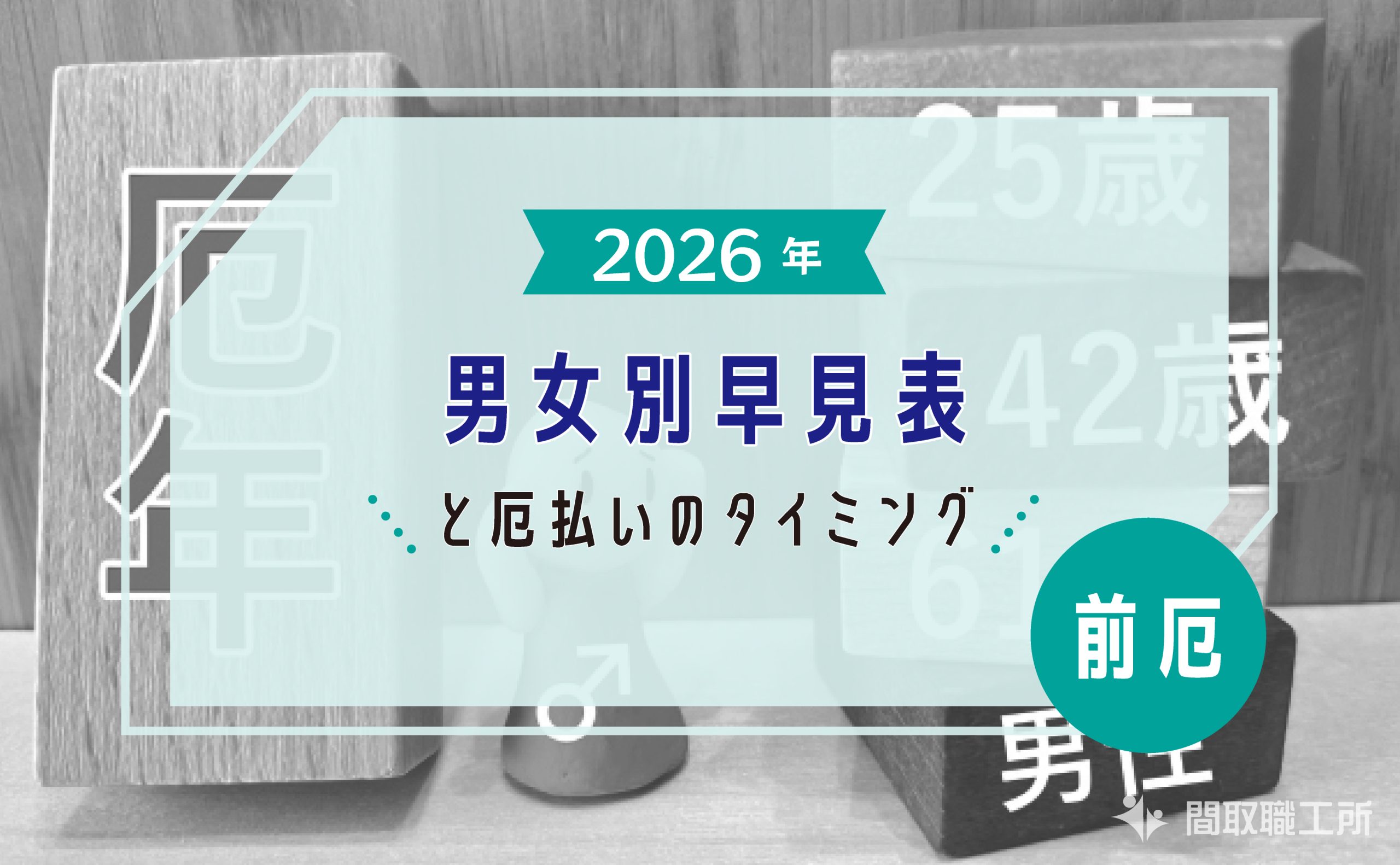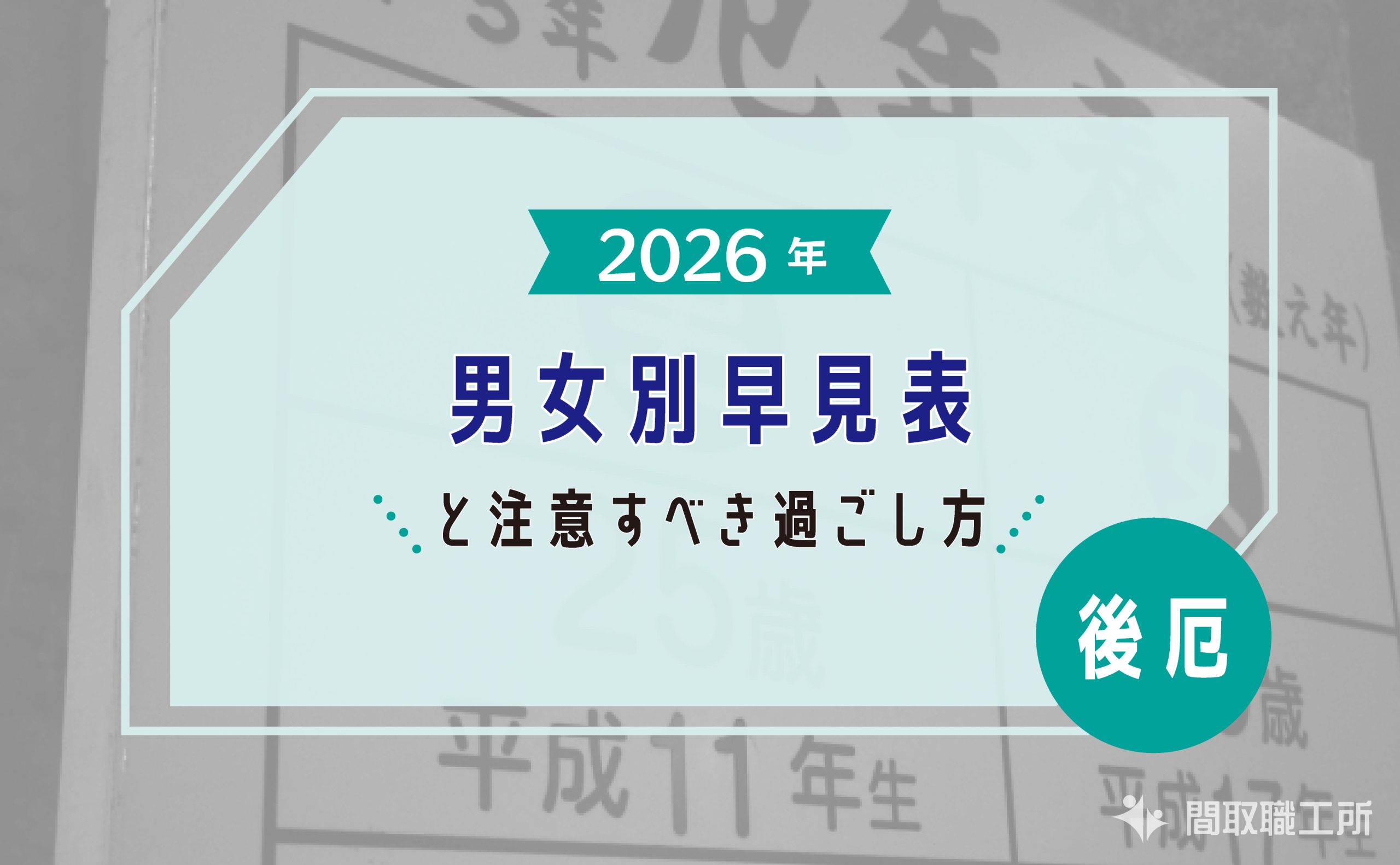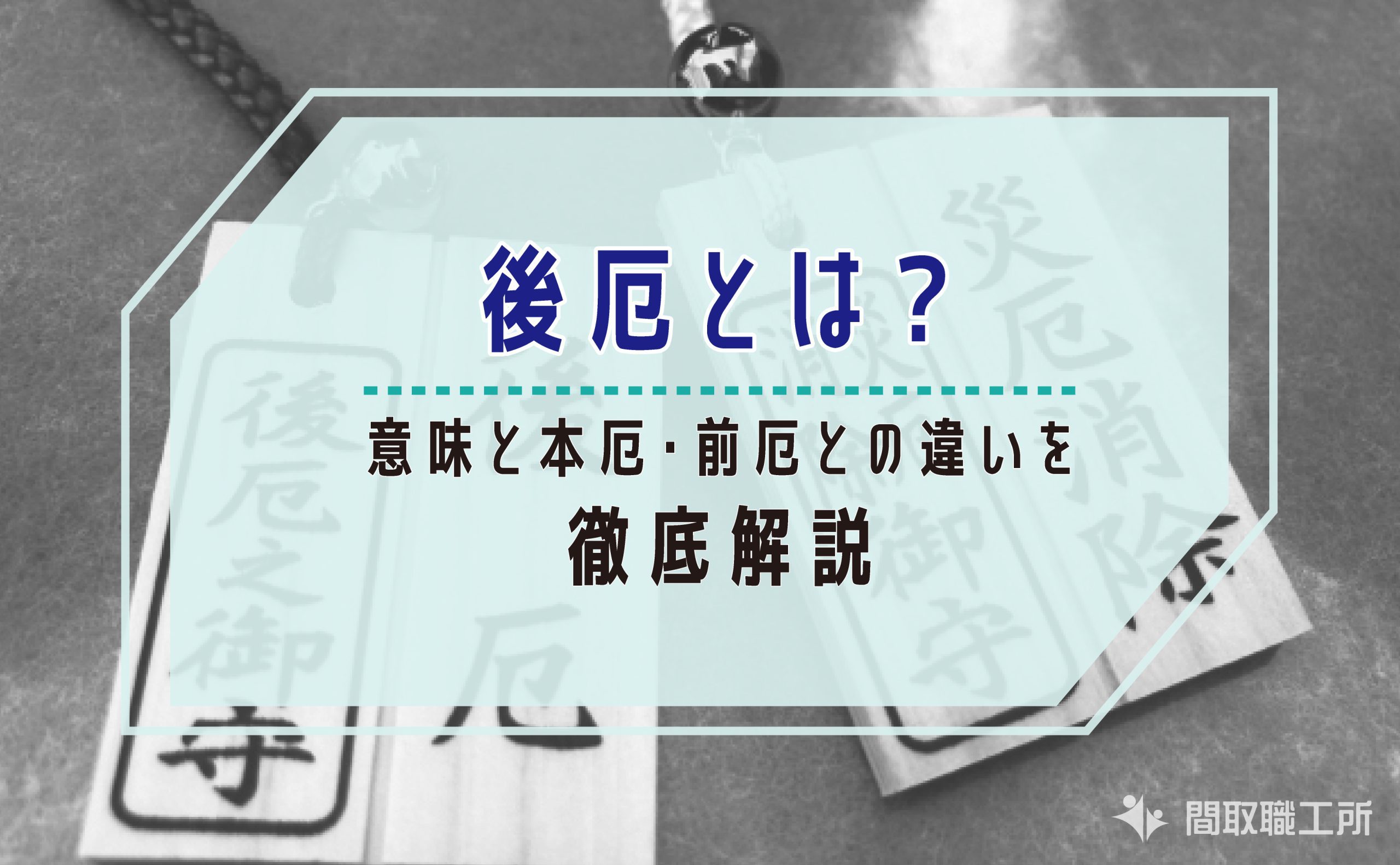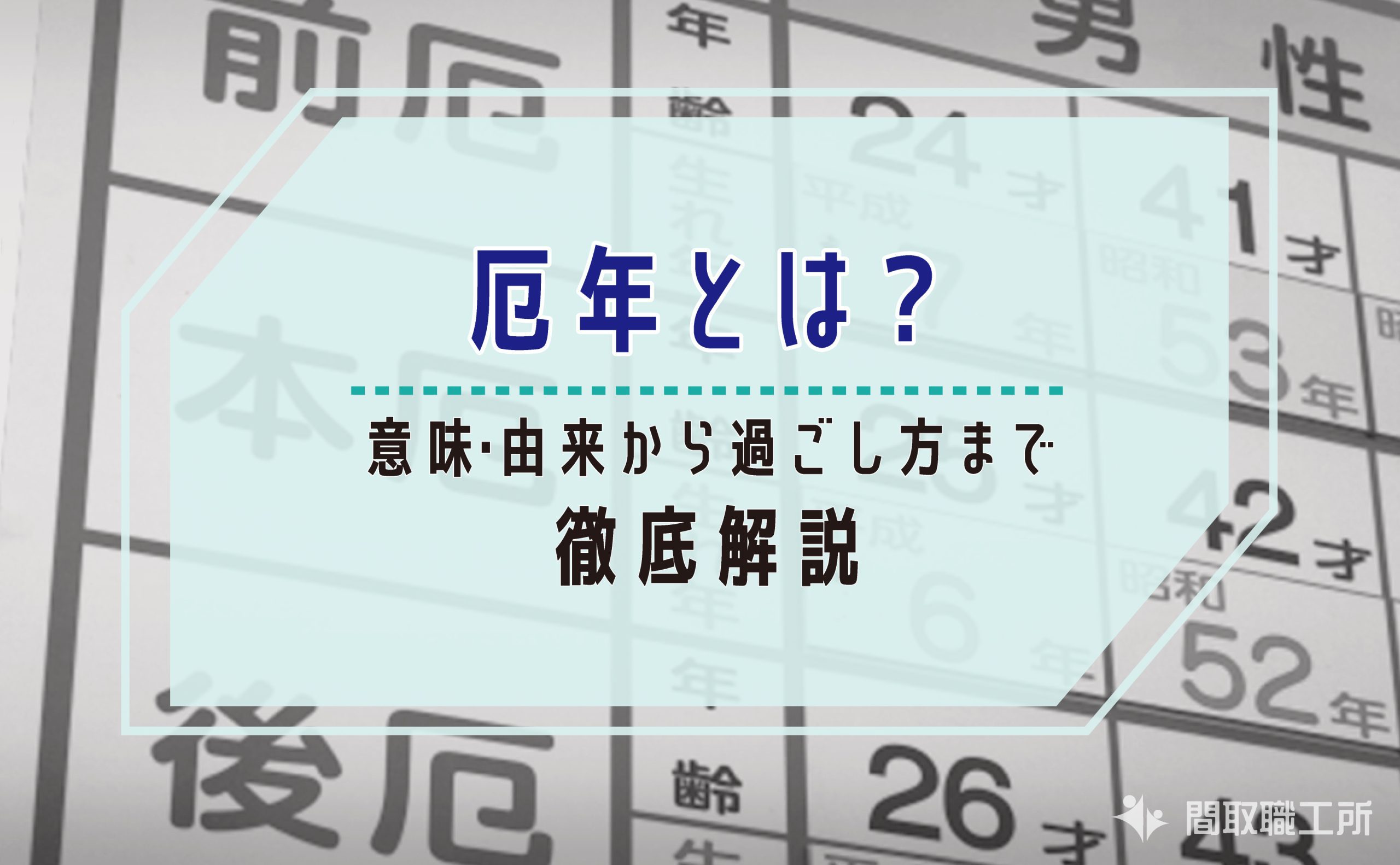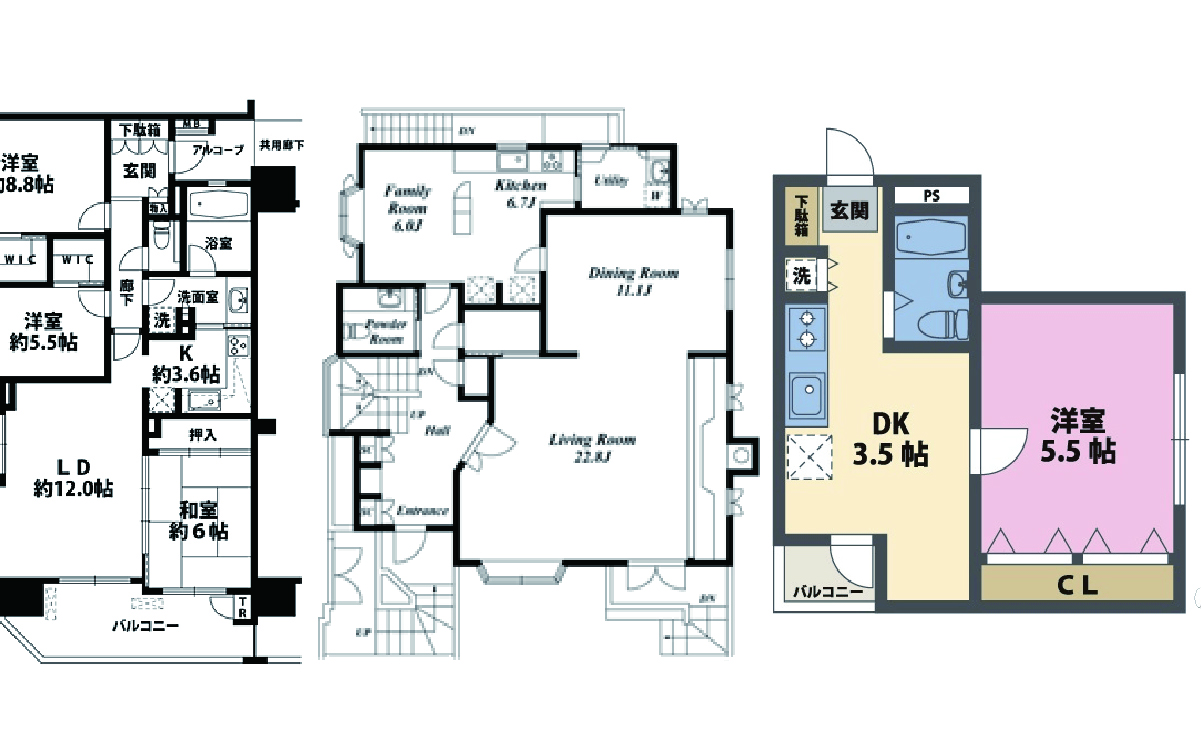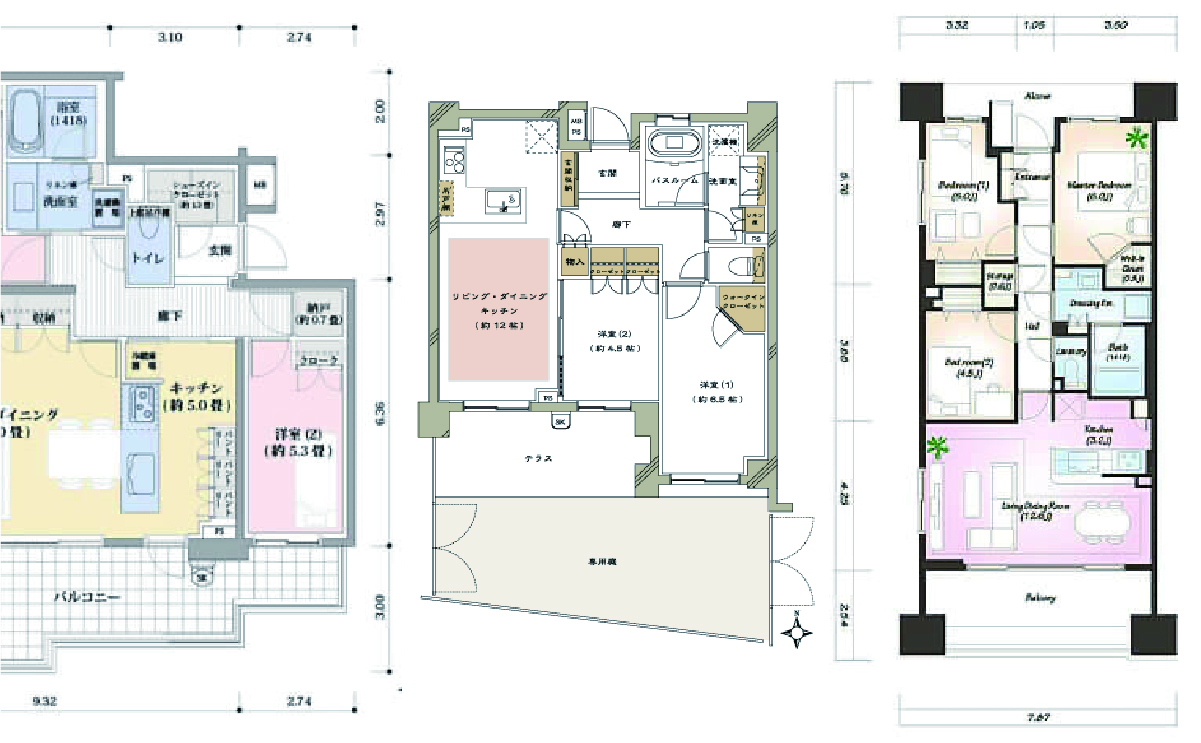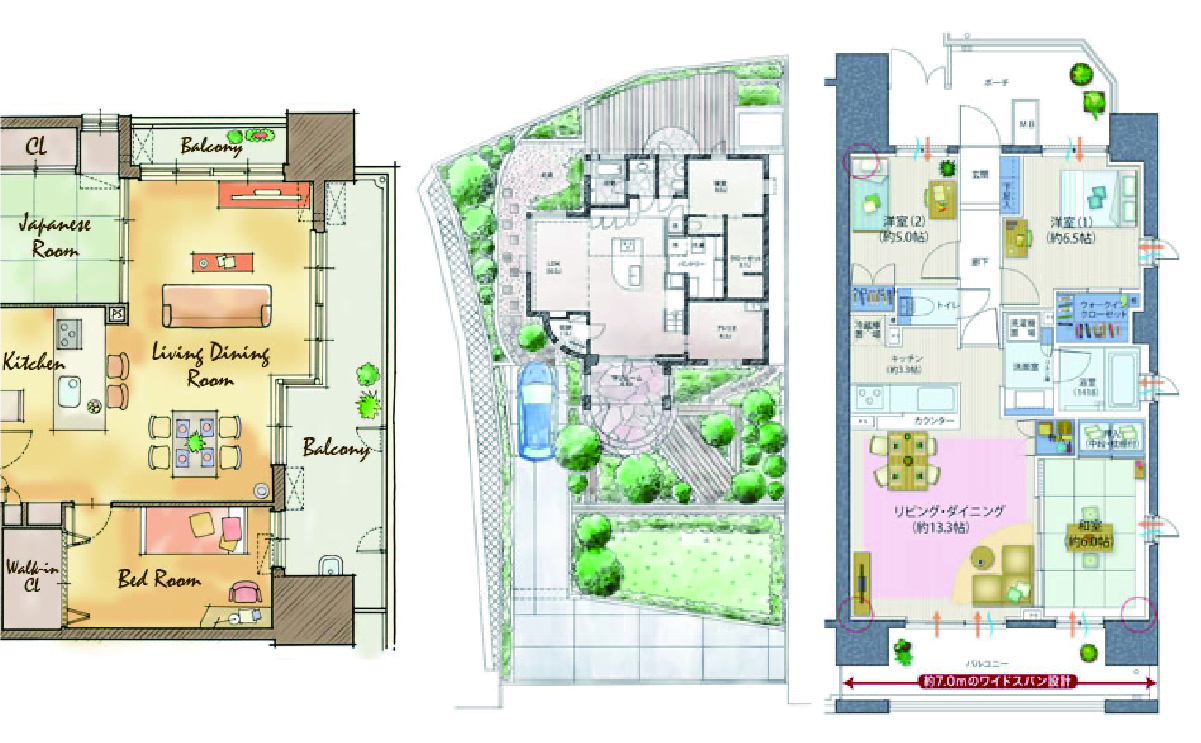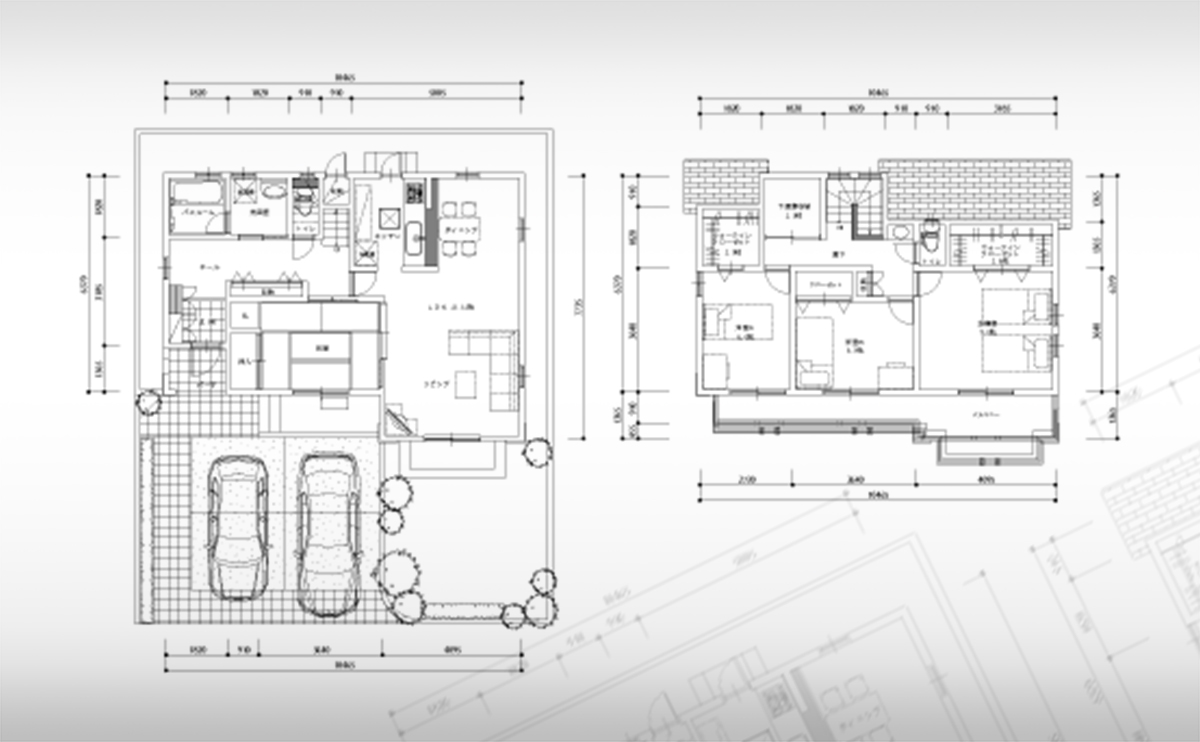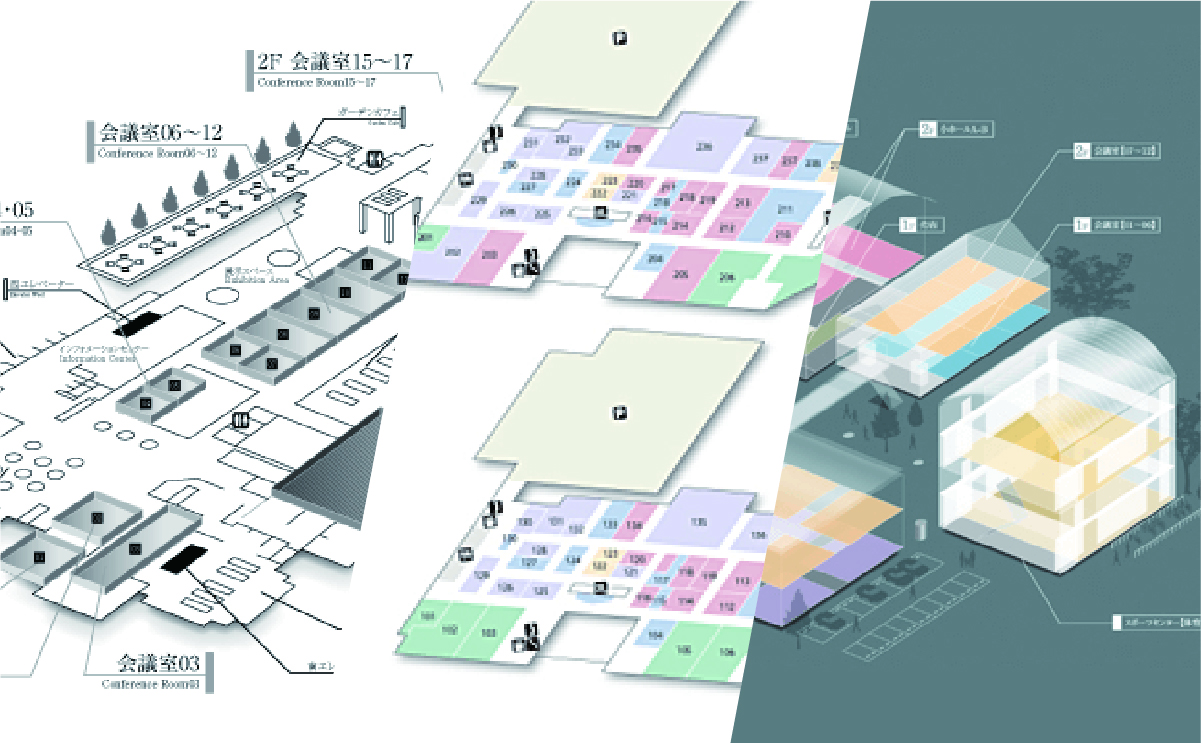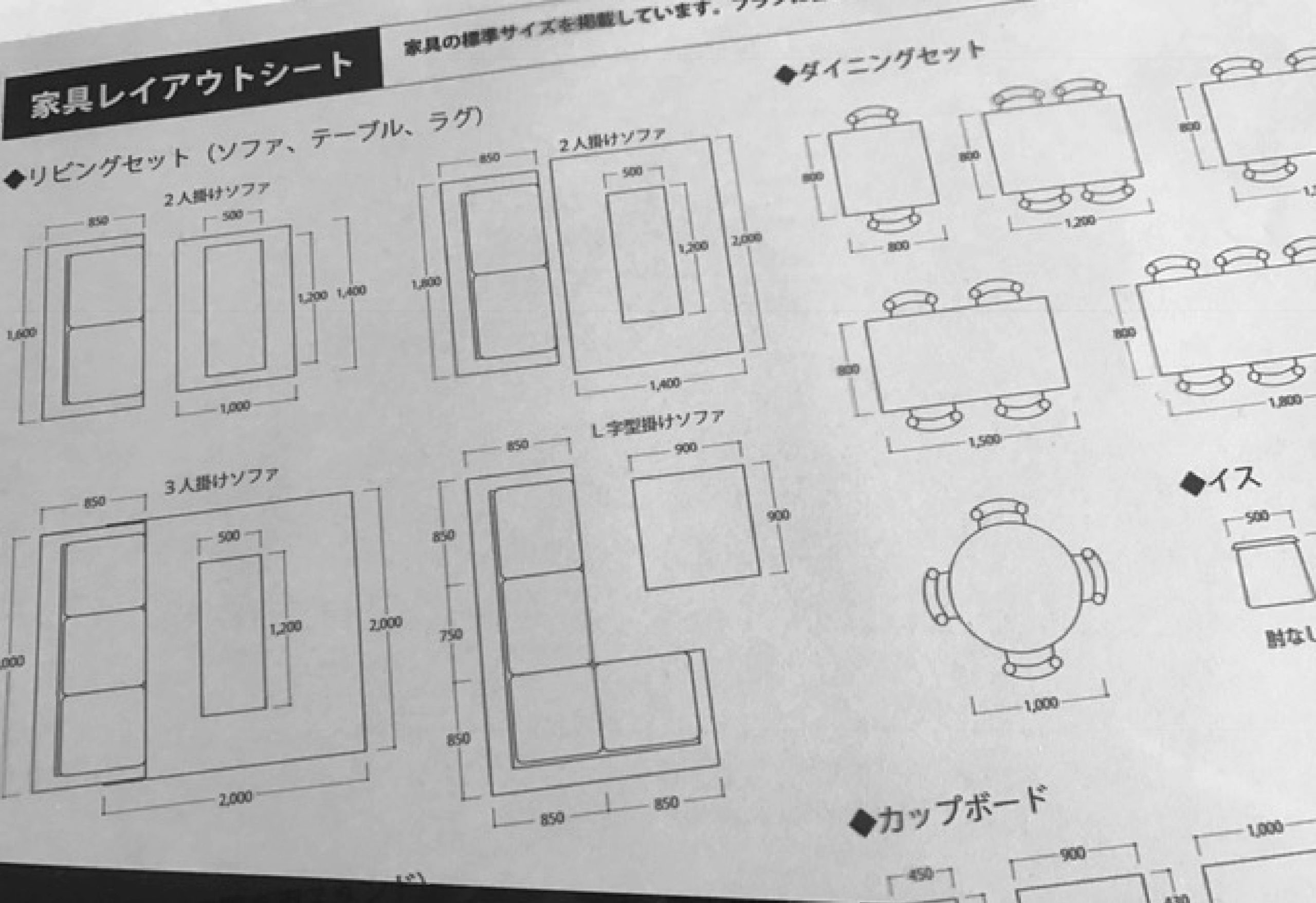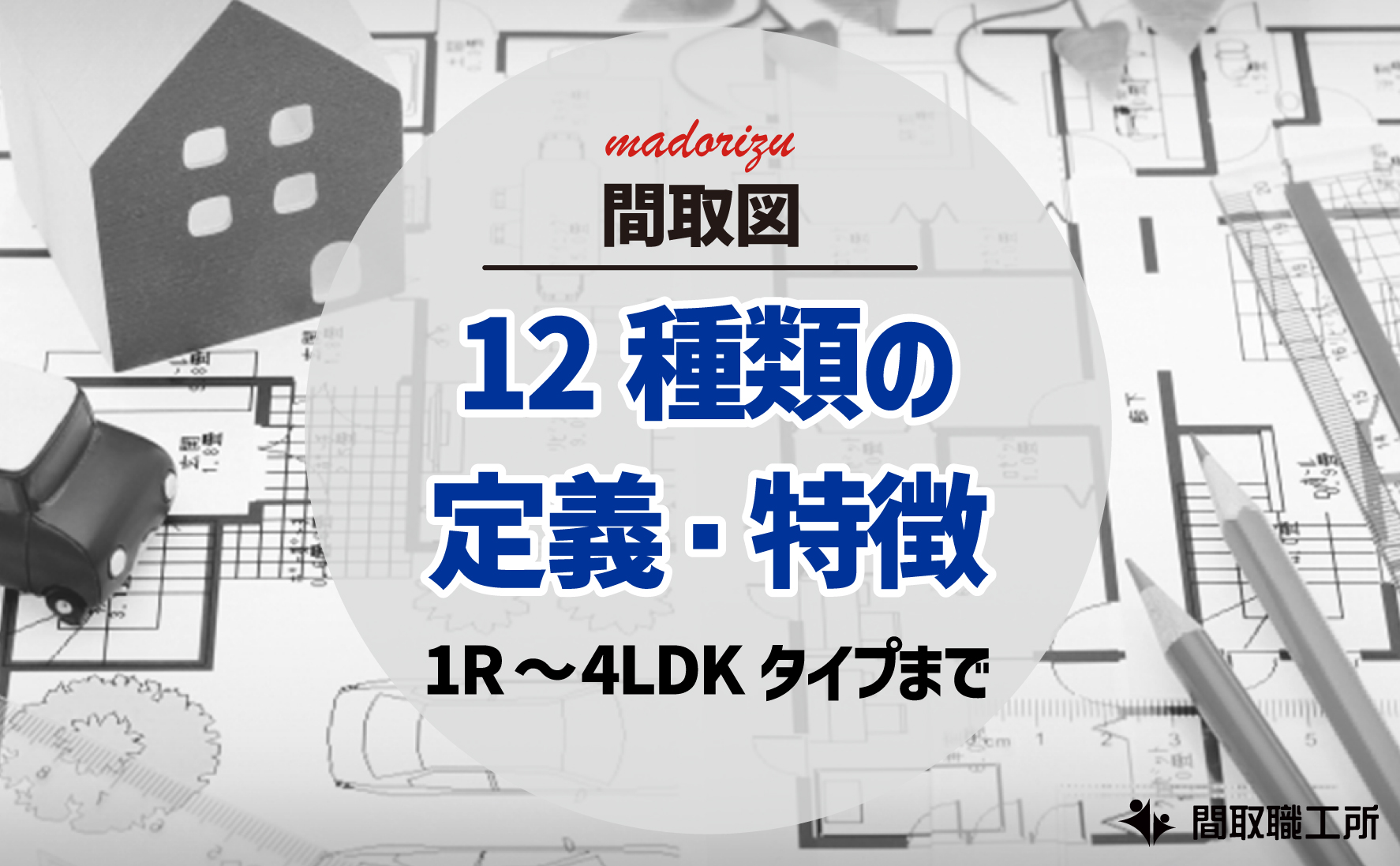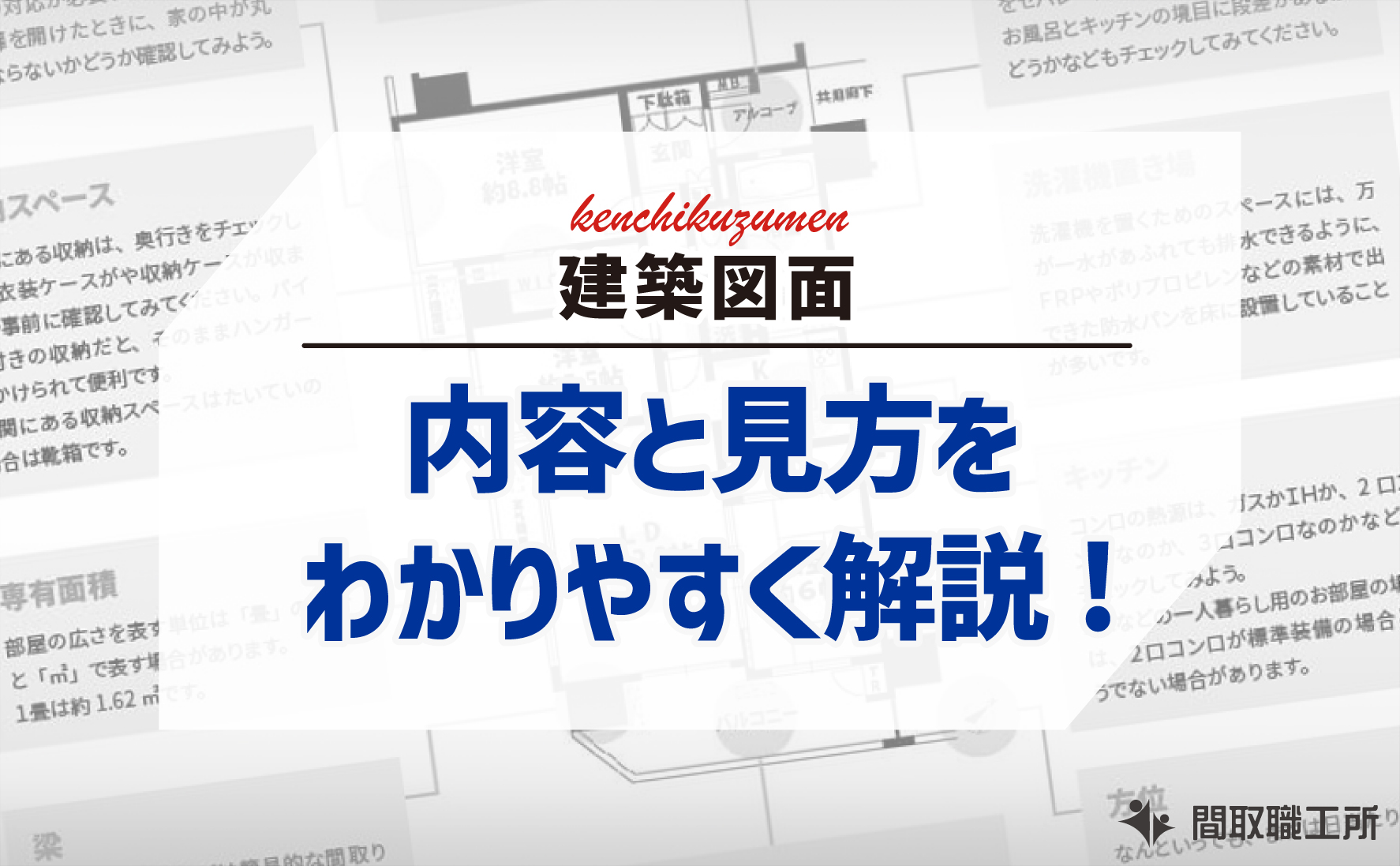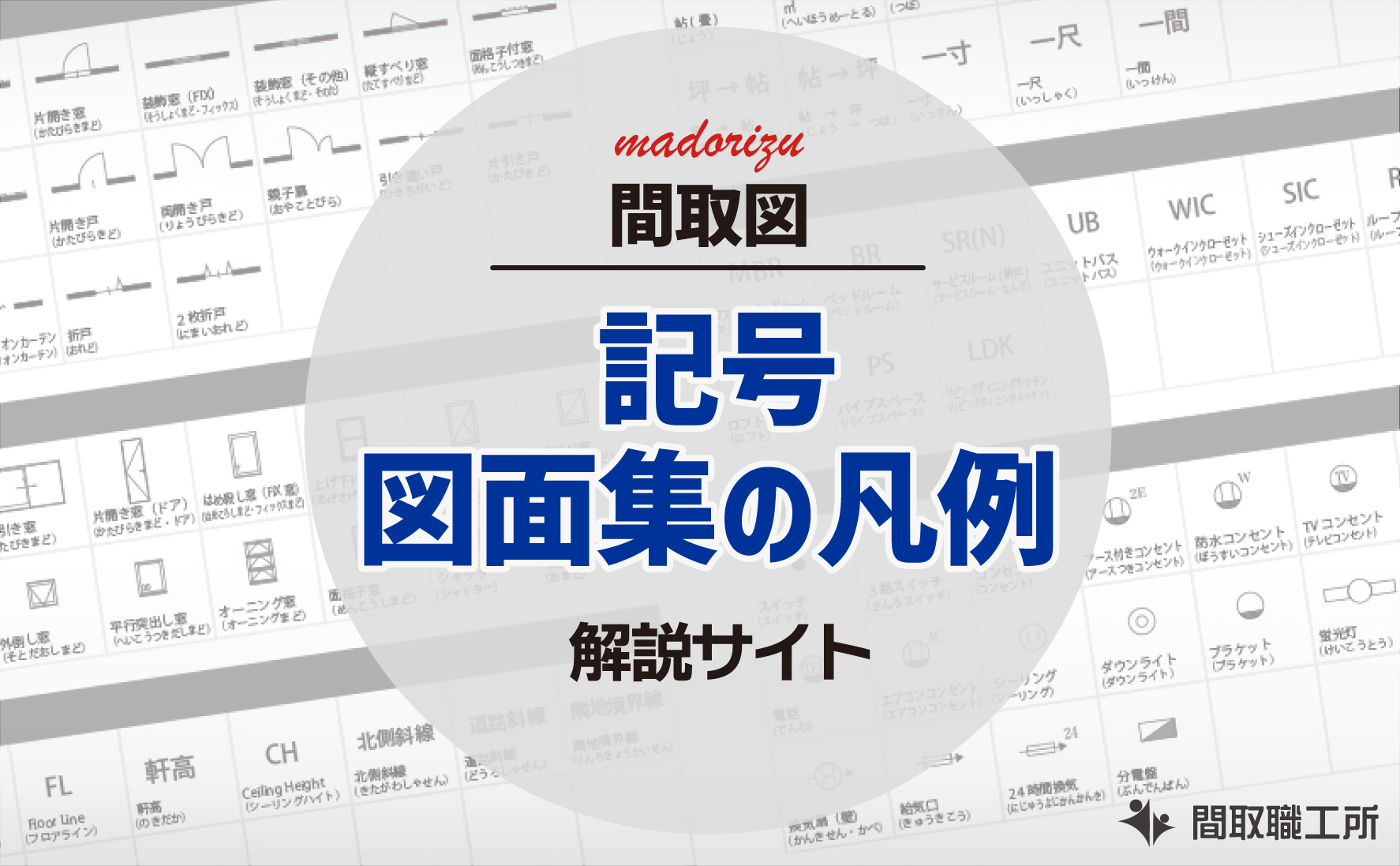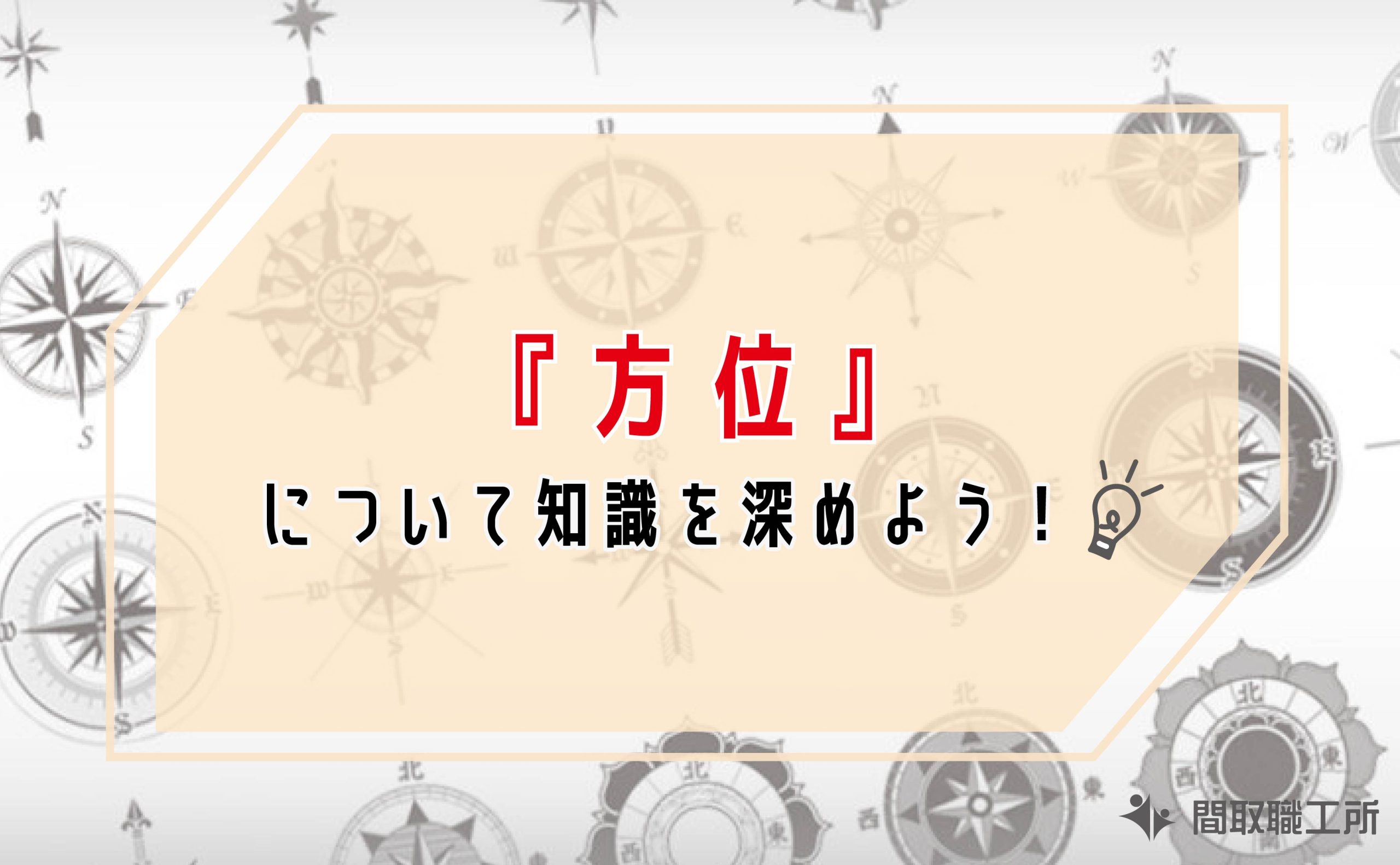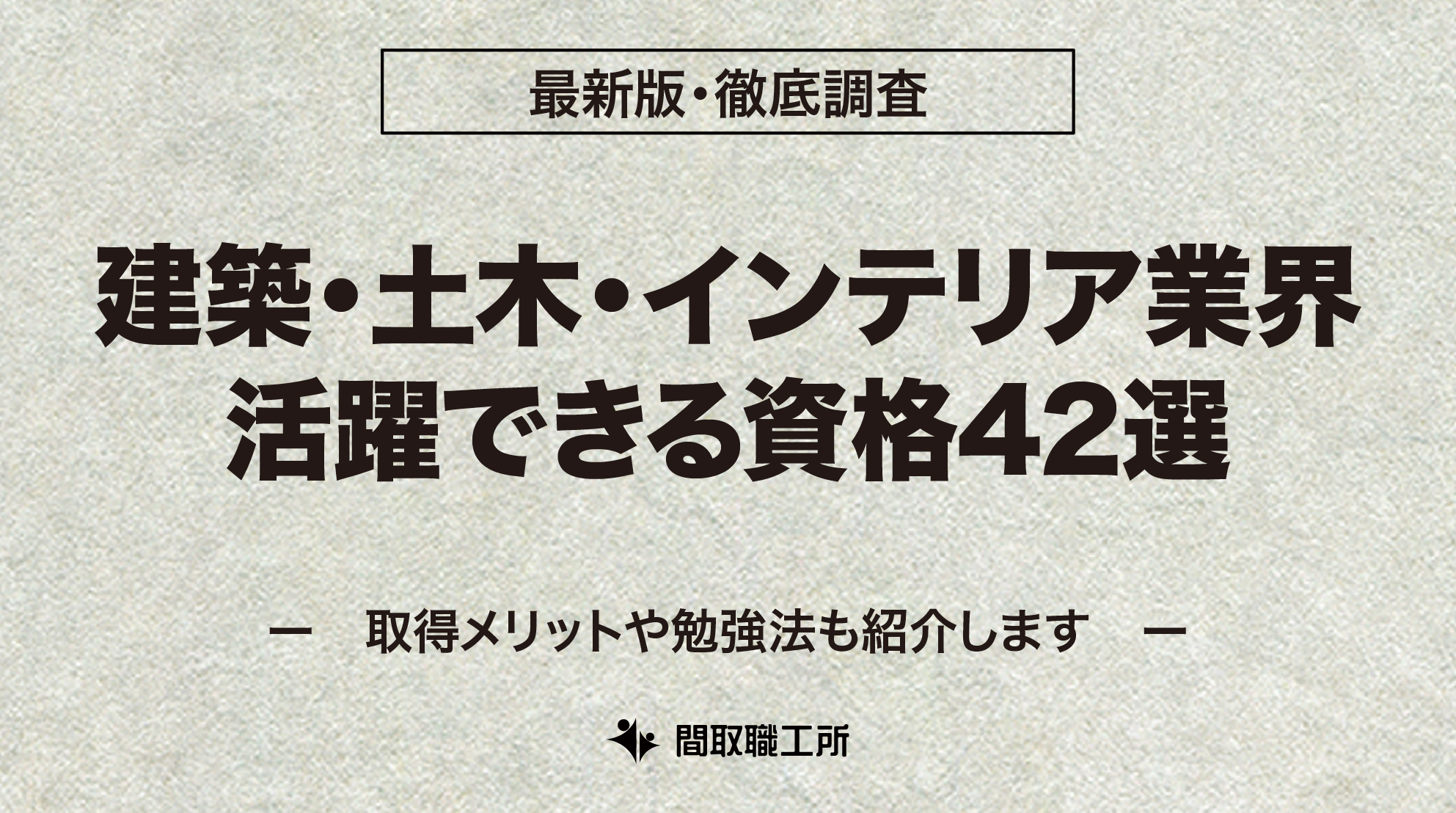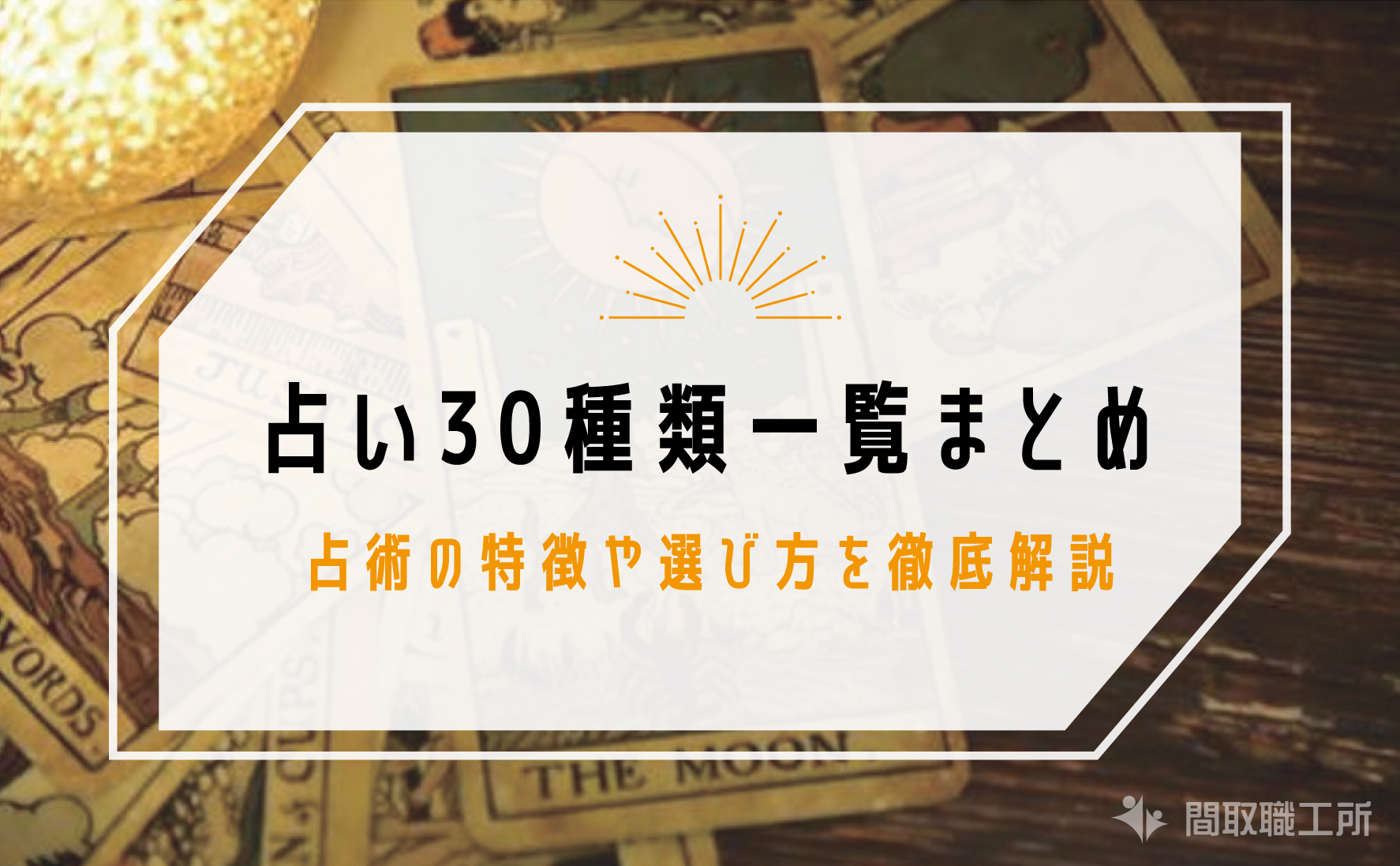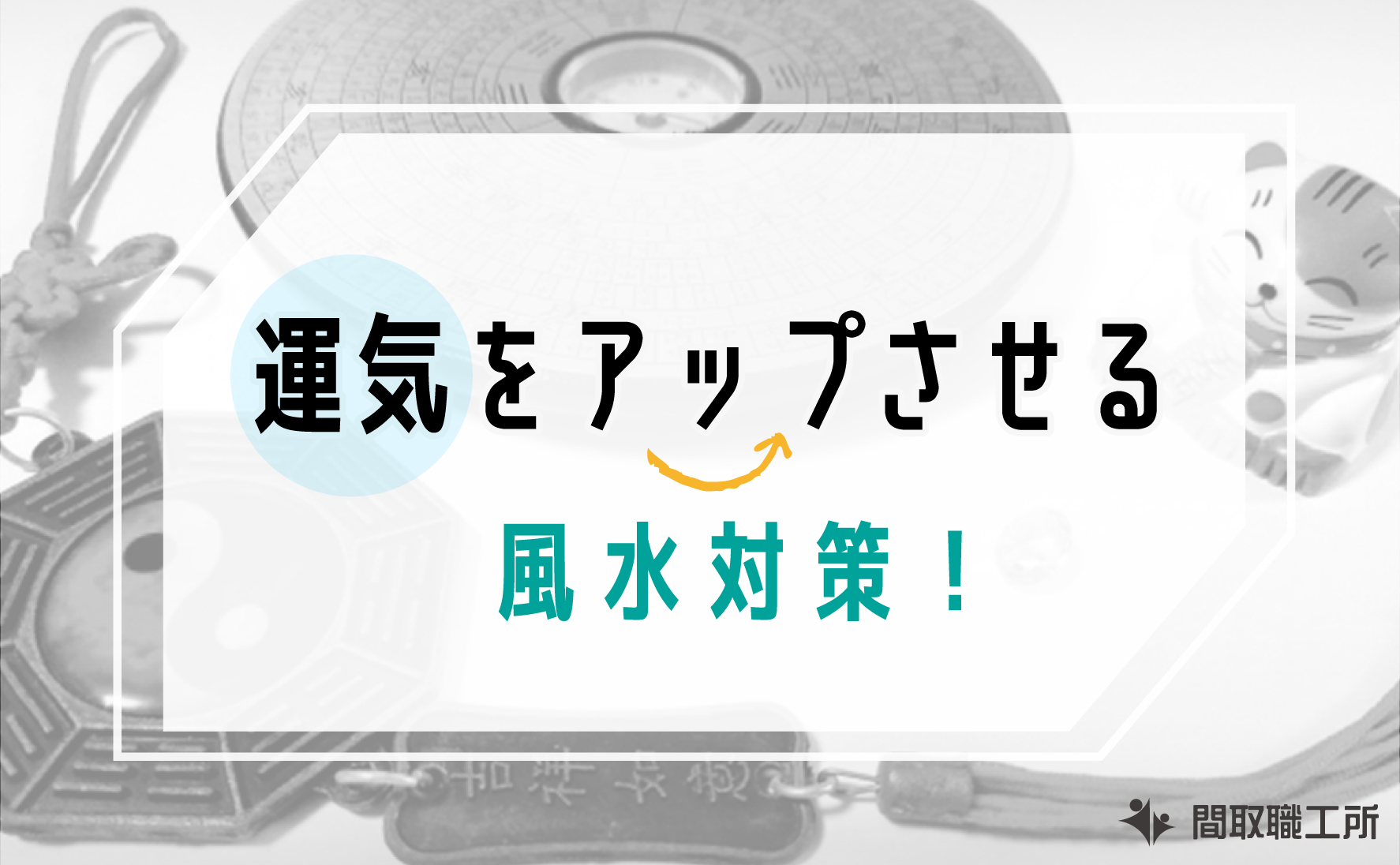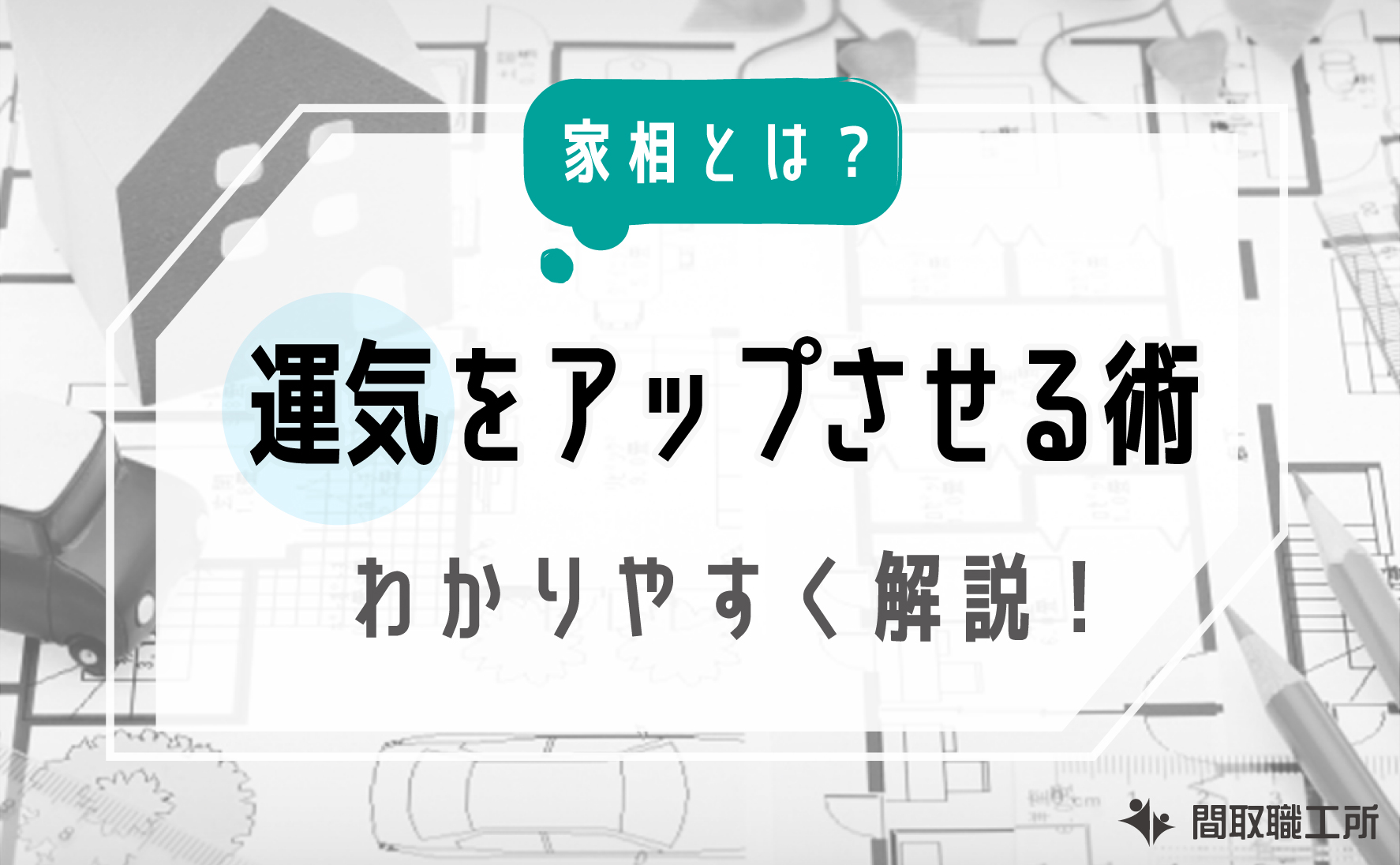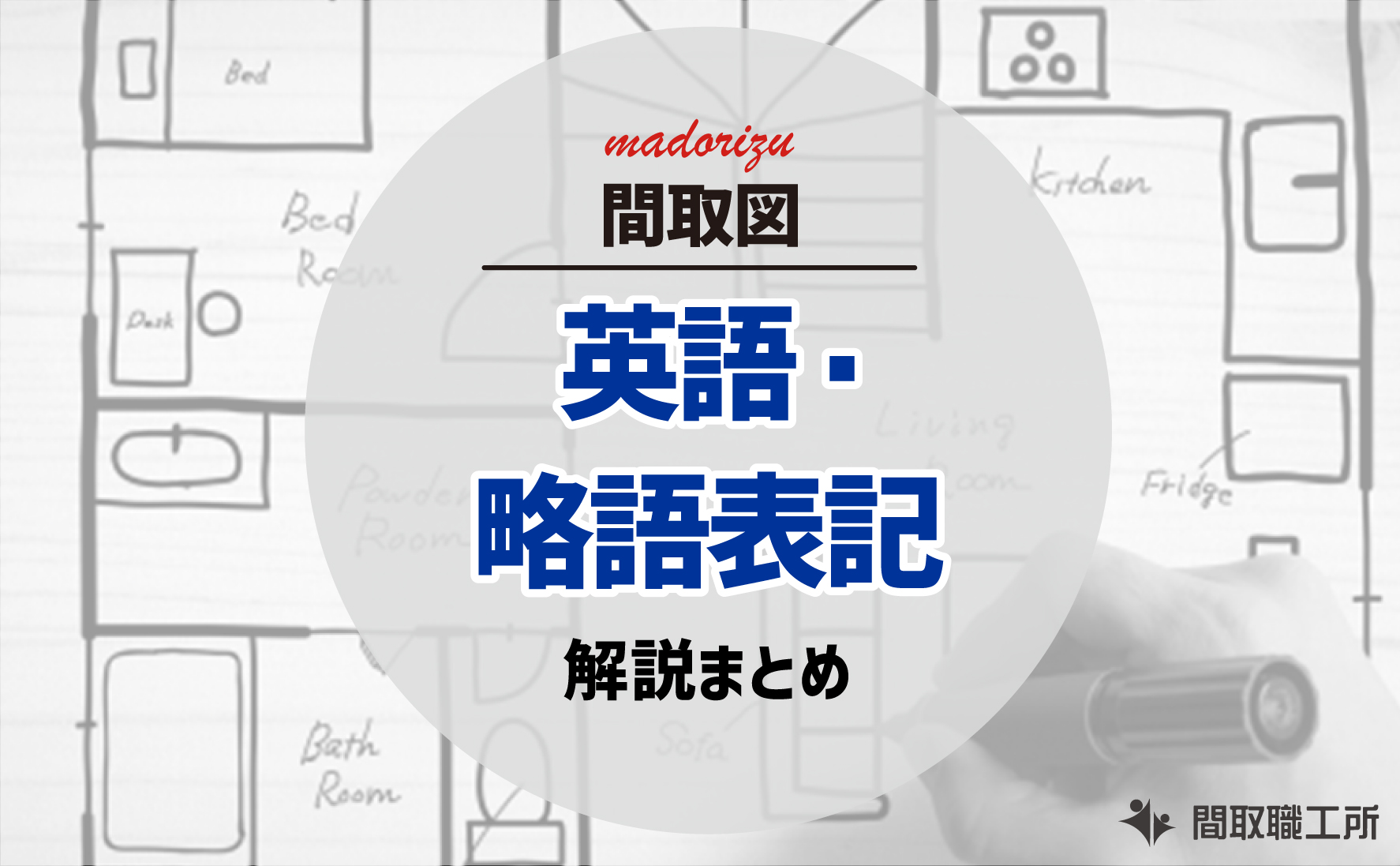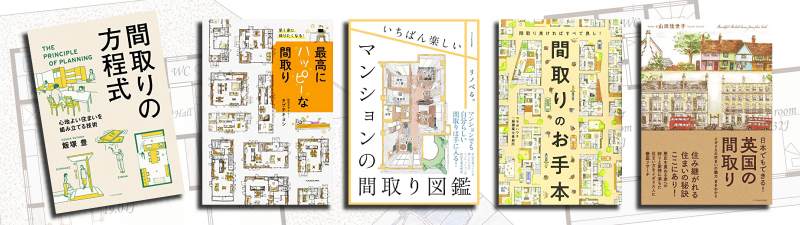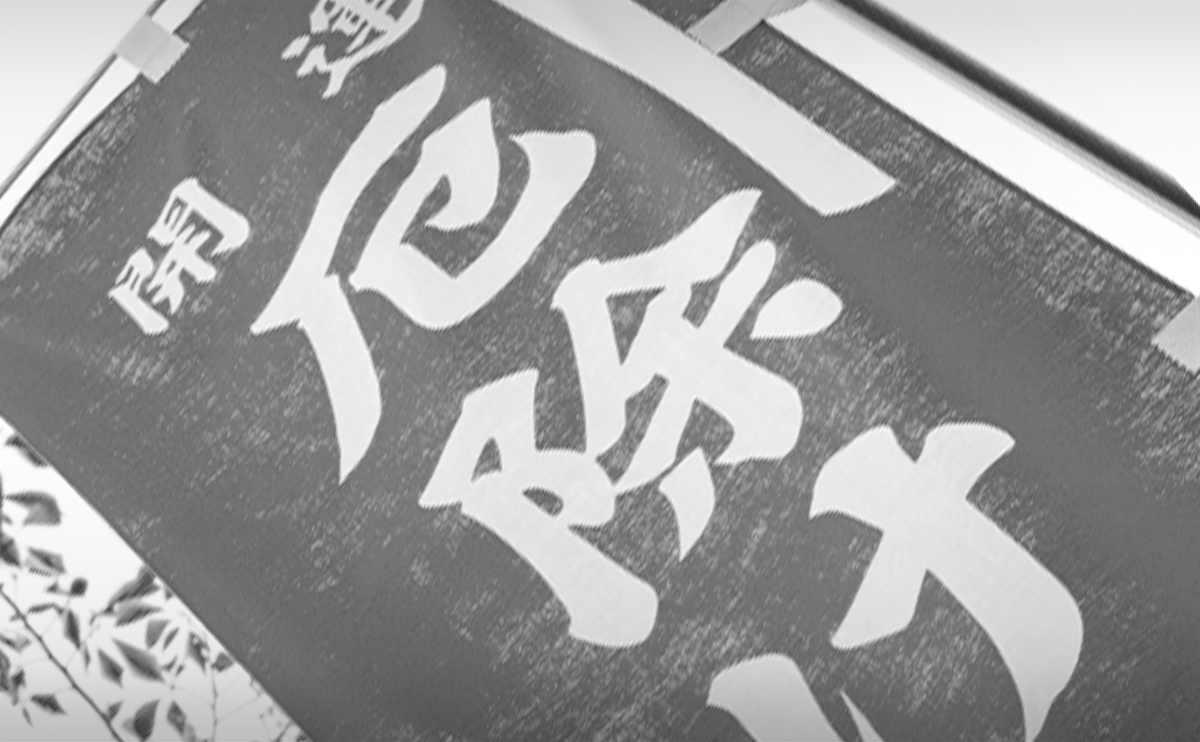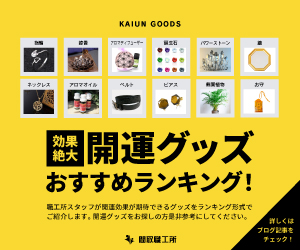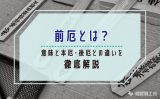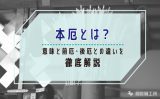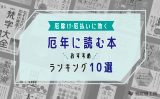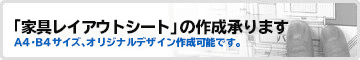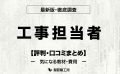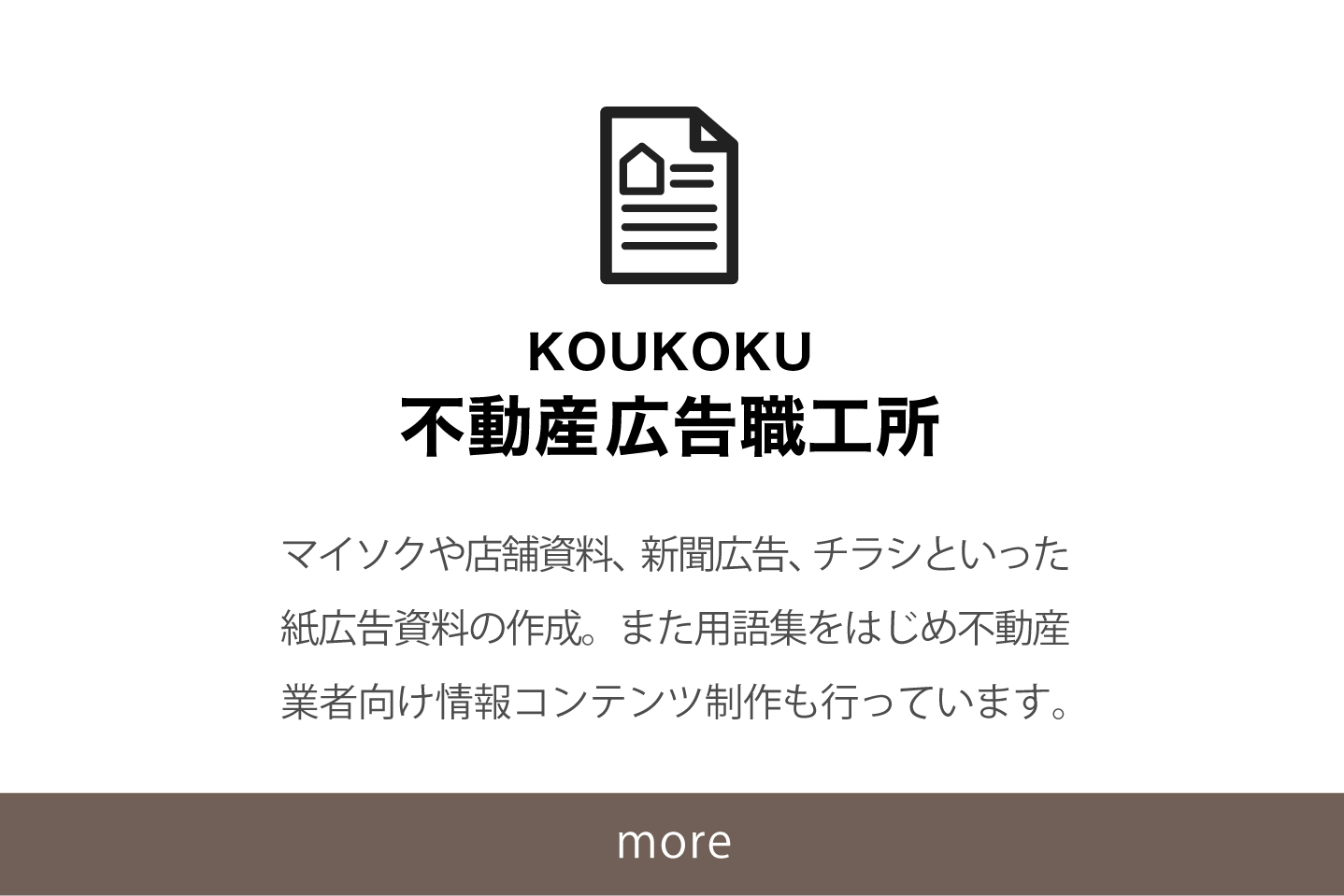人生の大きな節目に訪れる厄年。その中でも、特に災難が降りかかりやすく、最も注意が必要とされる中心の年が本厄です。「本厄って、具体的に何をする年なの?」「前厄や後厄とどう区別したらいいの?」と、漠然とした不安を感じている方も多いでしょう。本厄は、単に迷信として恐れるものではなく、身体的な変化や社会的責任が増す年齢と重なるため、人生の転機として古くから意識されてきた自己点検の期間です。
この記事では、本厄の正確な意味や由来、そして前厄・後厄との明確な違いを解説します。さらに、本厄を安心して乗り切るための心構えや、厄払いの方法までご紹介。本厄を正しく理解し、過度に恐れることなく、この重要な時期を健やかに、2026年も前向きに過ごすための参考にしてください。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
本厄とは?
本厄とは、厄年(厄の期間)を構成する3年間(前厄・本厄・後厄)のうち、ちょうど真ん中にあたる年を指します。昔から、この本厄の年が最も災厄が起こりやすく、心身ともに変化や不調が出やすい年だと考えられています。一般的に、数え年で男性は42歳、女性は33歳など、体力や環境が大きく変化しやすい「大厄」の時期も本厄に含まれます。この1年を無事に過ごすことが、人生を次のステージへと安定して進めるための重要な鍵となります。
本厄の意味
本厄は「災厄が最も強く訪れる年」という意味合いが強いですが、現代においては人生の基盤を見直し、心身のメンテナンスを徹底する年と解釈されます。厄年が設定されている年齢は、社会的地位が安定したり、家庭内の責任が増したりする時期と重なるため、知らず知らずのうちに無理を重ねてしまう傾向があります。本厄は、その無理が表面化しやすい年。だからこそ、立ち止まって自分の健康や生活態度を顧みる警告のサインであり、自立した大人としての人生を見直す機会なのです。
本厄の由来・なぜあるのか
本厄の考え方は、日本の陰陽道や古くからの年齢信仰に由来しています。特定の年齢を人生の変わり目と捉え、運気が不安定になる時期だと考えられてきました。特に、男性の42歳を「死に(しに)」、女性の33歳を「散々(さんざん)」と語呂合わせする俗説もあり、災厄を避ける意識を強めてきました。つまり、本厄の慣習は、科学的な根拠というより、人生の節目の自戒として古くから受け継がれてきたもの。「人生の大きな節目で、心身を休め、慎重に生活を見直しましょう」という先人たちの知恵と教えが、本厄という形になっているのです。
厄年の基本的な意味やその由来、歴史的背景について【厄年とは?】で詳しく解説。厄年の一年間をどのように過ごせば良いのか、心構えや伝統的な慣習まで紹介しています。
| 前厄 | → | 本厄 | → | 後厄 |
|---|---|---|---|---|
|
厄が徐々に近づく |
災厄が最も強く訪れる年 |
厄が徐々に遠ざかる |
本厄の年齢と男女別の特徴
本厄の年齢は、男女で異なり、いずれも人生の大きな転機と重なっています。これは、古来より男女の社会的役割や身体的な変化のタイミングが異なると考えられてきたためです。厄年は、生まれた年を1歳とする「数え年」で計算されます。男性の大厄は42歳、女性の大厄は33歳と定められており、それぞれの性別における心身のピークや変化が訪れやすい時期を警告しています。この章では、男女別の本厄年齢と2026年に本厄を迎える生まれ年を表にまとめました。その年代特有の注意点を見ていきましょう。
男性の本厄年齢
男性の本厄は25歳、42歳、61歳の3回です。
| 本厄年齢(数え年) | 実年齢(満年齢) | 生まれ年(例:2026年本厄の場合) |
|---|---|---|
|
25歳 |
24歳 |
平成15年(2003年) |
|
42歳(大厄) |
41歳 |
昭和60年(1985年) |
|
61歳 |
60歳 |
昭和41年(1966年) |
特に42歳は大厄(たいやく)と呼ばれ、最も重要な本厄とされています。この時期は、仕事で責任が重くなり、社会的ストレスが増大しやすい一方で、健康面では生活習慣病などのリスクが高まり始めます。そのため、働き盛りの無理が祟る年として、健康診断の徹底や過労を避けることが極めて重要です。25歳は社会人として本格的に始動する時期、61歳は定年など人生の大きな区切りに当たります。
女性の本厄年齢
女性の本厄は19歳、33歳、37歳の3回です。
| 本厄年齢(数え年) | 実年齢(満年齢) | 生まれ年(例:2026年本厄の場合) |
|---|---|---|
|
19歳 |
18歳 |
平成22年(2010年) |
|
33歳(大厄) |
32歳 |
平成6年(1994年) |
|
37歳 |
36歳 |
平成2年(1990年) |
女性の33歳も大厄とされ、最も注意が必要です。30代前半は、出産や育児、キャリアアップなど、ライフイベントが集中しやすい時期です。特に出産やホルモンバランスの変化による体調の揺らぎ、子育てや仕事の両立による精神的な疲労が蓄積しやすいため、体を冷やさない、無理をしないといった、心身を労わる意識が求められます。19歳は社会への転機、37歳は家庭と仕事の両立に悩む時期と重なります。2026年の厄年については、すぐに確認できる【2026年 厄年早見表】をご覧ください。
前厄・後厄との違い
本厄は厄年3年間(前厄・本厄・後厄)の中心であり、最も注意すべき年です。しかし、厄年の期間は本厄の前後1年を含めた合計3年間で構成されています。それぞれの年が持つ意味合いを正しく理解することで、3年間を通して計画的に過ごすことができます。前厄は「厄が近づき始める年」で心構えを始める期間、後厄は「厄の余波が残っている年」で油断せず厄を完全に落とす期間です。本厄と、前後の2年間がどう異なるのか、それぞれの役割と心構えを詳しく解説します。
前厄との違い
前厄(まえやく)は、本厄の1年前にあたり、厄が近づき始める年とされています。本厄が災厄のピークであるのに対し、前厄はウォーミングアップ期間です。厄の影響が徐々に現れ始めるため、小さなトラブルや体調の異変としてサインが出ることも。このサインを見逃さず、厄払いなどで本格的な本厄の準備を始めるのが前厄の過ごし方です。本厄での大きな災いを避けるため、生活の見直しをスタートさせるのが前厄の役割と言えます。「前厄」の基本的な意味にフォーカスし、なぜ本厄の前の年から注意が必要なのかを【前厄とは?】で解説しているので、こちらもご覧くださいね。
後厄との違い
後厄(あとやく)は、本厄の翌年にあたり、厄が徐々に遠ざかっていく年とされています。本厄が災難が最も集中する年であるのに対し、後厄は厄の余波が残っている年です。本厄で溜まった心身の疲れや、厄の影響が完全に消えていない状態のため、油断は禁物です。しかし、本厄ほどの強い警戒は必要なく、謙虚な気持ちで過ごし、本厄の間に改善した生活習慣を継続させることが大切。後厄の時期に改めてお祓いを受けることで、完全に厄を落とし、3年間の厄年を終えるという区切りをつけます。気が緩みがちな後厄の時期の過ごし方や、本厄・前厄との意味の違い、最後まで無事に過ごすためのポイントを【後厄とは?】で分かりやすく説明しています。
本厄で注意すべきこと
本厄の時期は、心身ともに無理が表面化しやすく、環境の変化やストレスが災いとして現れやすいとされます。そのため、やみくもに恐れるのではなく、この時期特有の心身のバランスの崩れや、環境の変化に合わせた具体的な注意を払うことが大切です。最も重要なのは、無理をしないことと、大きな決断を避けることです。健康面では、多忙な時期だからこそ検診を徹底し、生活習慣を見直しましょう。また、仕事や家庭においては、人生を左右するような新しい挑戦や大きな資金の移動は一旦見送るのが賢明です。この章では、本厄を無事に乗り切るために特に意識したい、具体的な注意点を解説します。
健康面での注意
本厄の時期は、心身に大きな変化が現れやすい時期です。特に、無理をしないことと、異常を見逃さないことが重要です。健康面で具体的に気を付ける点は下記3点です。
- 定期的な健康チェック:人間ドックや健康診断を必ず受診し、体の小さな変化も放置しないこと。
- 十分な休養:過労を避け、睡眠時間や休息を確保し、疲労を翌日に持ち越さない生活習慣を心がけましょう。
- ストレス管理:趣味や運動など、自分なりのストレス解消法を見つけ、心を健やかに保つ努力をしましょう。
仕事・家庭での注意点
人生を大きく左右するような、急な変化や大きな決断は避けるのが賢明です。仕事・家庭で具体的に気を付ける点は下記3点です。
大きな借金や投資を避ける
不動産や車の高額な買い物、または投機的な大きな借金や投資は、本厄の期間中は一旦見送るのが無難です。
転職や独立は慎重に
新しい環境でのチャレンジはストレスも大きいため、本厄を避けて前後で計画を立てるようにしましょう。
人間関係の調和
家族や職場の人間関係では、謙虚な姿勢と感謝の気持ちを忘れず、感情的な対立や決断を避けるように努めましょう。
厄年にやってはいけないとされる代表的な10項目を【厄年にやってはいけないこと】でリストアップ。運気を下げずに穏やかに過ごすため、ぜひご確認ください。また、こちらでは本厄で避けたいチェックリストをまとめたので、ご活用ください。
【チェックリスト】本厄で避けたい行動5つ
- 大きな借金やローンを組むこと
- 衝動的な転職や起業など、基盤を揺るがす挑戦
- 不動産や車の購入など、高額な財産の移動
- 感情的な人間関係の決断(離婚、絶縁など)
- 無理な夜更かしや過労など、健康を害する行為
本厄の過ごし方と厄払い
本厄は、単に災いを恐れて引きこもる年ではありません。むしろ、心身を清め、人生の基盤を整えるための貴重な準備期間と捉えることが大切です。古来から行われてきた厄払い(厄除け)は、災厄を遠ざけるだけでなく、「今年は慎重に過ごします」という心構えの区切りをつけるためにも有効です。厄払いを済ませたら、残りの1年間は徳を積む行動や、内面を磨く自己投資に集中しましょう。新しい大きな挑戦は避ける代わりに、基盤を固める努力や、人への感謝を忘れない謙虚な生活を送ることが、本厄を平穏に乗り切り、次の飛躍に繋げるための最善の過ごし方となります。具体的な厄払いの方法と、おすすめの心構えをご紹介します。
厄払い・お祓いの方法
厄払い(または厄除け)は、厄年特有の災厄を神仏の力で祓い、平穏を願う儀式です。
時期
一般的に、新年を迎えてから節分(2月3日頃)までに受けるのが最適とされます。もし時期を逃しても、思い立ったときに受け付けてくれる神社やお寺も多いです。
場所
地元で信仰を集める神社や寺院、または厄除けで有名なところへ出向きましょう。
心構え
厄払いは、単に厄を払うだけでなく、「これから1年、気を付けて過ごします」という神様への決意表明でもあります。感謝と敬意をもって臨みましょう。
おすすめの過ごし方
本厄の1年間は、人生の準備期間と位置づけ、内面に目を向けた過ごし方がおすすめです。以下3つのおすすめを紹介します。
徳を積む行動
人のために尽くす、ボランティアに参加するなど、「陰徳(いんとく)」を積む行動は、厄を分散させ、開運に繋がると言われています。
基礎固めの学習
資格取得のための準備や読書など、内面を豊かにする活動に時間を使います。新しい挑戦よりも、今の仕事や生活の基盤を固める努力をしましょう。
ゆとりある生活
スケジュールに余裕を持ち、あえてゆっくりと流れる時間を意識的に作ることで、心身の安定を保つことができます。
2026年度の厄年一覧は【2026年 厄年早見表】でご確認ください。また、厄年を乗り越えるためのヒントを与えてくれる本は【厄年に読む本】で紹介しているので、おすすめです。
まとめ|本厄を正しく理解して安心して過ごす
本厄とは、厄年3年間のうち最も災厄が集中し、心身のケアが求められる年です。しかし、これは決して恐れるべき不運な年ではありません。男性の42歳、女性の33歳といった人生の重要なタイミングで、健康や生活を見直しなさいという先人からの大切なメッセージなのです。2026年の本厄を平穏に、そして有意義に乗り切るための最終的なポイントは、以下の通りです。
- 厄払いで清める: 年明けから節分までに厄払いを受け、心身の区切りをつけましょう。
- 健康を最優先: 無理をせず、健康診断と十分な休養を徹底しましょう。
- 大きな決断は避ける: 転職や住宅購入など、人生の基盤を揺るがす決断は本厄の期間を避けて前後で計画しましょう。
本厄を過剰に恐れるのではなく「自分を見つめ直すチャンス」と捉え、地に足のついた謙虚で丁寧な生活を送ることで、必ずや平穏で豊かな次の人生へと繋がっていくはずです。日々忙しく過ぎていくと、ついつい自分のことは後回しになってしまいがちです。本厄を知ることで、自分の心とからだの声に耳を傾けるきっかけになれば幸いです。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.madori-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)