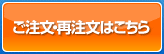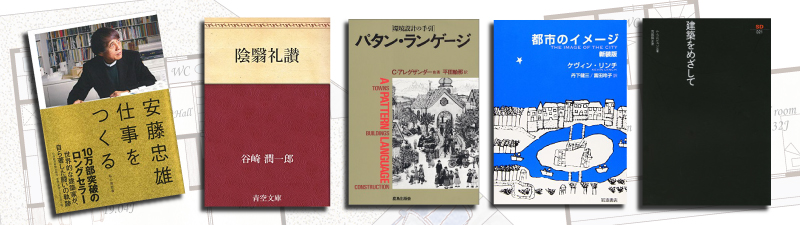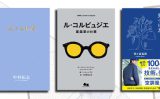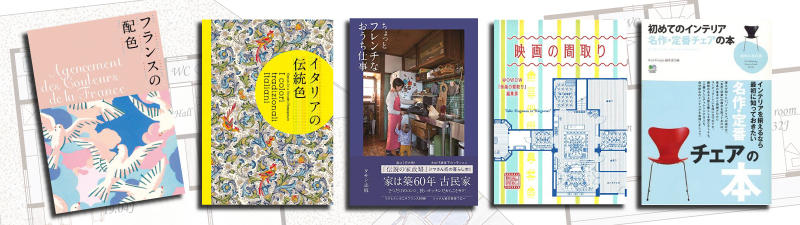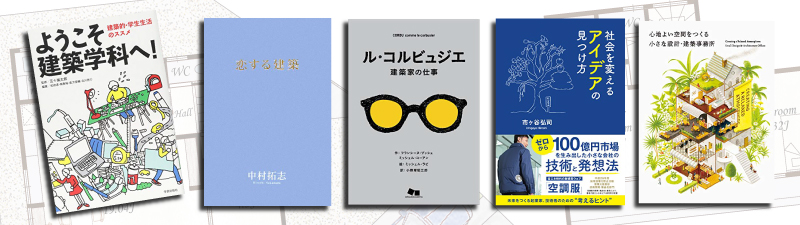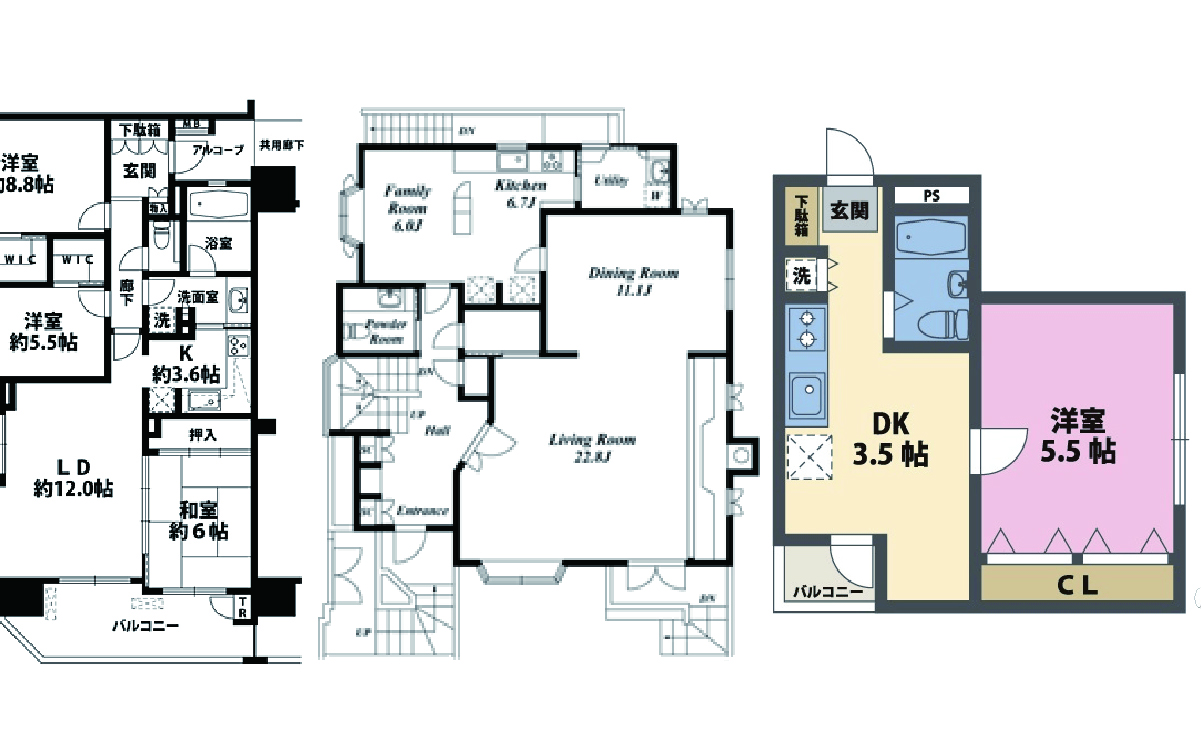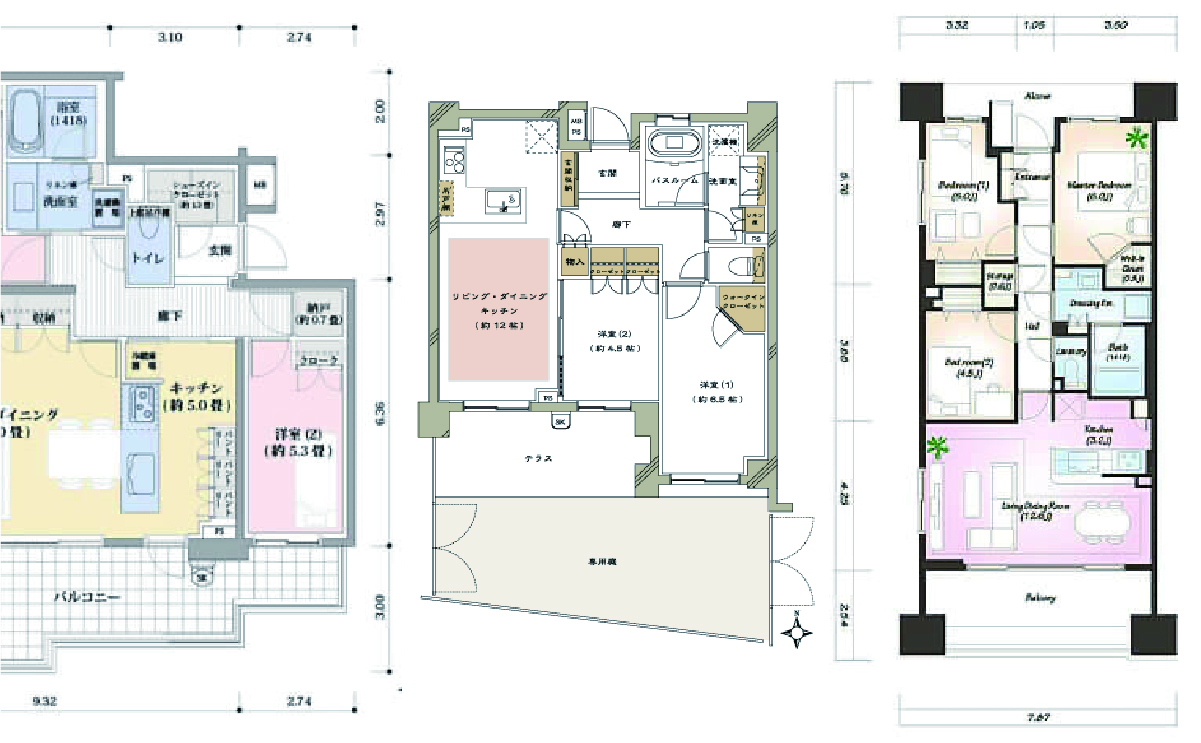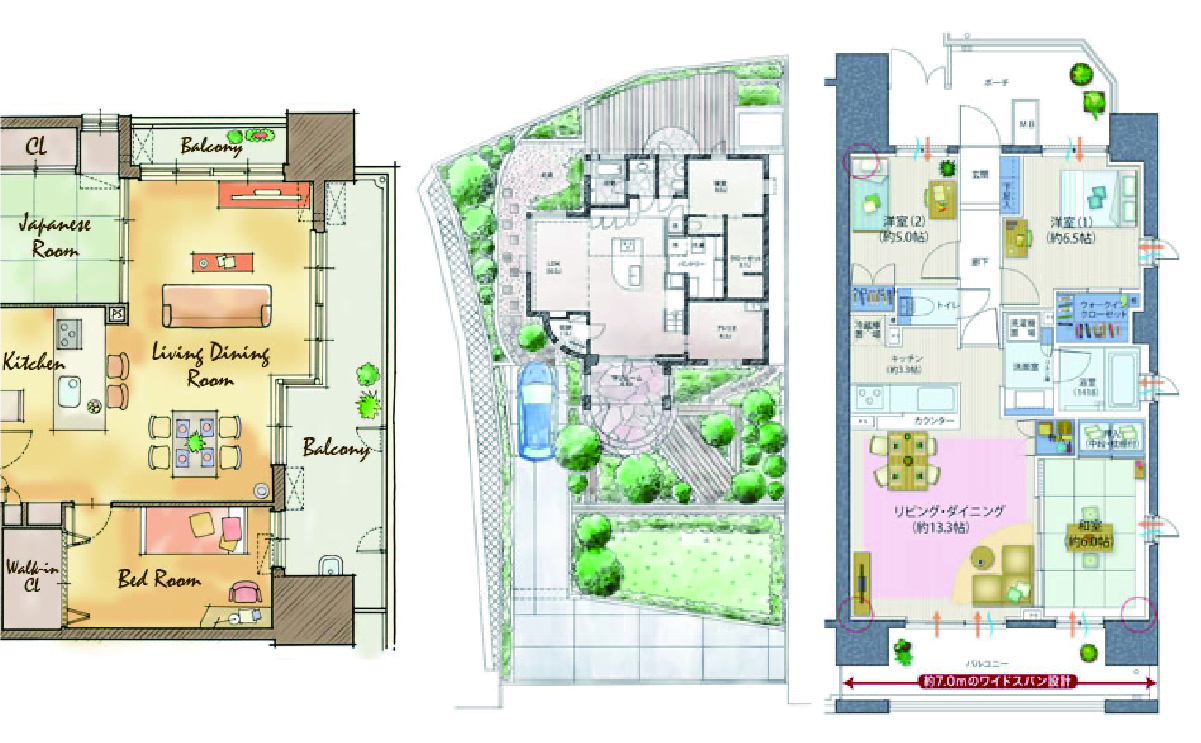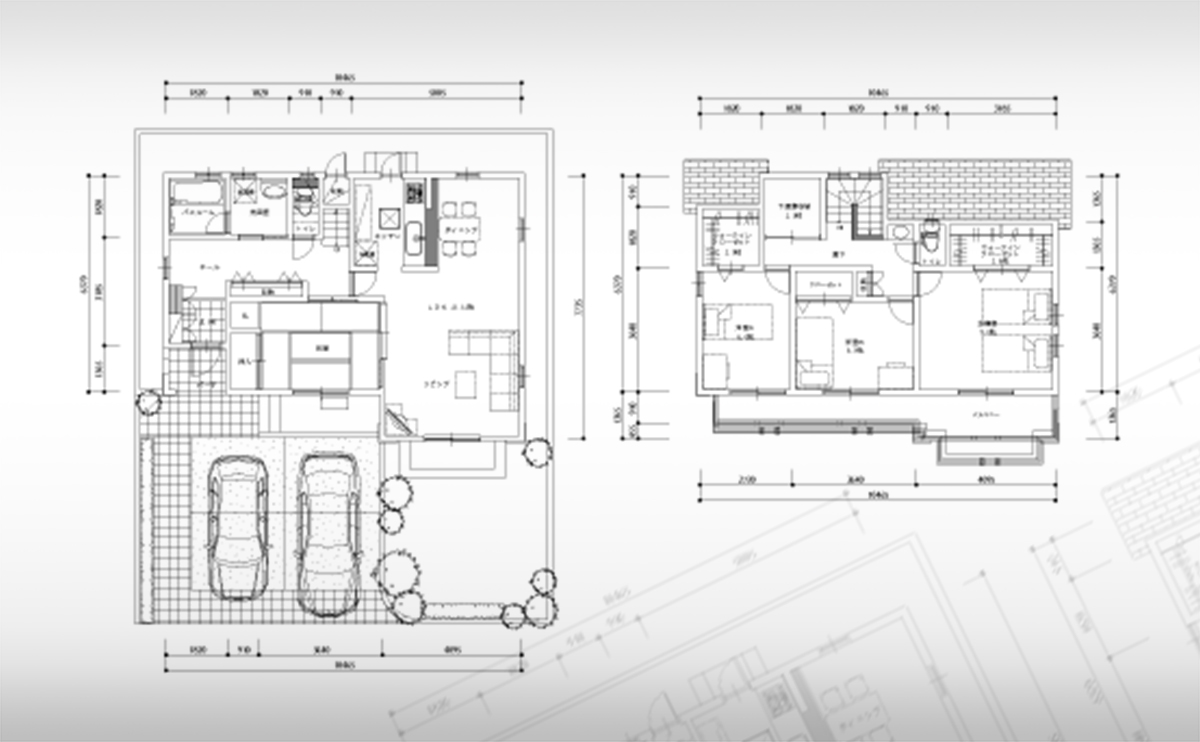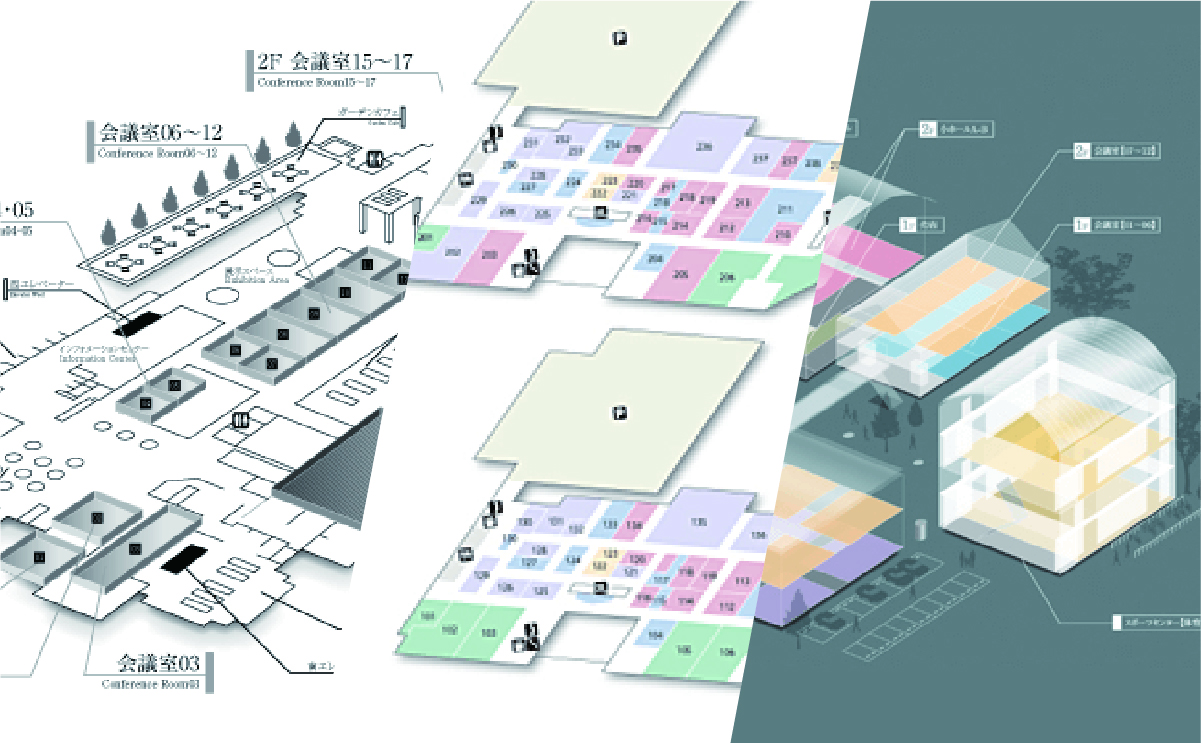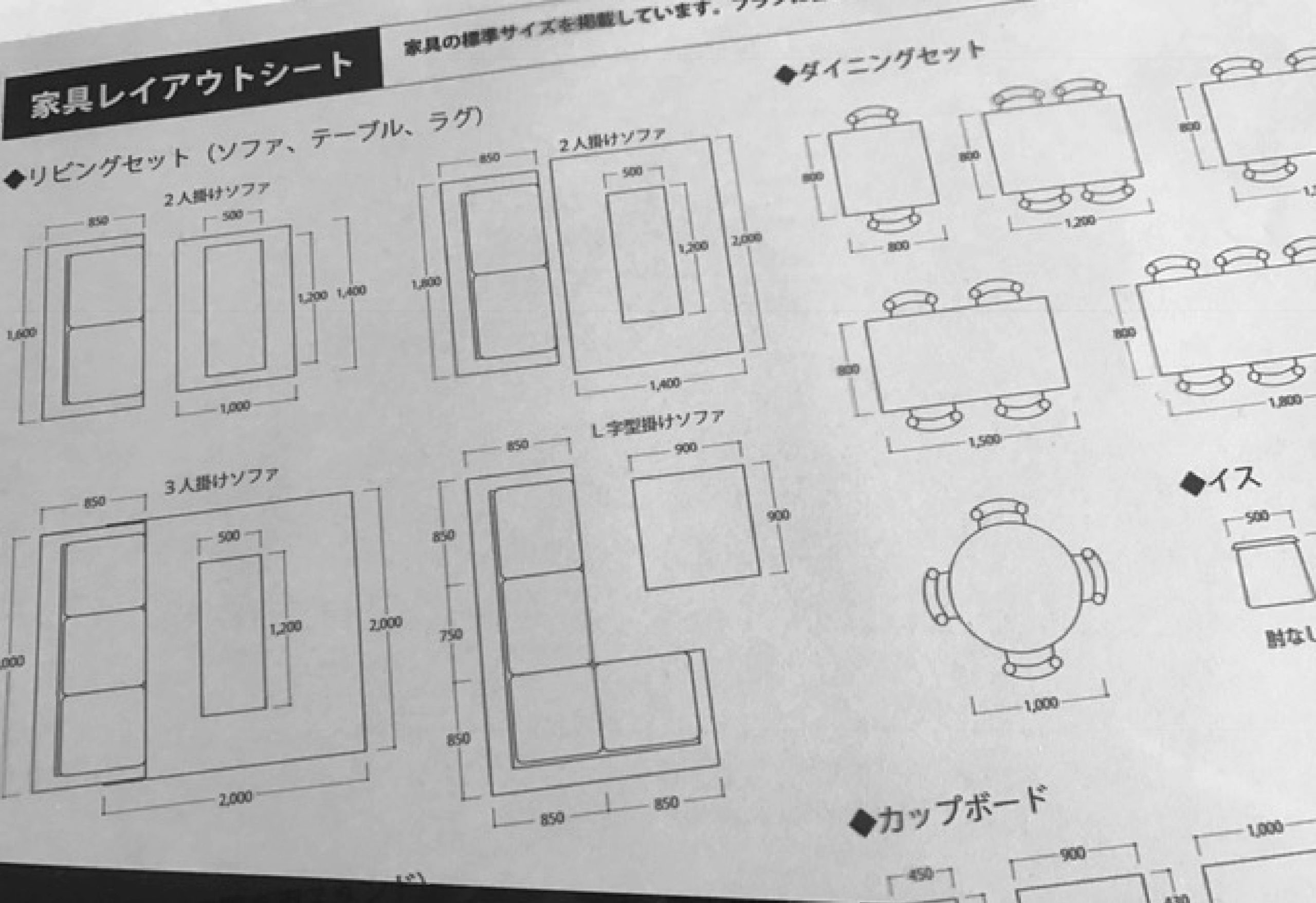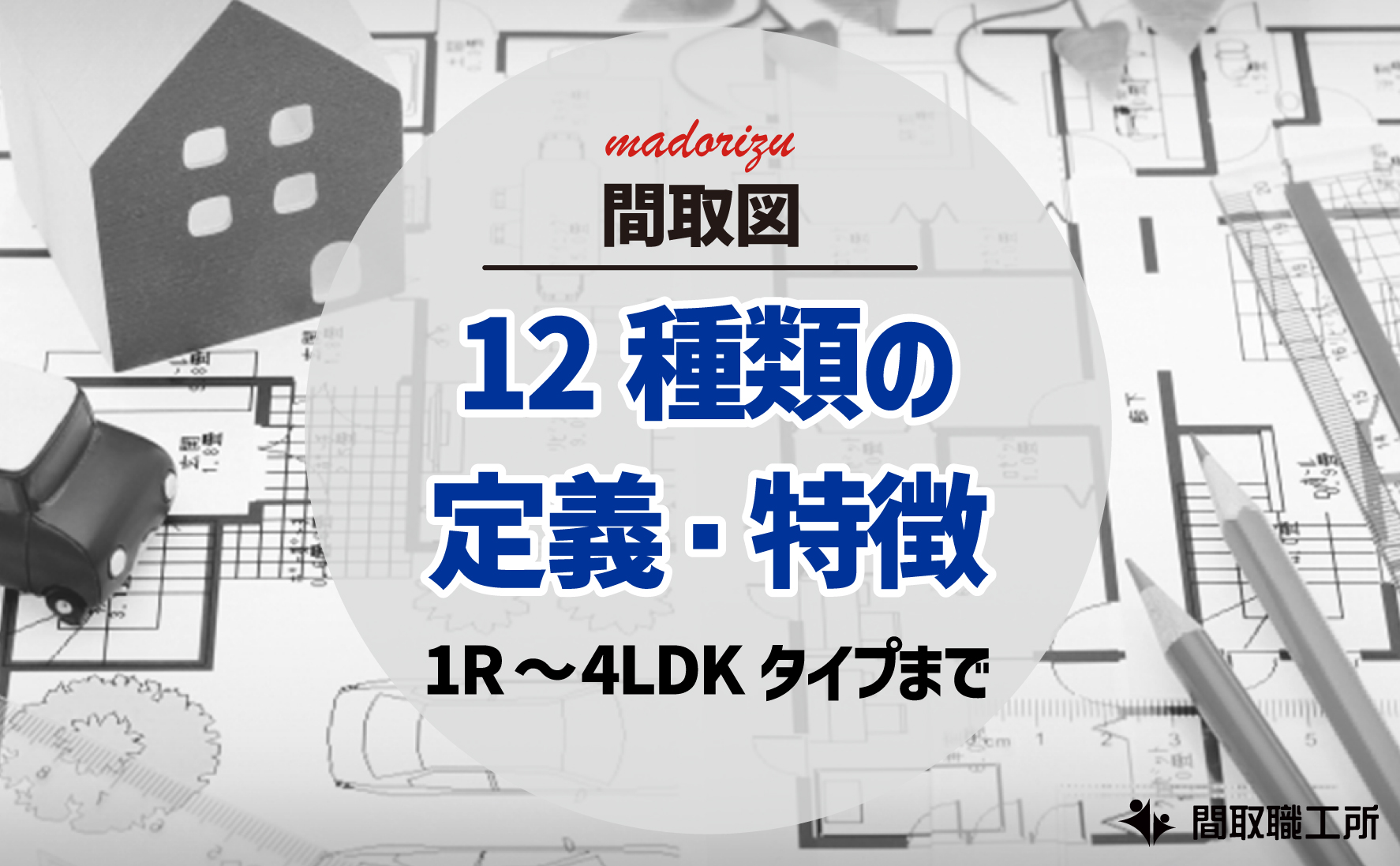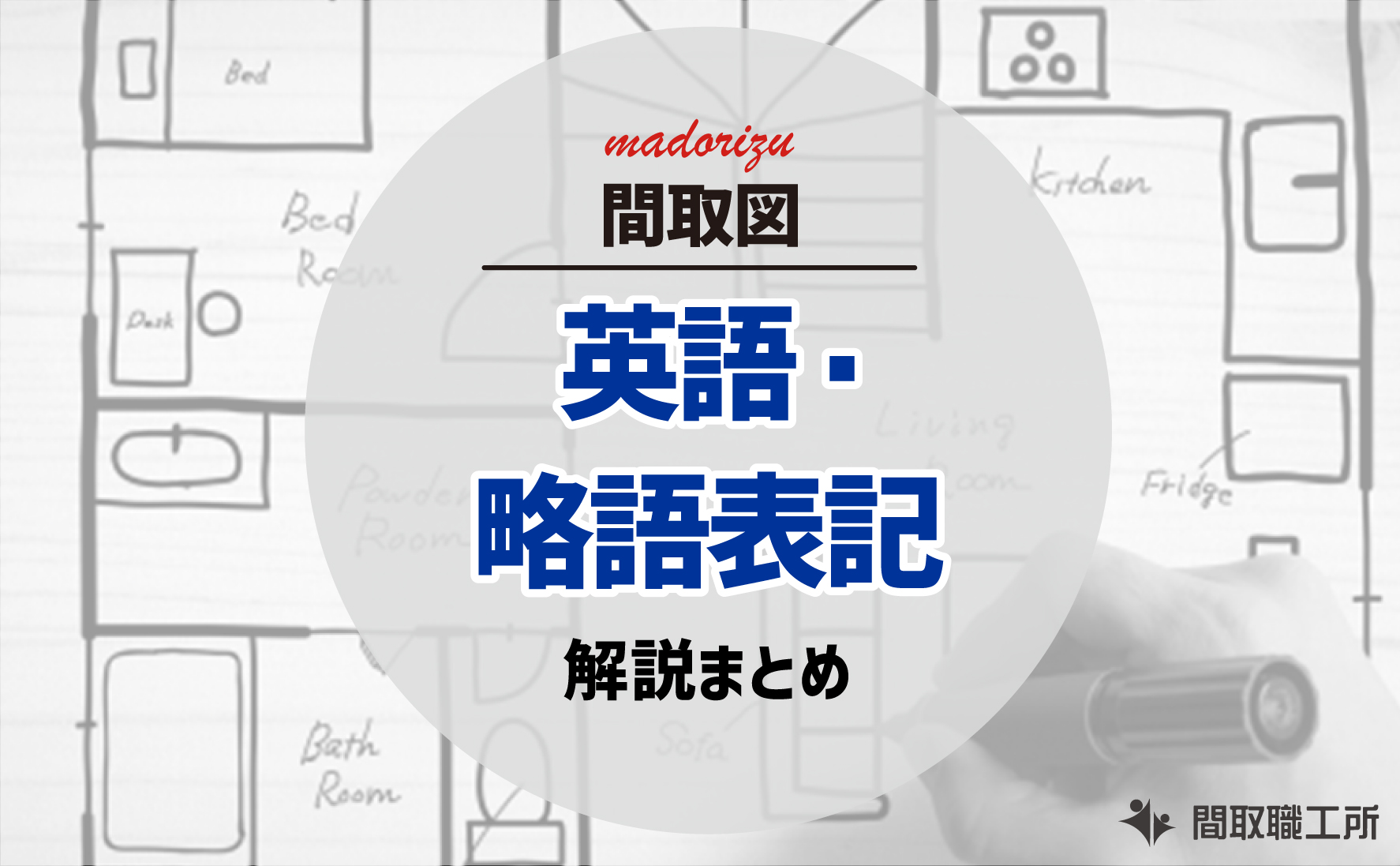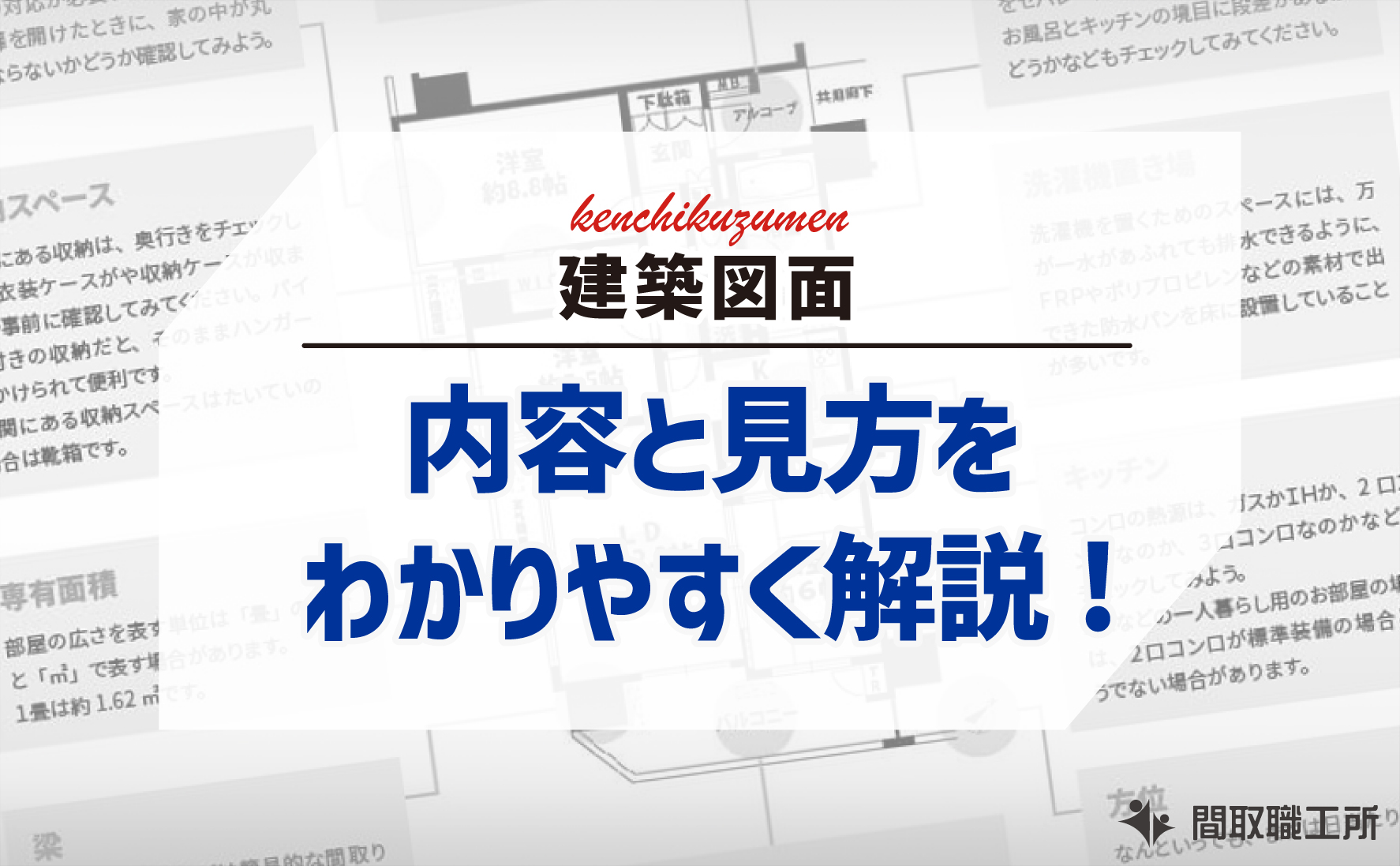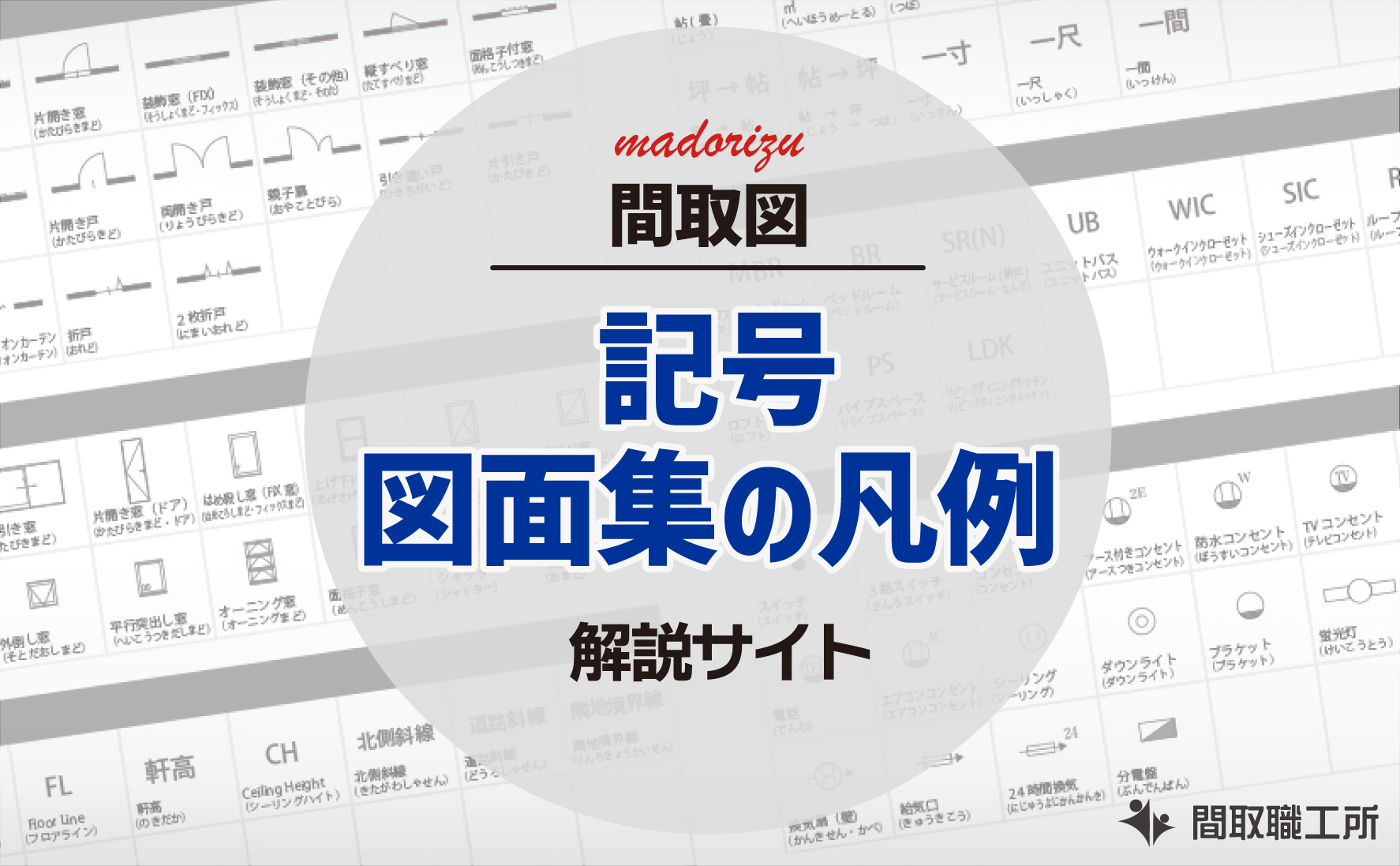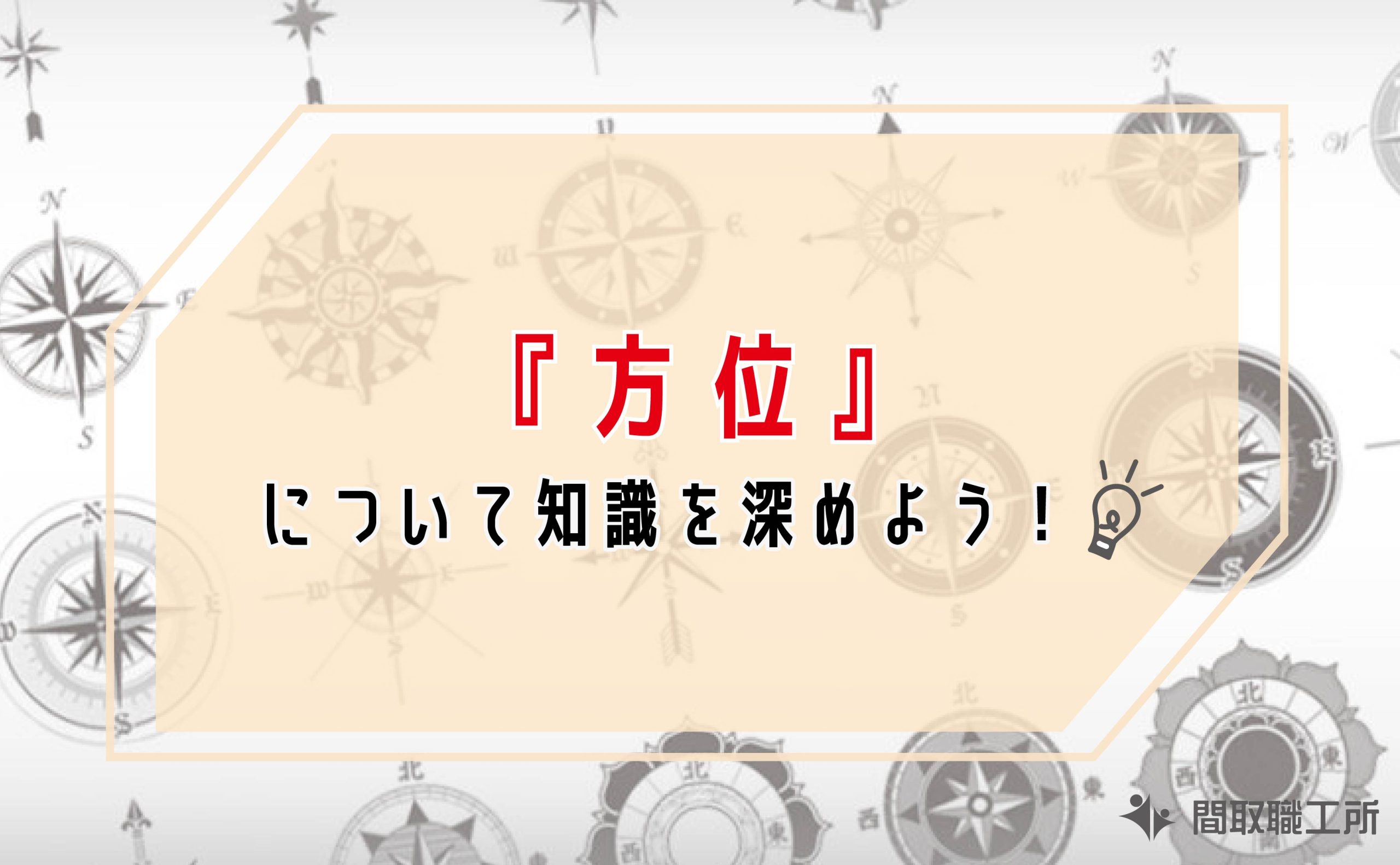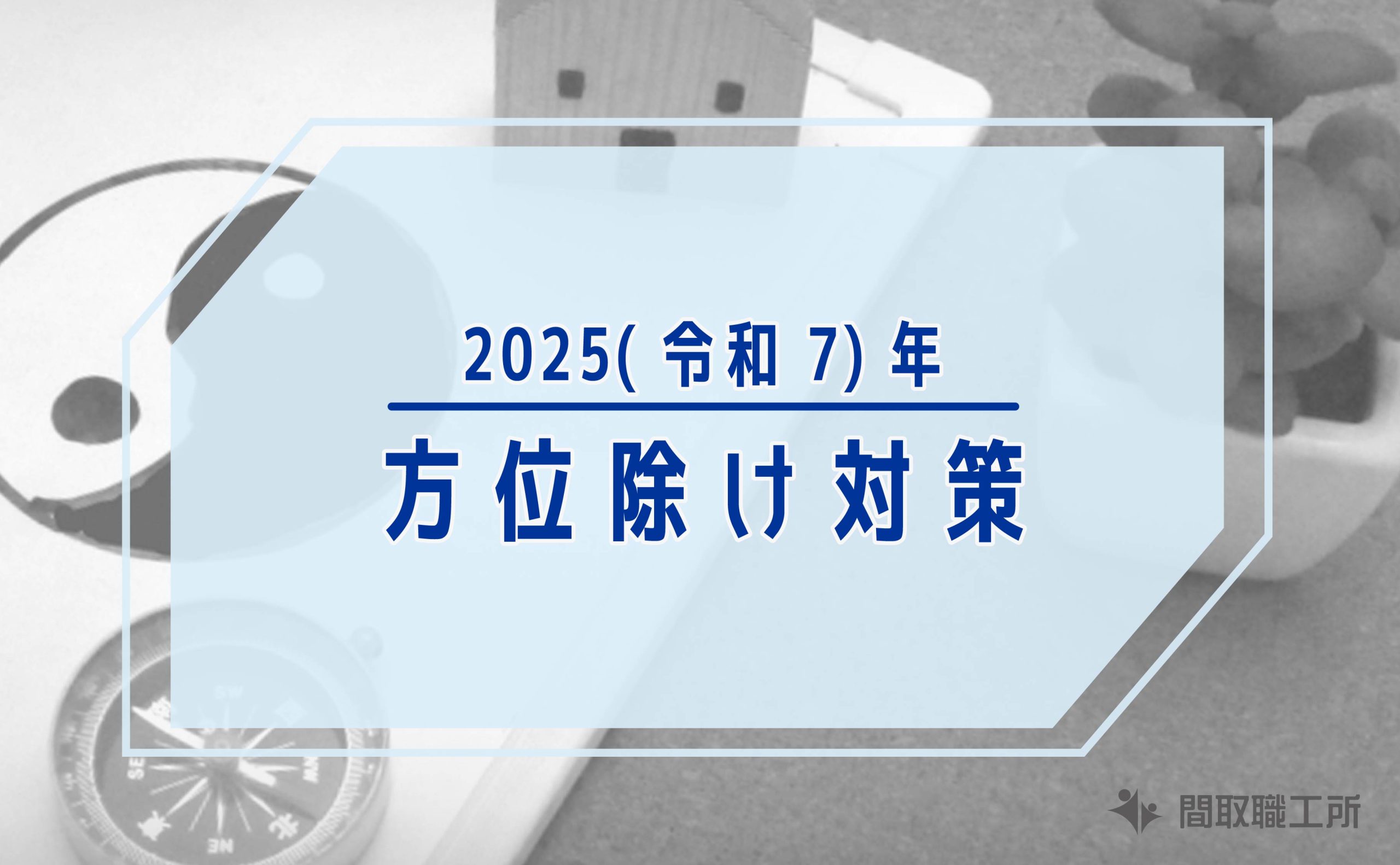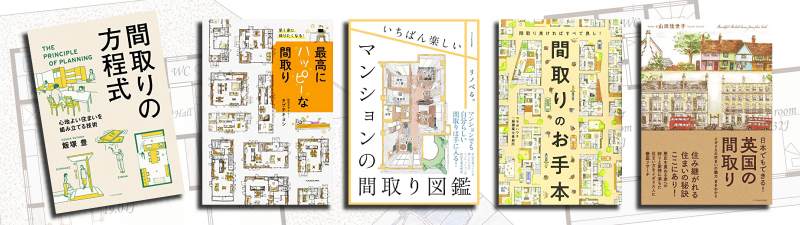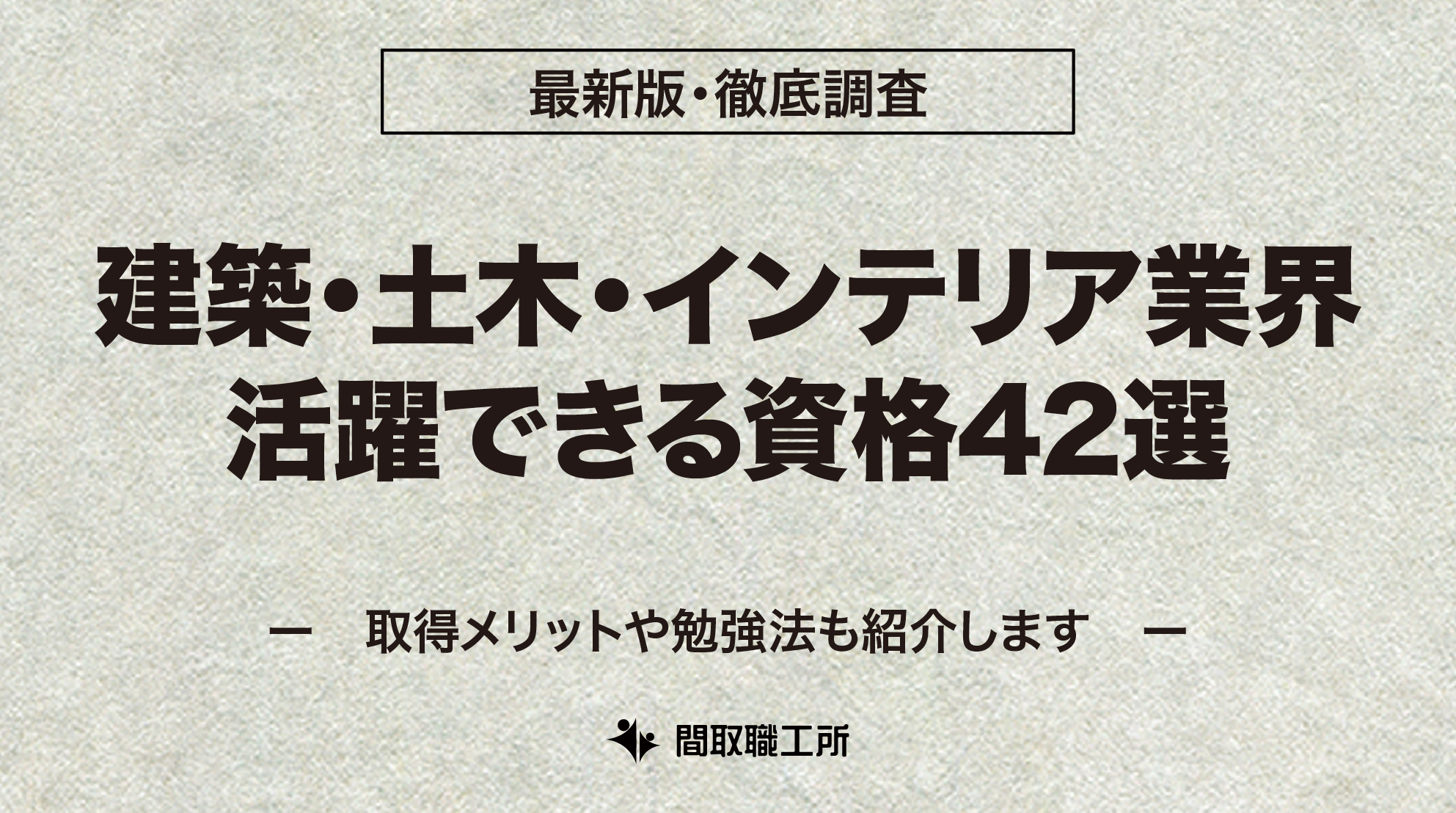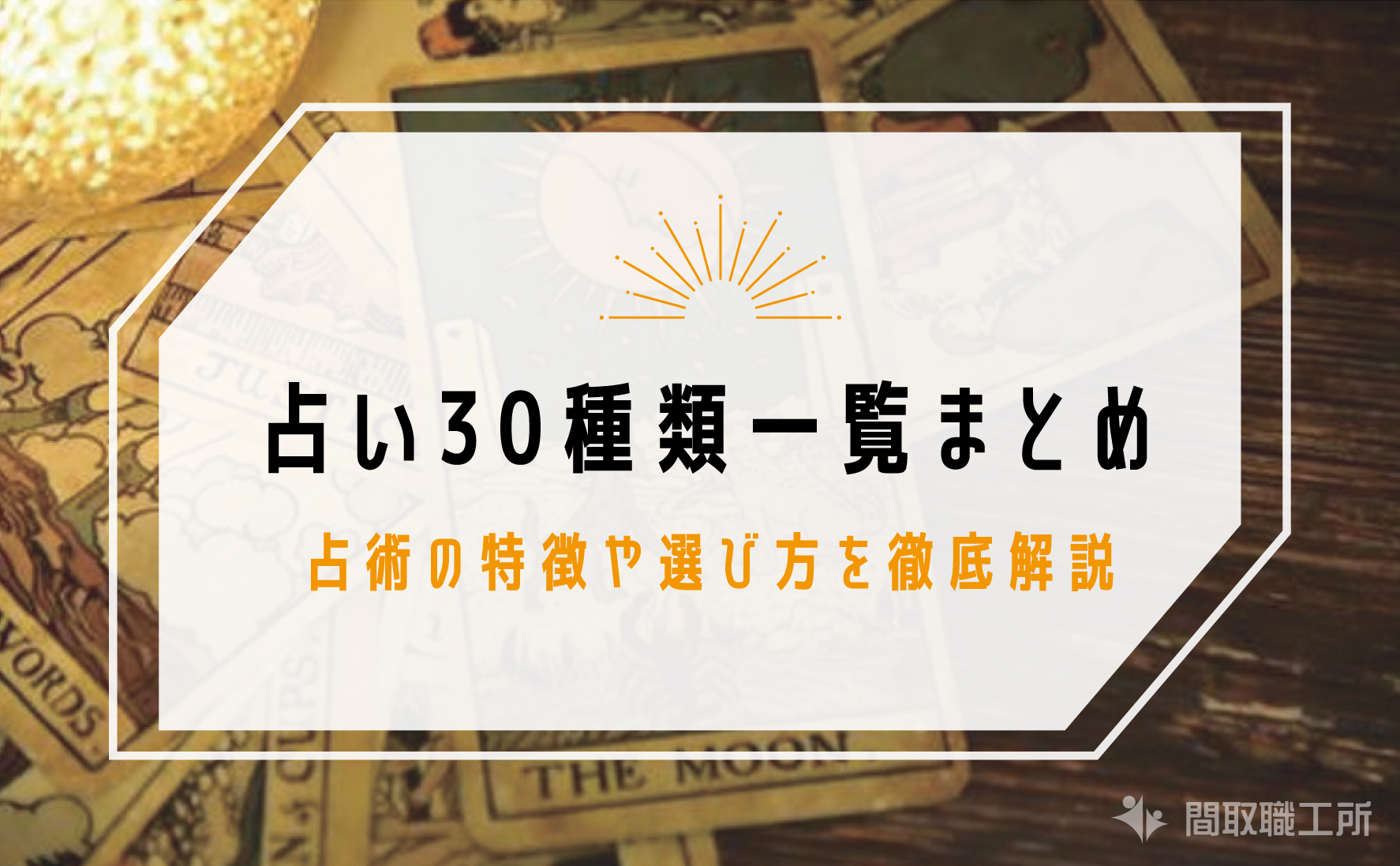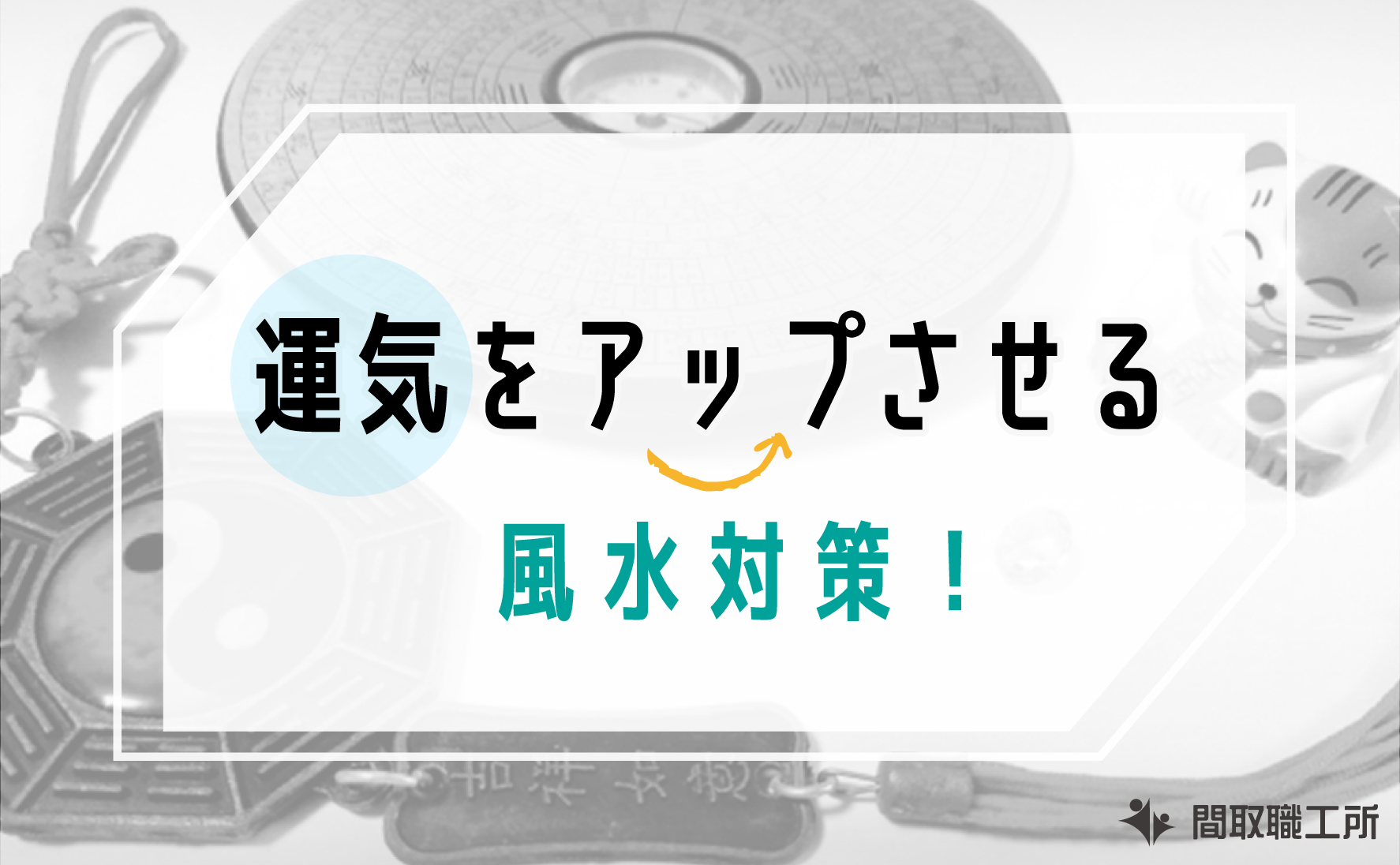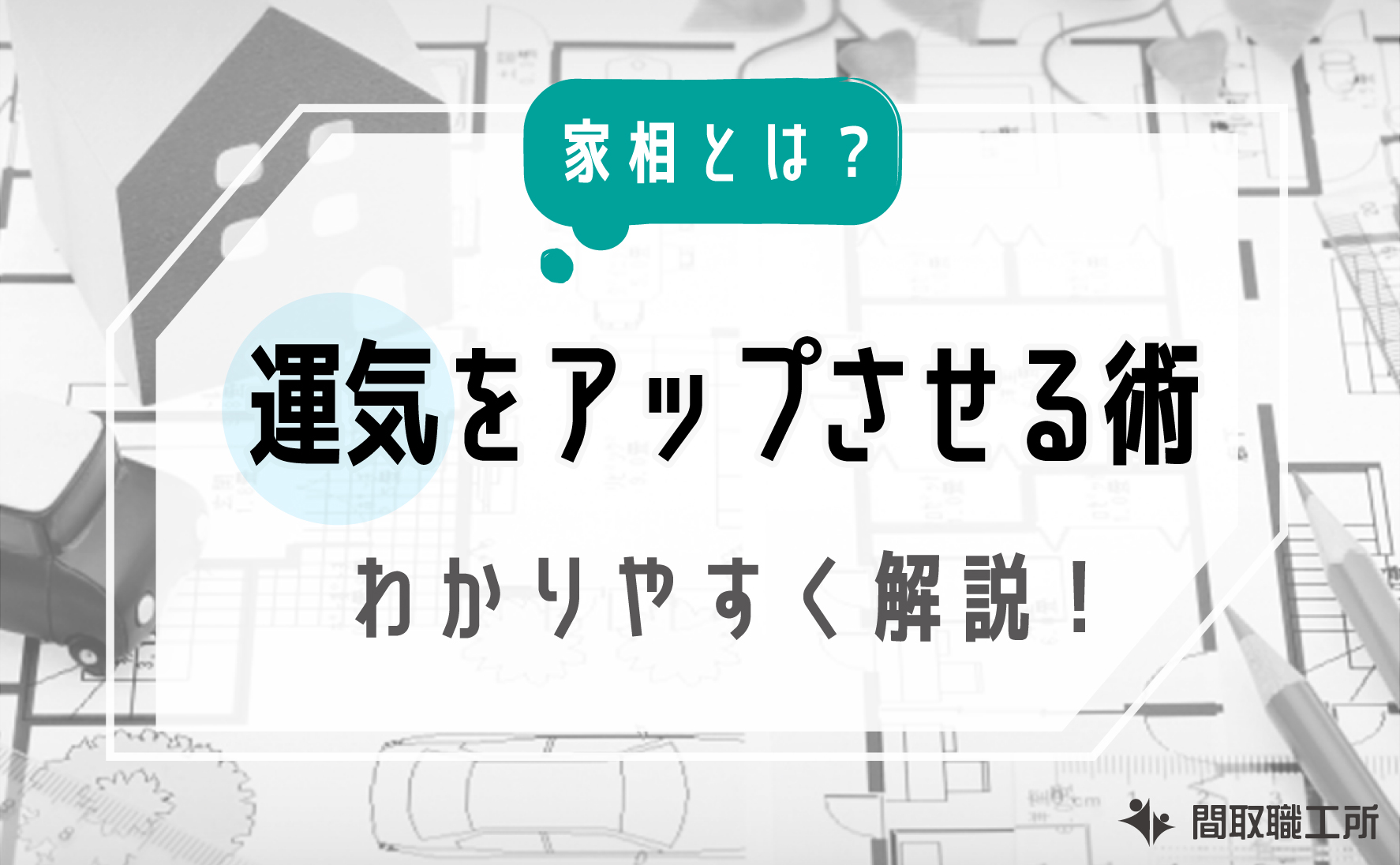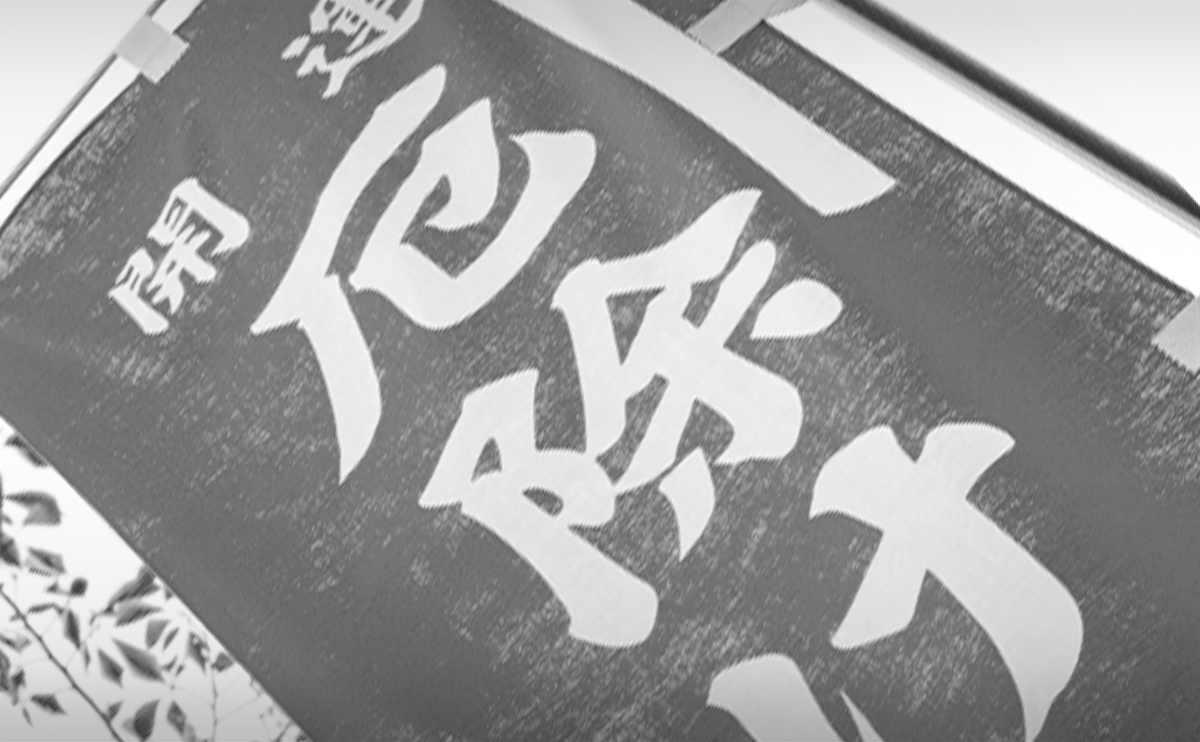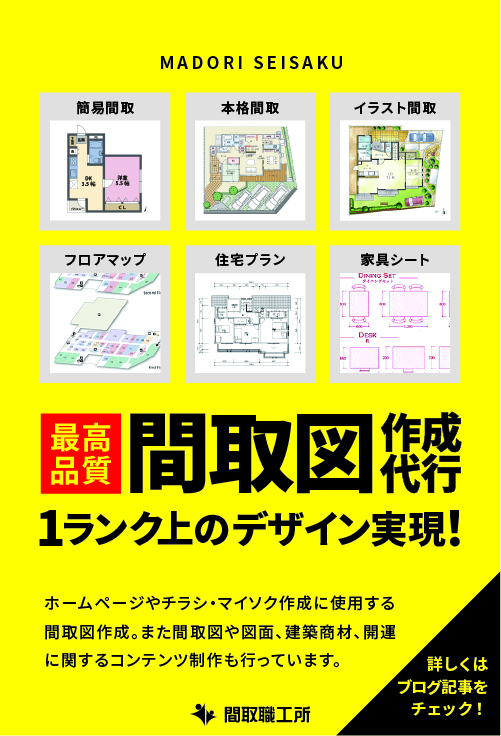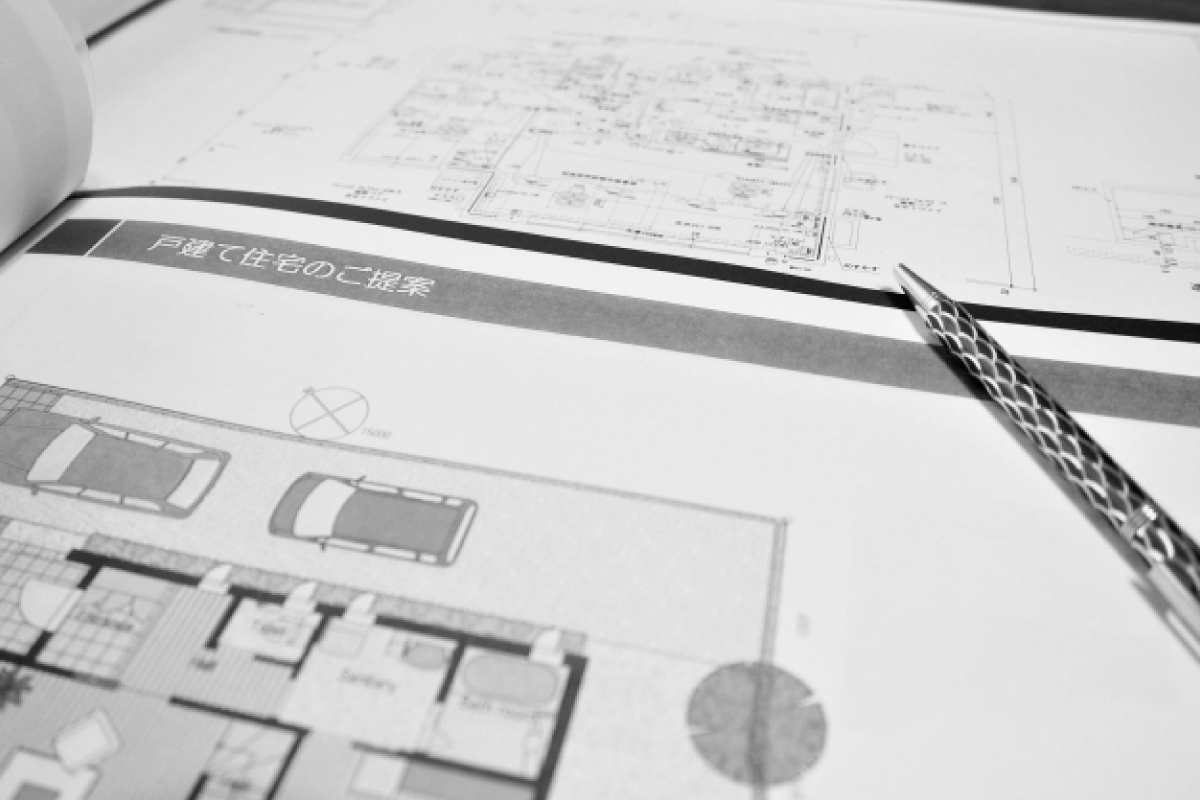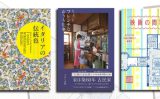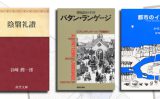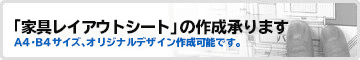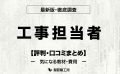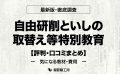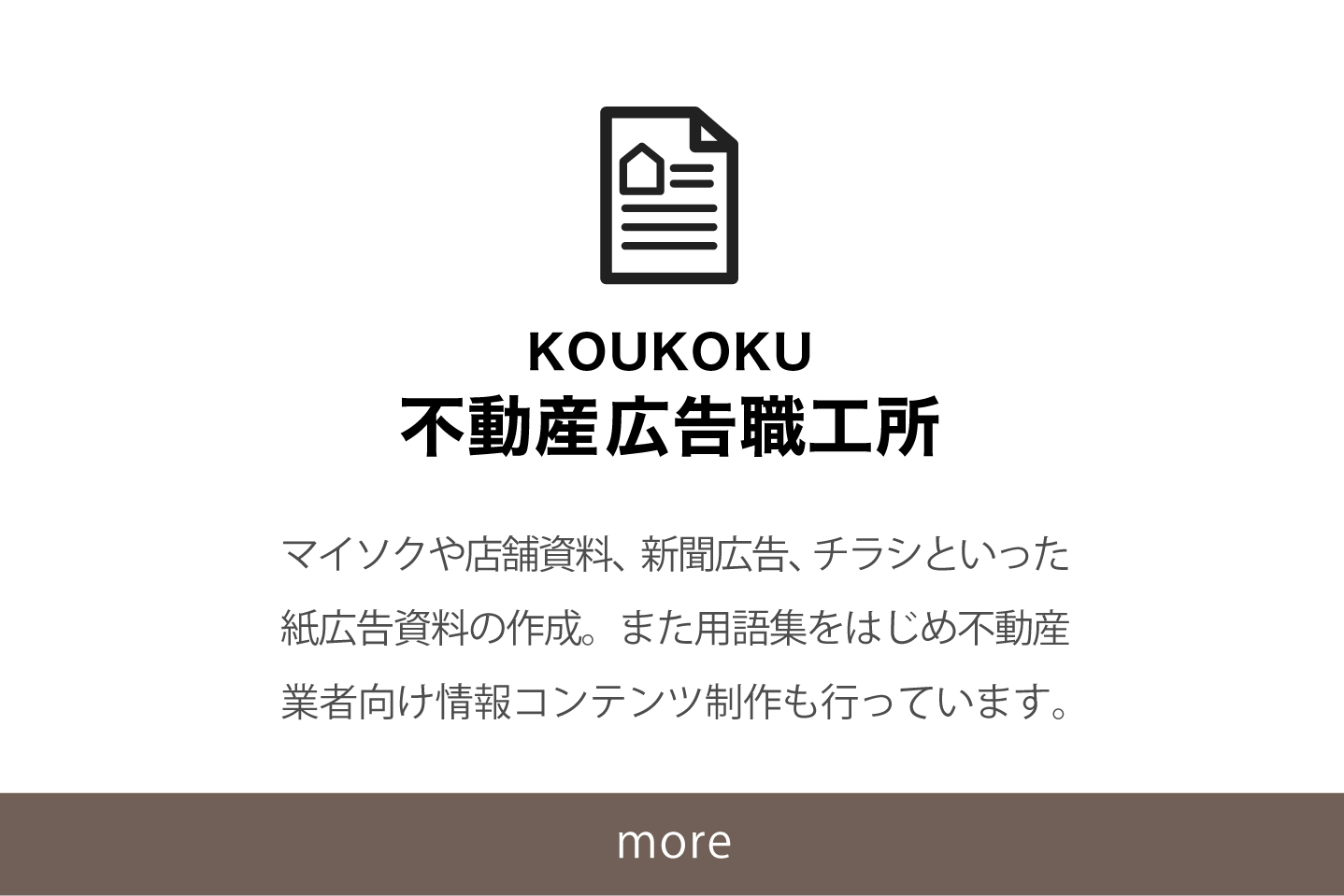今回は建築家を目指して頑張っている学生さんに、読んでほしいおすすめの本をランキング形式で紹介しています。建築関連の本はたくさんありますが、現在の私(建築士)が、学生時代の自分を顧みながら…こんな本を学生時代に読んでおけばよかったと思える本を紹介します。
有名建築家の本を読むのもいいですが、歴史を回顧したり…世界に目を向けたり…広く浅く建築に触れることは、とても大事なことです。下記で紹介する本はそんな貴方にぴったり。特に、建築士の私が、「建築の原点度」や「自分を磨く本」という項目でランキング化(★5つ)して紹介しています。建築を学ぶ際の参考にしてください。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
建築士が教える!建築学生におすすめの本ランキング10冊
名建築家の建築や有名な建築を見たり学びながら、魅了された建築や建築家を目指して課題に取り組んだり、コンペに参加したり。そして就職活動も始まると忙しい毎日。そんな建築学生に読んでほしい10冊をまとめました。いま第一線で活躍している多くの建築家たちがバイブルとしてきた本と言っても良い十冊です。歴史を学ぶことによって今を考える。歴史を知らなければ未来はつくれない。是非一読をお勧めします。
では順にご紹介しましょう。
【第1位】陰翳礼讃
建築に携わるものがほぼ知る名作
建築学生さんに、読んでほしいおすすめの本ランキング第1位は『陰翳礼讃』です。言わずと知れた文豪・大谷崎と言われた谷崎潤一郎の名作。1934年に発刊された本ですが、建築を学んできた人なら今現在でもほとんど知っているほどの名作です。部屋の隅々まで明るくして陰翳がなくなりつつある現代。本来の日本文化とは陰翳を美としその中から芸術や文化をを作り上げきたのであってそれこそ日本人の美学なのだということを身の回りのことから考察しています。大川裕弘氏の著者の言う陰翳を見事に撮影した写真入りとなり、イメージがどんどん入ってきます。大川氏は「婦人画報」「美しいキモノ」などが有名ですね。
| 著者 | 谷崎 潤一郎 (著者) 大川 裕弘 (写真) |
|---|---|
| 出版社 | パイインターナショナル |
| ページ数 | 256ページ |
| 建築の原点度 | ★★★★★ |
| 自分を磨くための本 | ★★★ |
【第2位】隠れた秩序―21世紀の都市に向かって
日本建築美学を都市スケールで考える
建築学生さんに、読んでほしいおすすめの本ランキング第2位は『隠れた秩序―21世紀の都市に向かって』です。都市計画家の芦原氏が西洋と東洋の都市の違いを考察し、東洋の都市には隠れた秩序があるのだと提言してます。西洋の建築の特徴は、形式主義・装飾主義・左右対称・正面性などが特徴ですが東洋、特に日本建築は内部や生活を重視、質感を重視すると提言しています。そしてその「曖昧性」が日本の「アメーバ都市」を生んでいると提言しています。この本も「陰翳礼讃」と並んで、日本建築美学の原点を都市というスケールの中で考えることができる一冊で学生の皆さんにはおすすめです。芦原氏の書籍は、他にも「街並みの美学」・「東京の美学」がある。
| 著者 | 芦原 義信 |
|---|---|
| 出版社 | 中央公論社 |
| ページ数 | 212ページ |
| 建築の原点度 | ★★★★ |
| 自分を磨くための本 | ★★★★ |
【第3位】仕事をつくる―私の履歴書
日本を代表する建築家 安藤忠雄氏の履歴書
建築学生さんに、読んでほしいおすすめの本ランキング第3位は『仕事をつくる―私の履歴書』です。学歴も実績もなく独学で建築を学び世界の建築家になった安藤忠雄氏。そのプロセスを自ら泥臭く紹介していく一冊。安藤ファンでなくとも是非読んでほしい一冊です。建築に対する強い思いやプロフェッショナル精神が伝わってきます。「仕事は自分で作らなければならない」これから建築の道を歩もうとしている若者に対する励ましと共にプロフェッショナルとは何かを教えてくれる一冊です。日本を代表する建築家の本は、学生のうちに当然ながら目を通しておきたいものです。 → 安藤忠雄氏の書籍一覧はこちら
| 著者 | 安藤 忠雄 |
|---|---|
| 出版社 | 日本経済新聞出版 |
| ページ数 | 252ページ |
| 建築の原点度 | ★★★ |
| 自分を磨くための本 | ★★★★★ |
【第4位】負ける建築
隈研吾氏の建築論を知る
建築学生さんに、読んでほしいおすすめの本ランキング第4位は『負ける建築』です。新国立競技場の設計にも携わり、ここ十数年建築家のトップランナーとして走り続けてきた隈研吾氏。東洋・西洋含め建築の歴史を振り返りながら独自の建築論を語ります。周辺環境から屹立する20世紀型の「勝つ建築」ではなく未来の建築とはもっと色々な外力を受けいれていく「負ける建築」の道をたどるべきだと論じています。建築家とは歴史や社会のあり方など色々なことを考えながら進んで行く仕事なのだと時間させられる一冊です。そして建築家トップランナーが何を考えているのかを知ることもこれからの建築家にとって重要なテーマ。建築学生さんにはかなりおすすめします。 → 隈研吾氏の書籍一覧はこちら
| 著者 | 隈 研吾 |
|---|---|
| 出版社 | 岩波書店 |
| ページ数 | 264ページ |
| 建築の原点度 | ★★ |
| 自分を磨くための本 | ★★★★★ |
【第5位】ニッポン ヨーロッパ人の眼で見た
日本の建築美学をドイツの建築家が語る
建築学生さんに、読んでほしいおすすめの本ランキング第5位は『ニッポン ヨーロッパ人の眼で見た』です。ドイツの著名な建築家が昭和8年に初めて日本を訪れ、その建築の美しさを賛美して書かれた一冊です。「桂離宮は、現代における最大の世界的奇跡」とまで断言しているタウト氏の言葉には「一切が究極の清楚」「機能主義が完全に発揮されている」「その美はまったく精神的性質のものである」など。外から見たニッポンという国はこんなに美しく見えるものなのか、と驚かされる反面「自分は日本を知らなすぎる」と感じると思います。そして先に紹介しました「陰翳礼讃」と共通の建築美学があります。
| 著者 | ブルーノ・タウト |
|---|---|
| 出版社 | 講談社 |
| ページ数 | 208ページ |
| 建築の原点度 | ★★★★ |
| 自分を磨くための本 | ★★★ |
【第6位】都市のイメージ
世界中で絶賛された建築・都市デザインの本
建築学生さんに、読んでほしいおすすめの本ランキング第6位は『都市のイメージ』です。イメージアビリティ=イメージしやすさが建築・都市のデザインにとって重要だという半世紀前においては新たな視点として世界中で絶賛され、建築を学ぶ人は皆読んだ一冊。都市計画という学問のバイブルにもなったほど。リンチの概念は現代の建築・都市計画に対して今でも大きな影響を与えています。特に今では当たり前になっている視覚・心理学・行動学的な視点で都市を演じているいるところはかつてないものであったと言えるでしょう。建築を志す学生さんには必読です!ケビンリンチ氏の著書としては「敷地計画の技法」も有名ですね。
| 著者 | ケヴィン リンチ |
|---|---|
| 出版社 | 岩波書店 |
| ページ数 | 286ページ |
| 建築の原点度 | ★★★★ |
| 自分を磨くための本 | ★★★★ |
【第7位】パターンランゲージ 環境設計の手引き
1980年代後半の建築学生のバイブル
建築学生さんに、読んでほしいおすすめの本ランキング第7位は『パターンランゲージ 環境設計の手引き』です。建築・都市計画をこなう上でのアプローチを「パターン」にして記述した記述し、それらを細かく関連づけてカタログした本。この一冊も当時(1980年代後半〜)の建築学生たちのバイブルとなった一冊。253のパタンと800余の挿図と、膨大なプロセスが記述されていて有機的環境設計の集大成とも言えます。今活躍しているベテラン建築家たちの多くがこの本を手に設計作業をしてきたとも言えます。実はこの本は現代IT実務者の必読の一冊にもなっているのです。
| 著者 | クリストファー・アレグザンダー |
|---|---|
| 出版社 | 鹿島出版会 |
| ページ数 | 656ページ |
| 建築の原点度 | ★★★★ |
| 自分を磨くための本 | ★★★★★ |
【第8位】建築家の講義 ミース・ファン・デル・ローエ
三大建築家ミースに師事した高山正實氏執筆
建築学生さんに、読んでほしいおすすめの本ランキング第8位は『建築家の講義 ミース・ファン・デル・ローエ』です。残る三冊は世界の三大建築家を紹介していきます。まずはミース・ファン・デル・ローエ。建築を学んでいる人であれば真っ先に「ファーンズワース邸」が浮かんでくると思います。そしてこの本はなんとミースに直接師事した日本人、高山正實氏が執筆しています。ミース氏の生涯を辿りながらその姿勢と手法を考察しています。その中の本文紹介します。 「。。。建築は形の遊びではない、ということを学びました。建築と文明の密接な関係を理解するようになりました。建築はその文明を支え推進する力から生まれ出てきたものでなければならない。(中略)最善であれば、その時代の根底にある構造の表現となり得る。。。」 → 建築家の講義シリーズはこちら
| 著者 | |
|---|---|
| 出版社 | 丸善 |
| ページ数 | 128ページ |
| 建築の原点度 | ★★★★ |
| 自分を磨くための本 | ★★★★ |
【第9位】建築をめざして (SD選書21)
三大建築家ル・コルビジェの名書
建築学生さんに、読んでほしいおすすめの本ランキング第9位は『建築をめざして (SD選書21)』です。そしてル・コルビジェ。建築の教科書にも出てくるので読んでいなくてもご存知の方は多いでしょう。都市計画の設計理念を世界に示した「輝く都市」と共にル・コルビジェの最も有名で語り継がれている一冊。授業で「近代建築の5原則」は出てきたかもしれません。かの有名な「住宅は住むための機械だ」が書かれているこの本は歴史的な建築と現代建築を比較考察しながら現代建築を批判しあるべき建築の姿を考察しています。なんといってもコルビジェ氏の優れていたところ(=世界中に認めらたところ)は提言にプランをつけている点です。 100年前、世界の建築家が何を考えていたか。そして今の建築にどう影響しているいるのか。という視点で読んでほしい一冊です。→ ル・コルビジェの書籍一覧はこちら
| 著者 | ル・コルビュジェ |
|---|---|
| 出版社 | 鹿島出版会 |
| ページ数 | 216ページ |
| 建築の原点度 | ★★★★★ |
| 自分を磨くための本 | ★★★★ |
【第10位】フランク・ロイド・ライトの日本
三大建築家ライトを谷川正己氏が記す
建築学生さんに、読んでほしいおすすめの本ランキング第10位は『フランク・ロイド・ライトの日本』です。最後にフランク・ロイド・ライト。ライトの研究では日本で第一人者である谷川正己氏の著書。ライトの解説本は数多くありますが、ライトが浮世絵のコレクターでありその収集のプロセスや旧帝国ホテル建築の経緯などが書かれて日本とライトとの関係という別の角度からライトを考察するのも面白いです。その代表作「落水荘」と葛飾北斎の浮世絵をヒントにしたというようなエピソードも巷によく聞かれますが(本人は日本文化・建築の影響は否定的)先に紹介したブルーノ氏の本とも一緒に読むとさらに楽しく読めます。→ ライトの書籍一覧はこちら
| 著者 | 谷川 正己 |
|---|---|
| 出版社 | 光文社 |
| ページ数 | 223ページ |
| 建築の原点度 | ★★★★ |
| 自分を磨くための本 | ★★★★ |

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.madori-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)