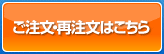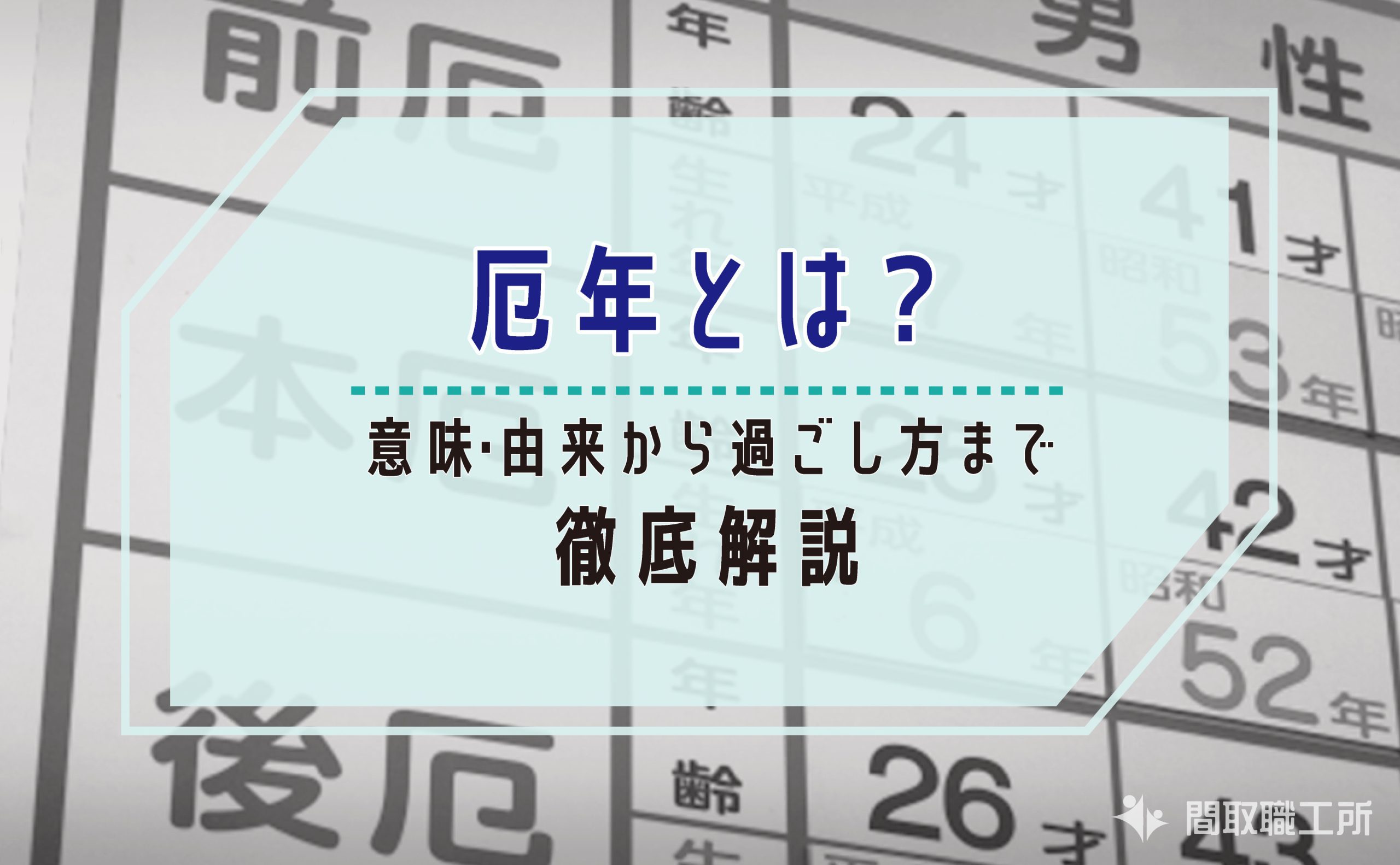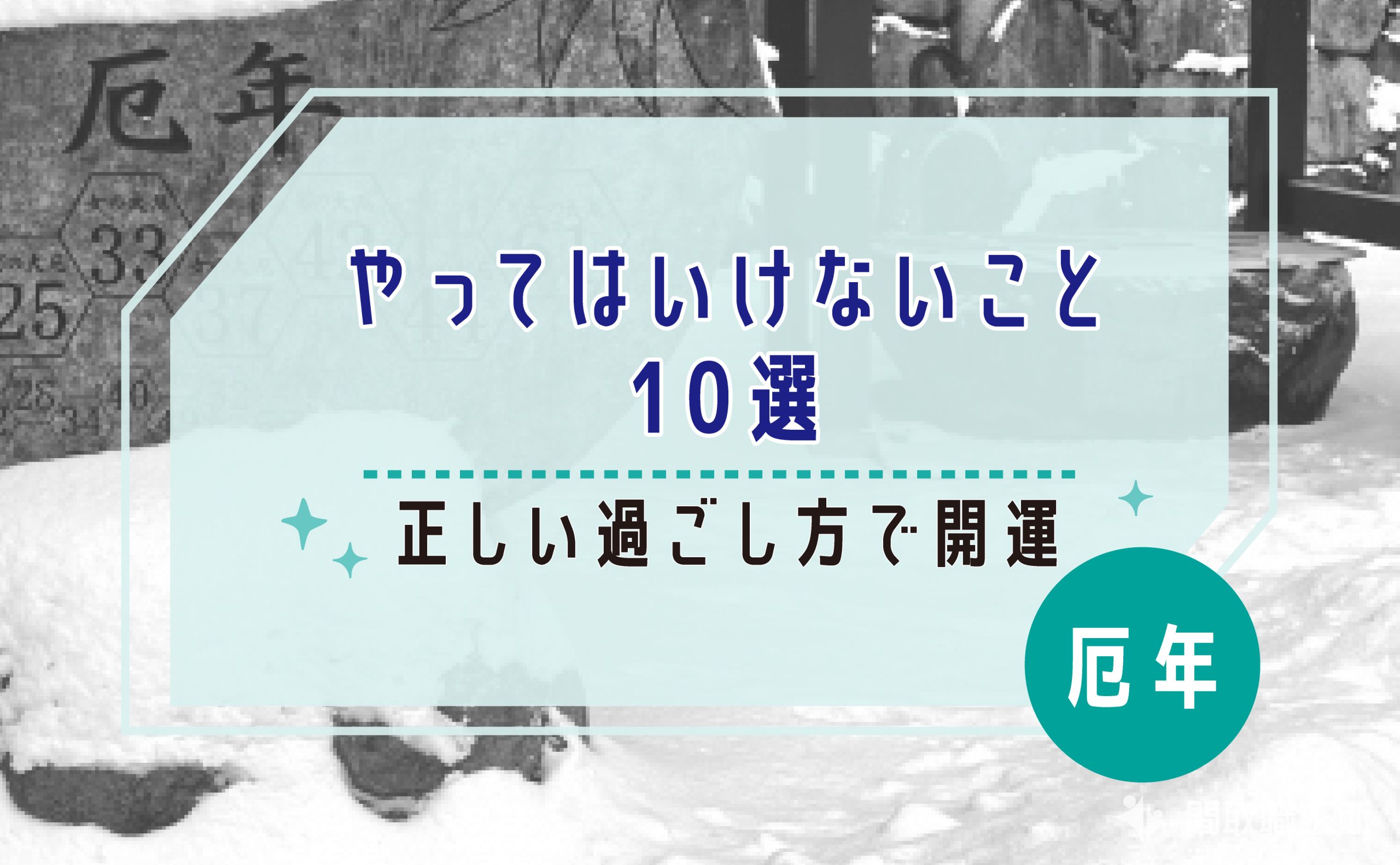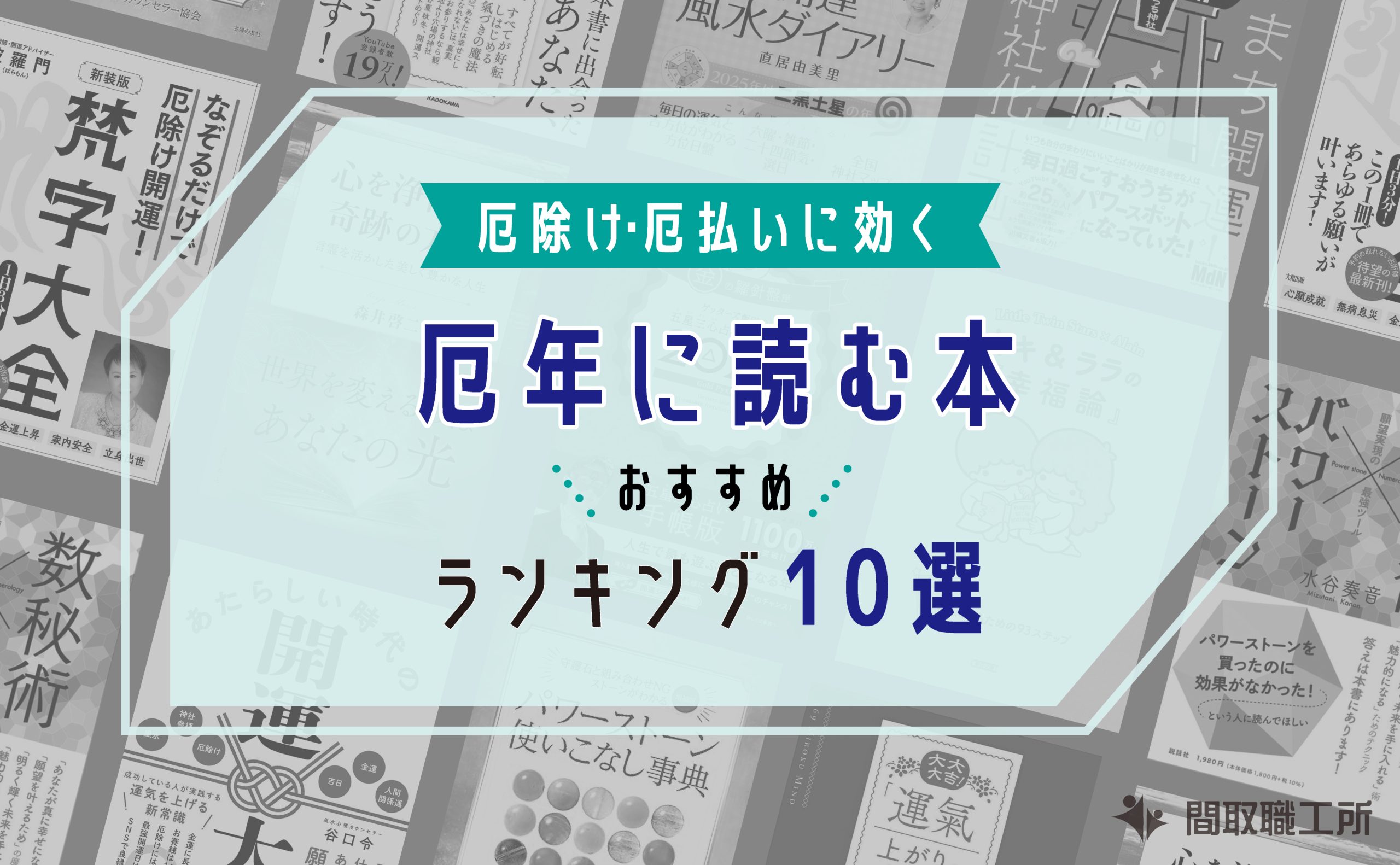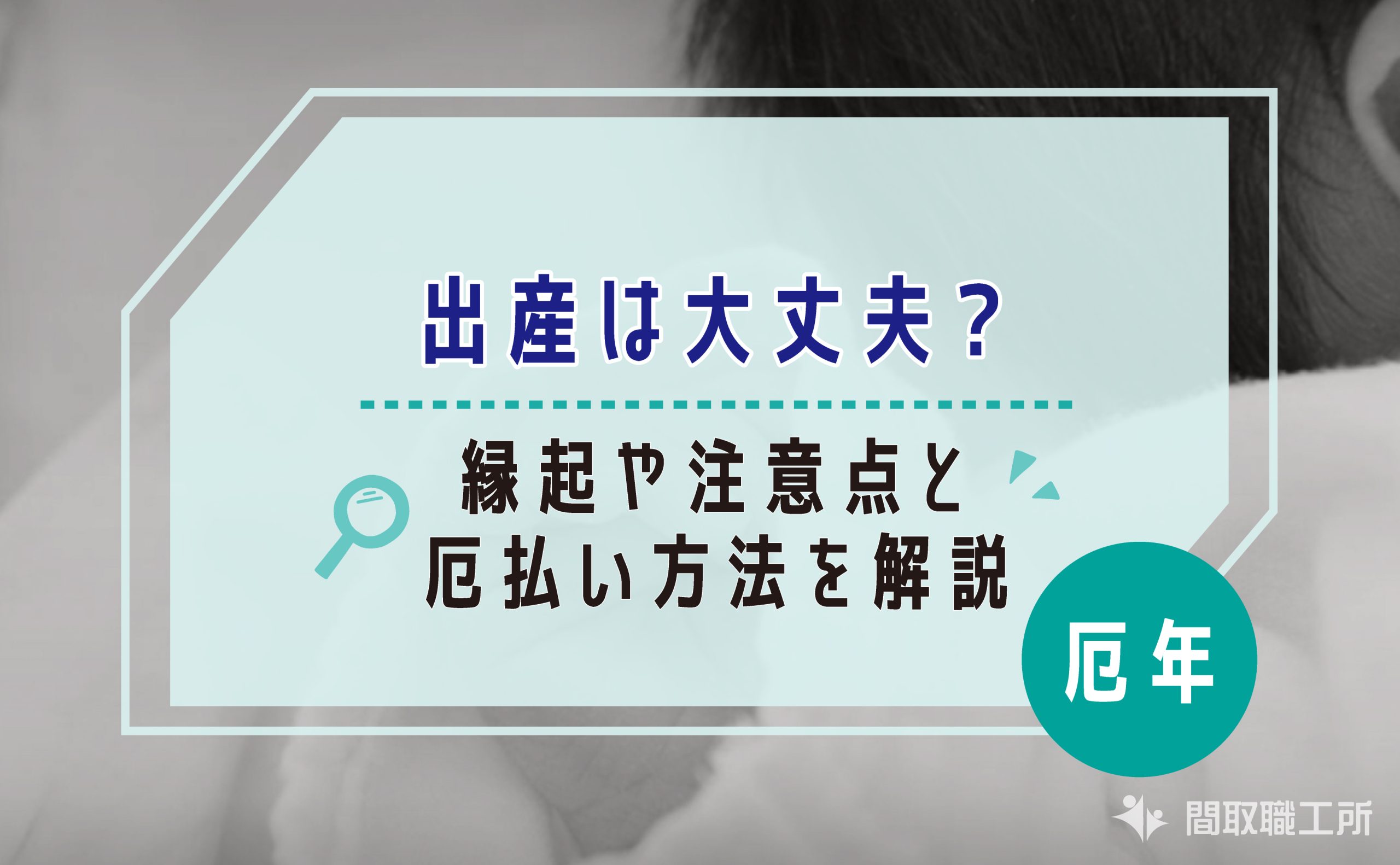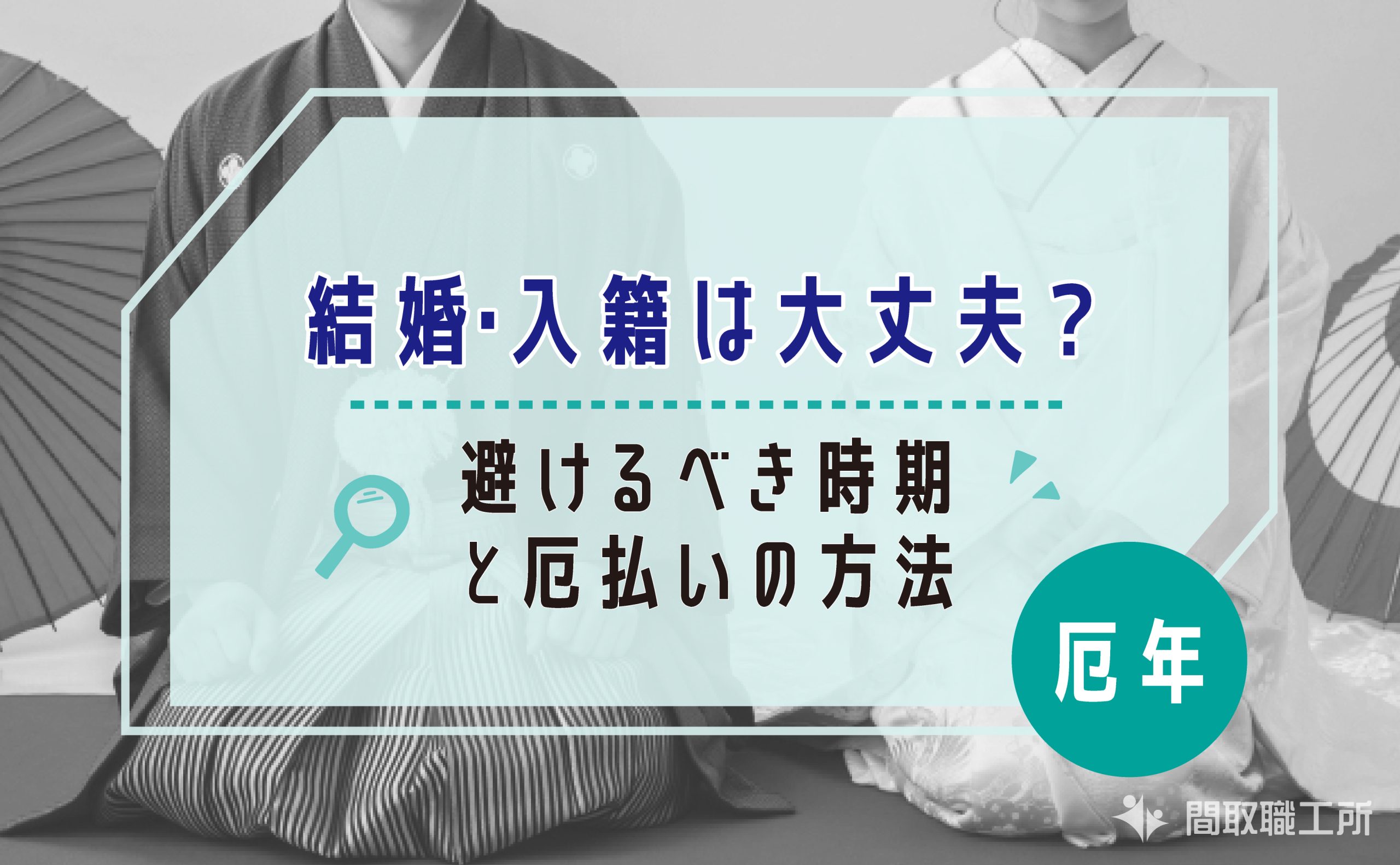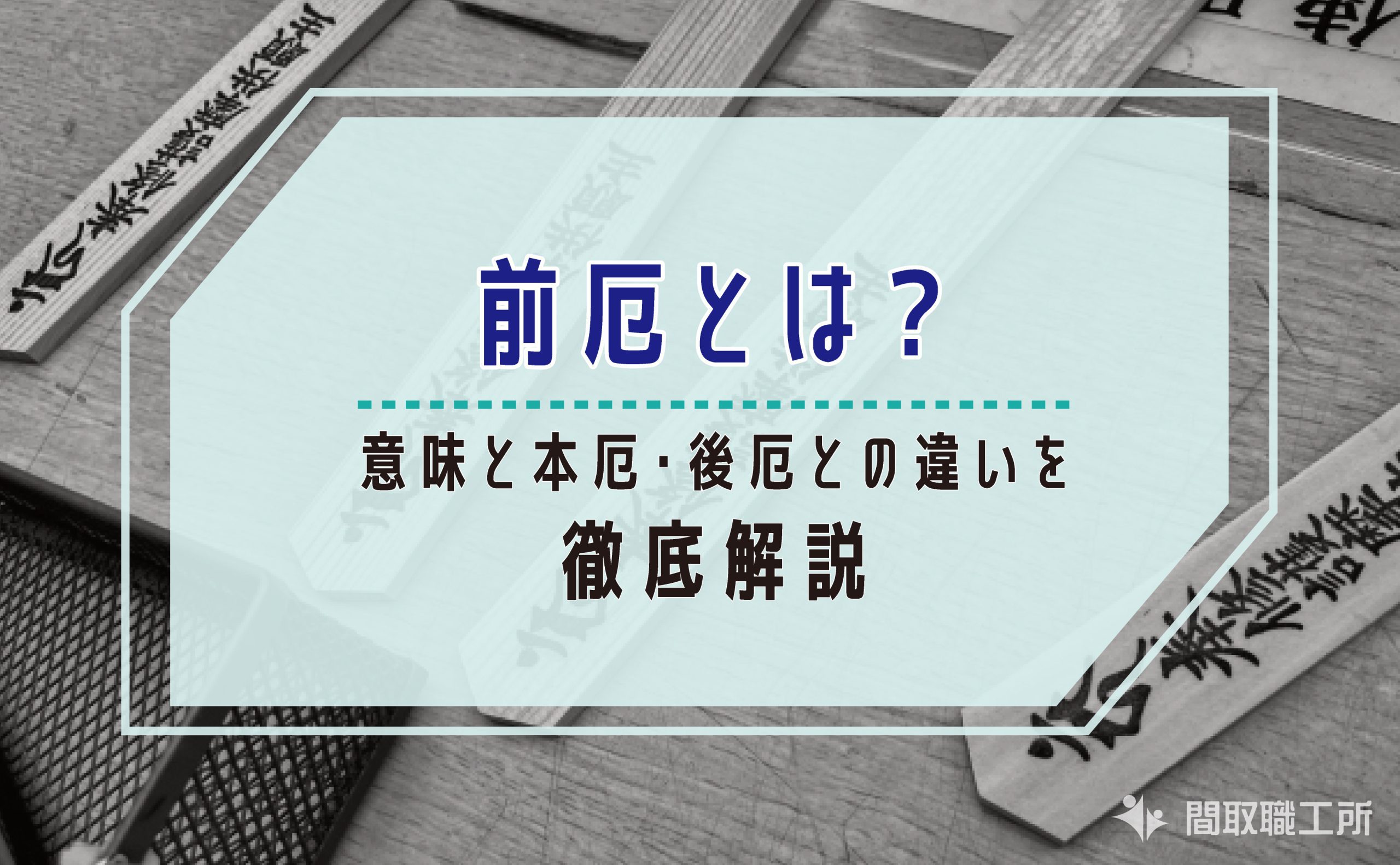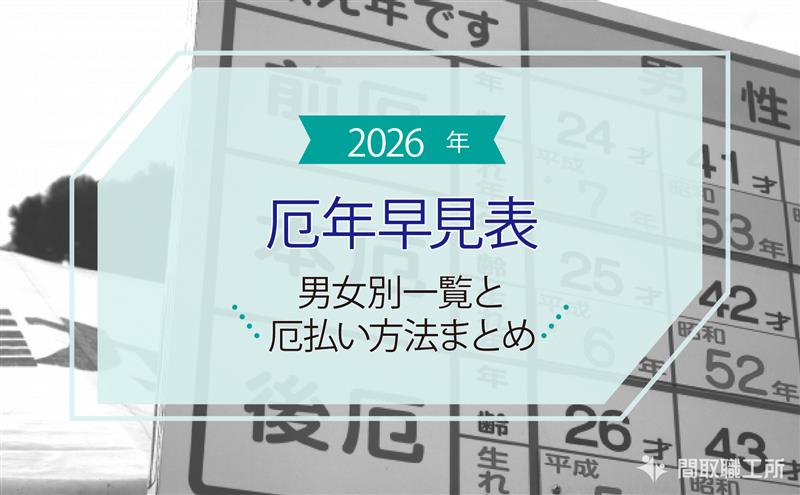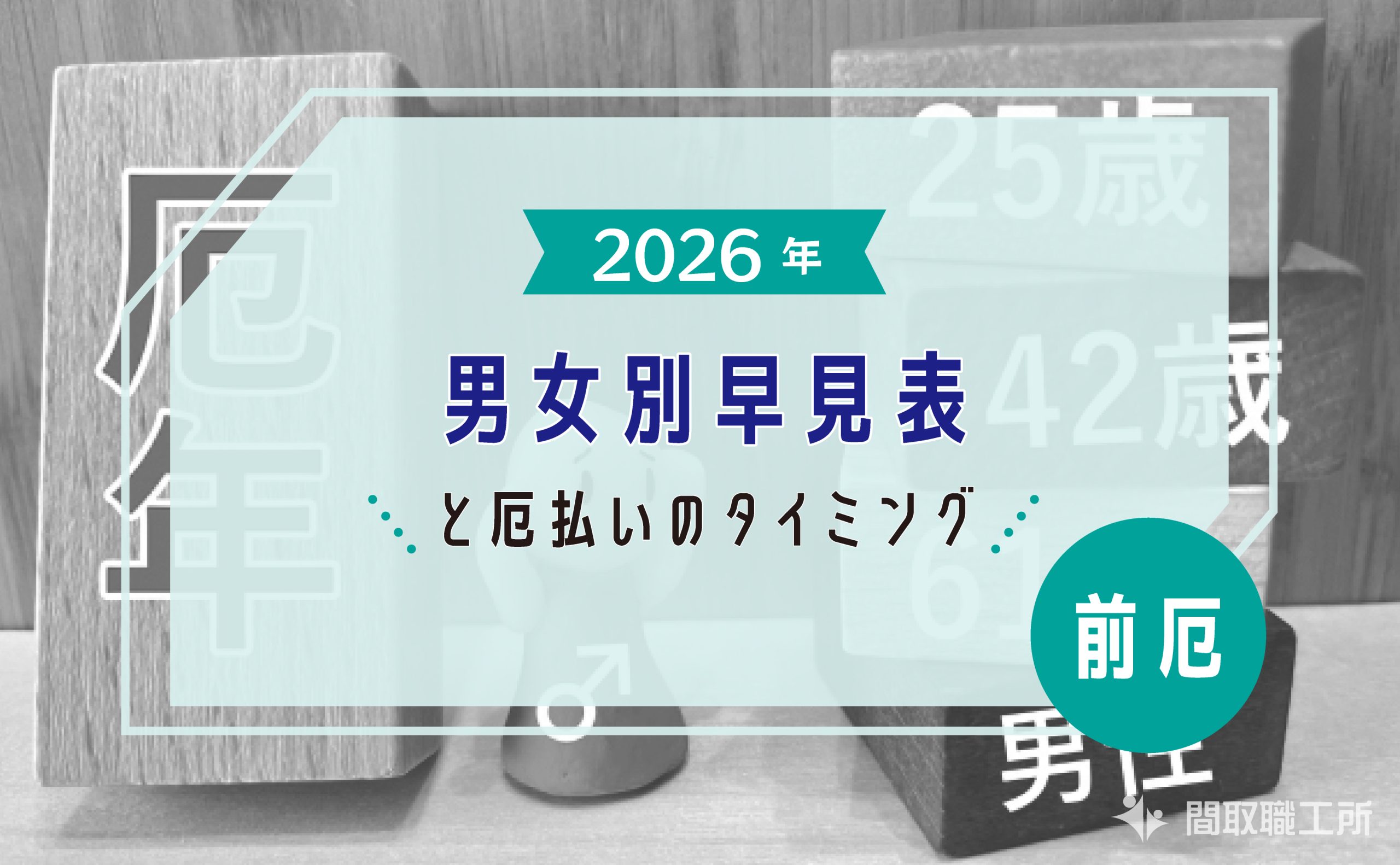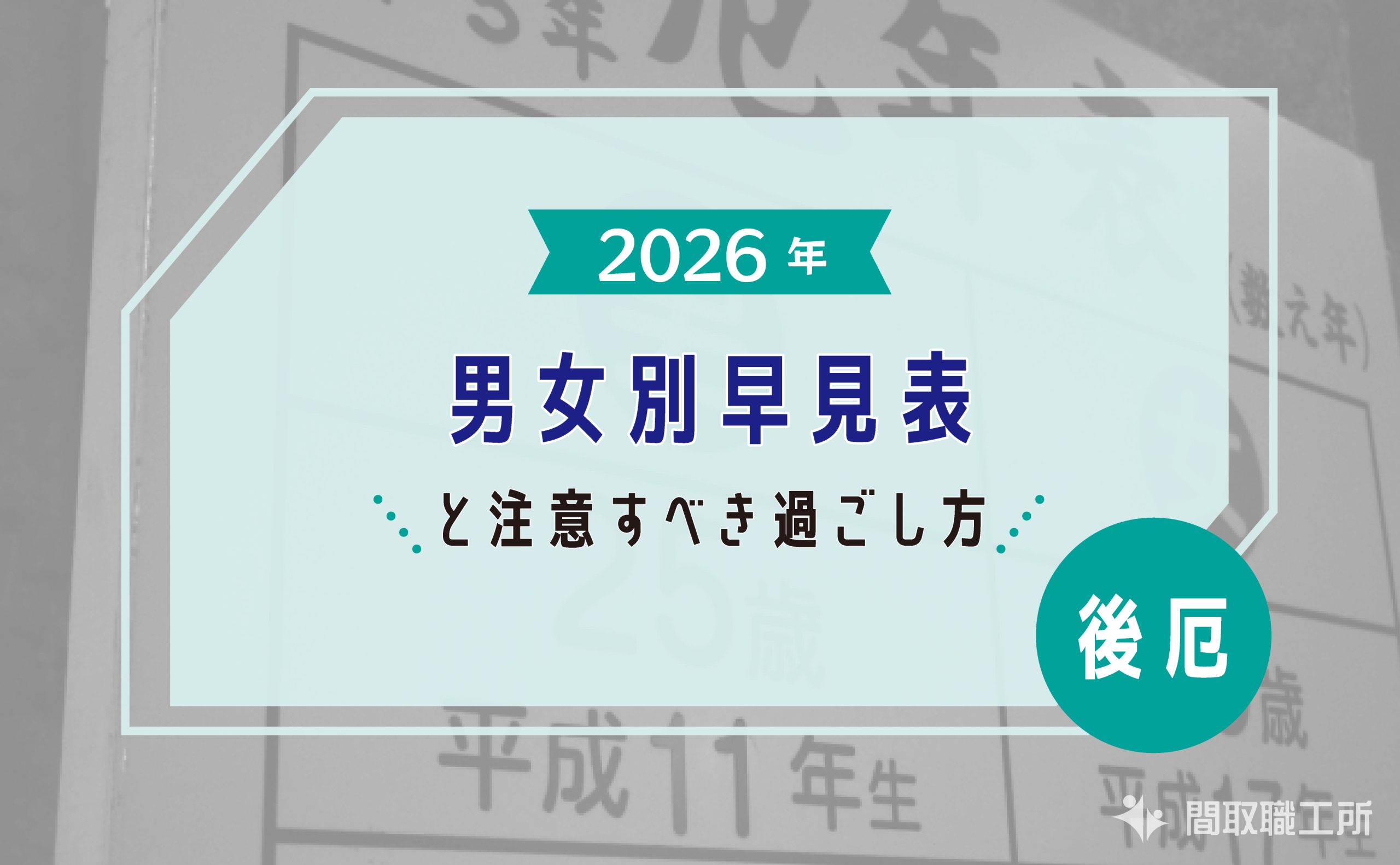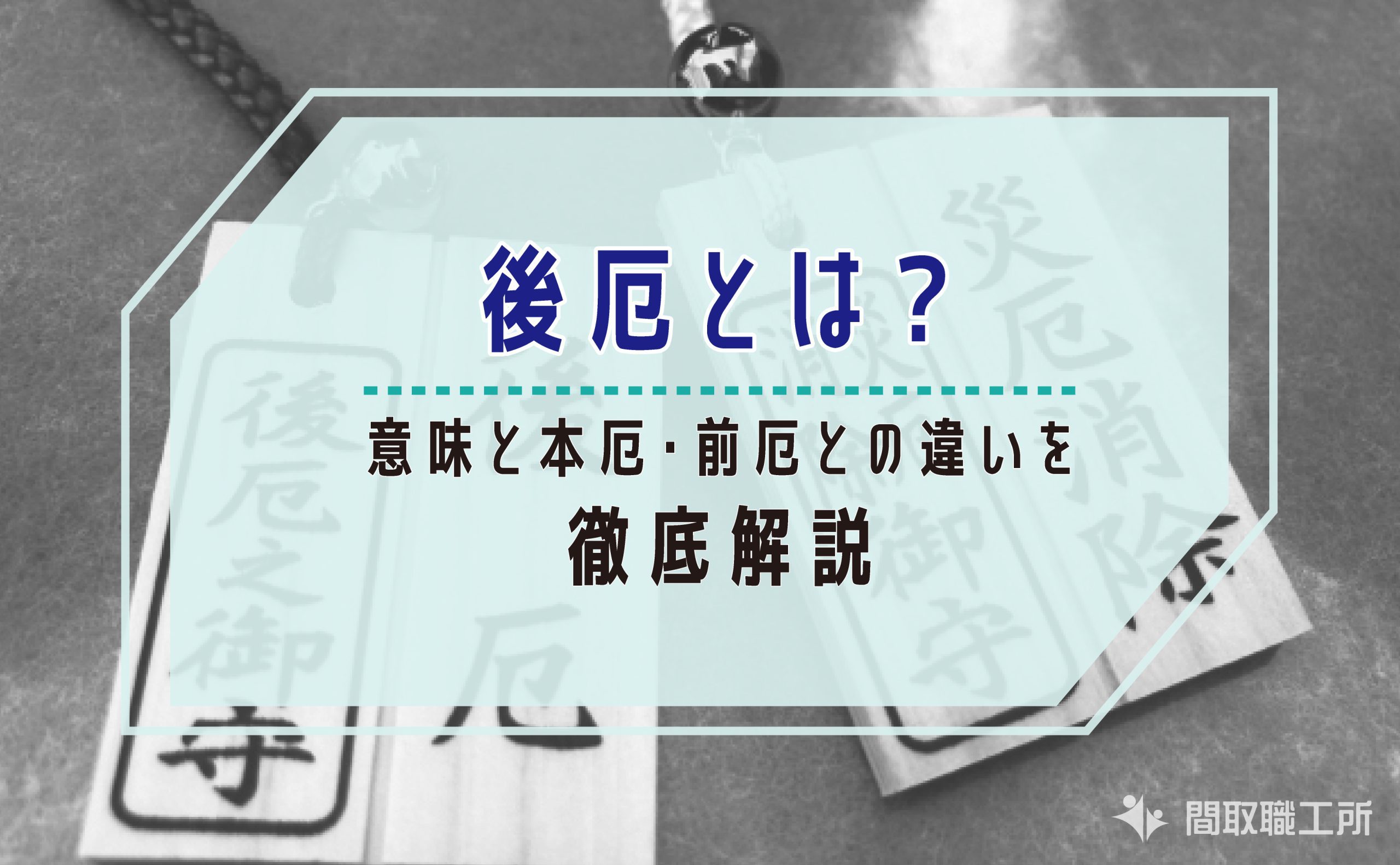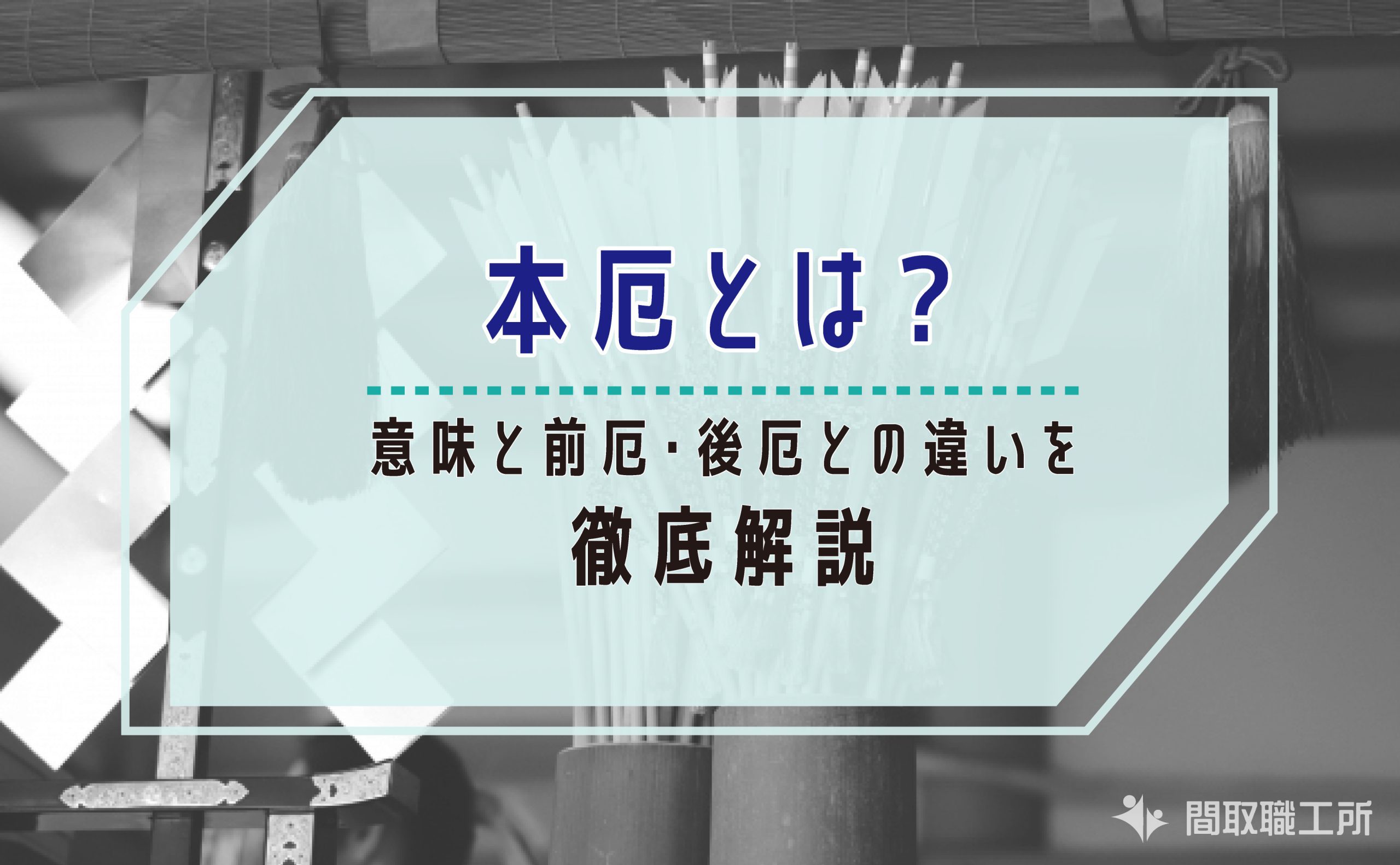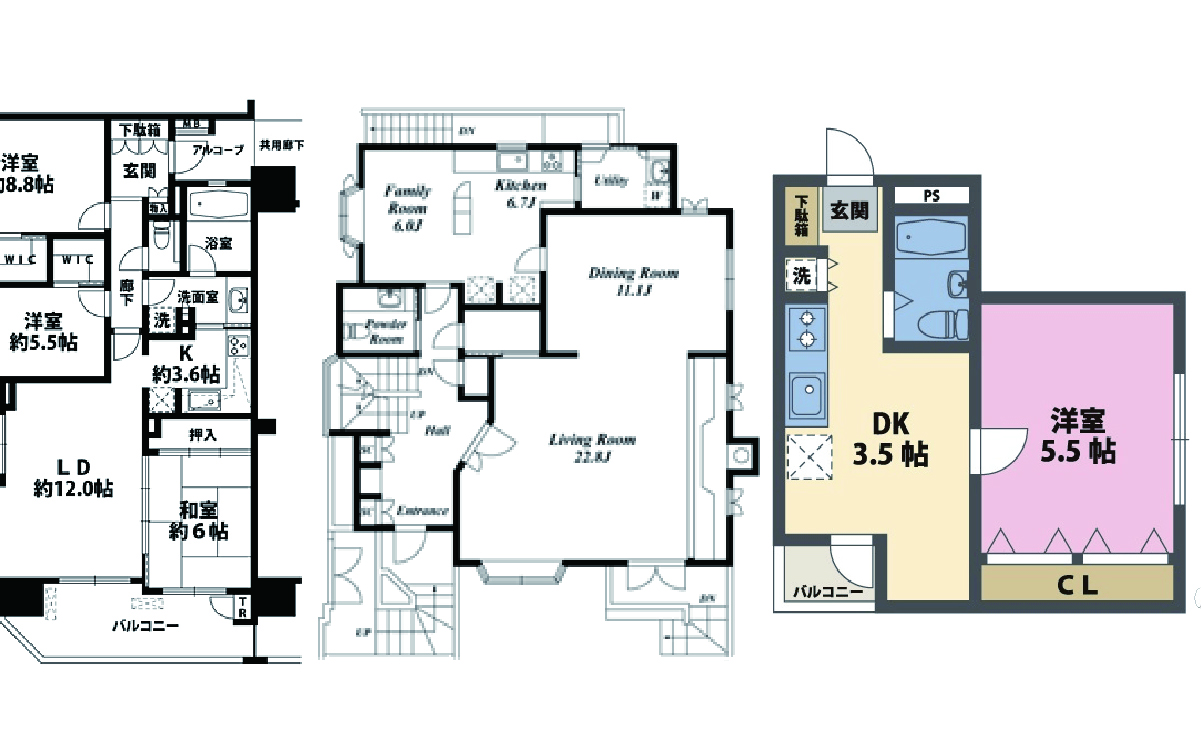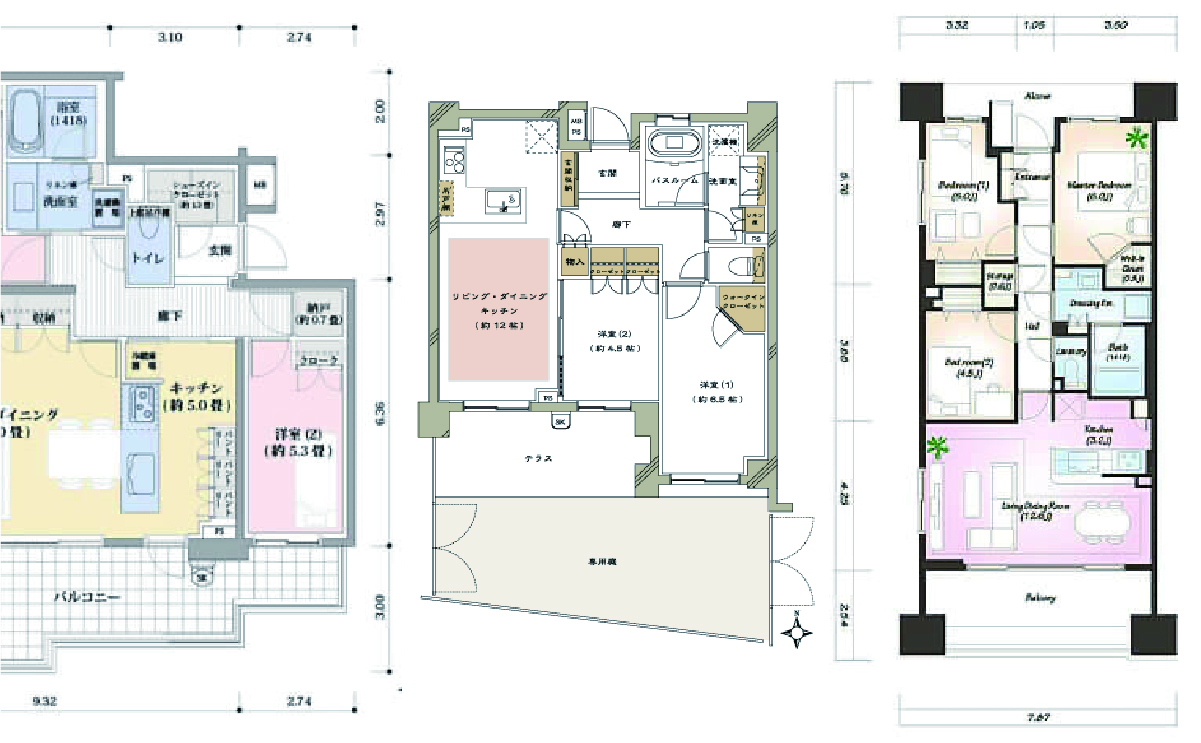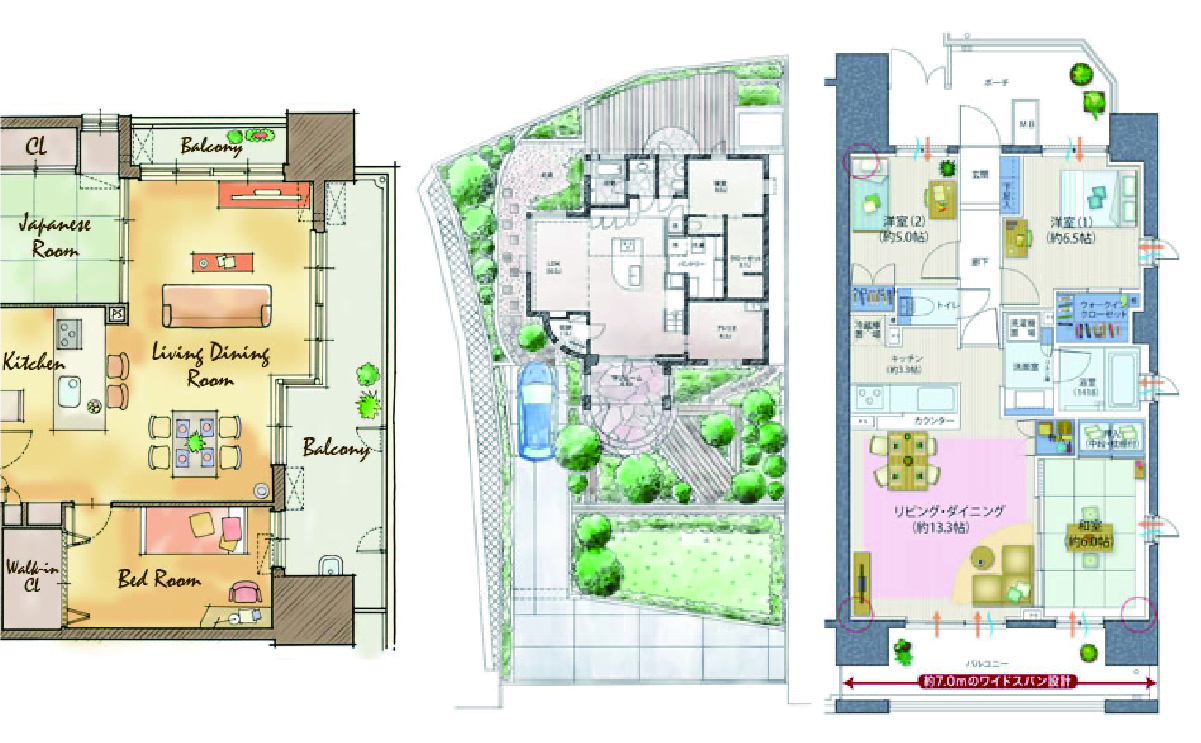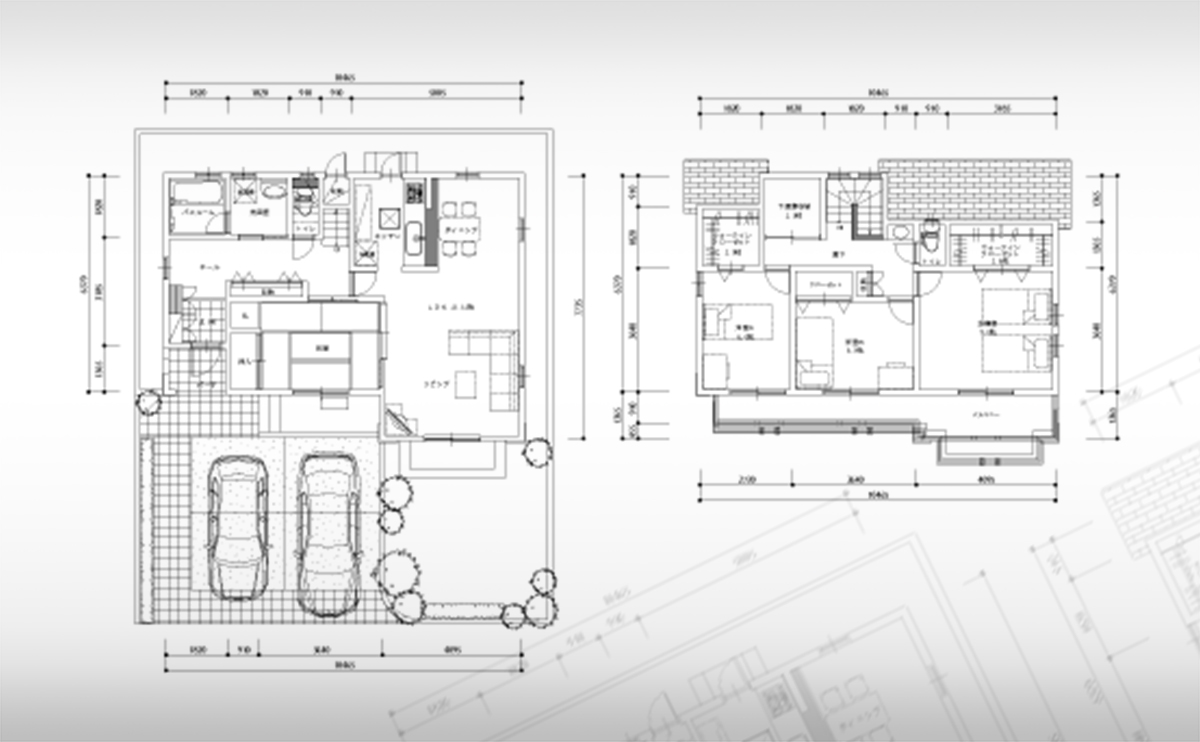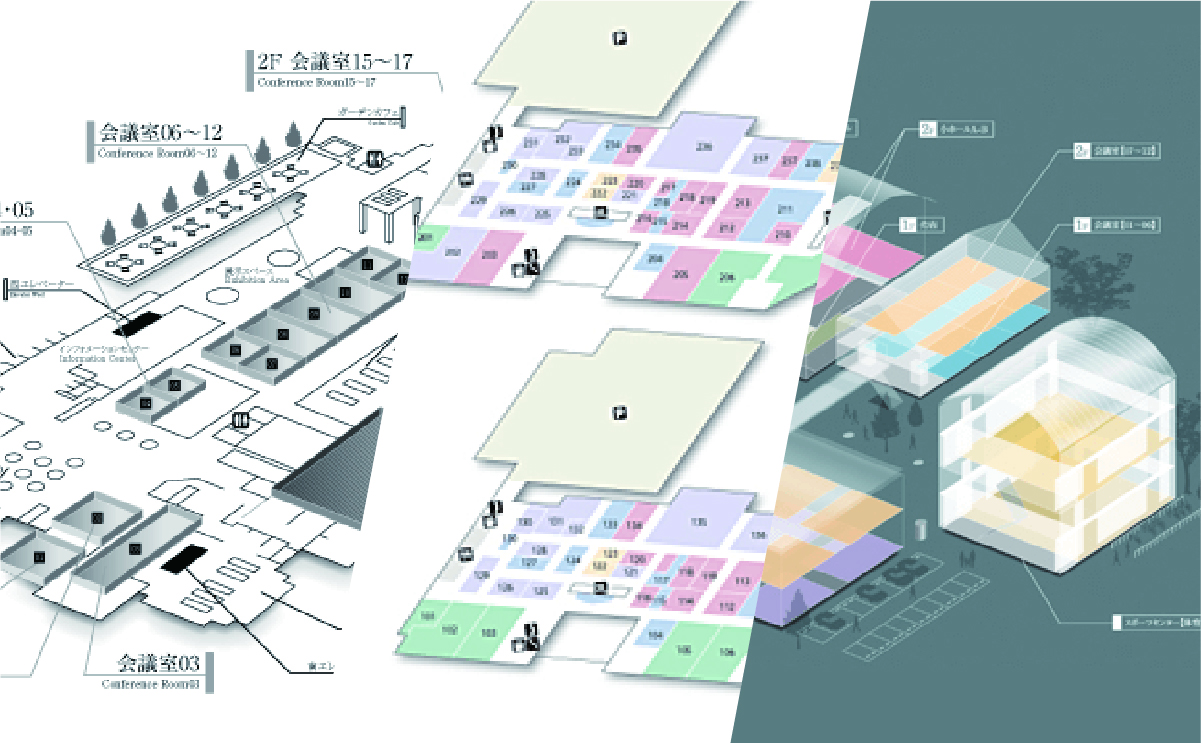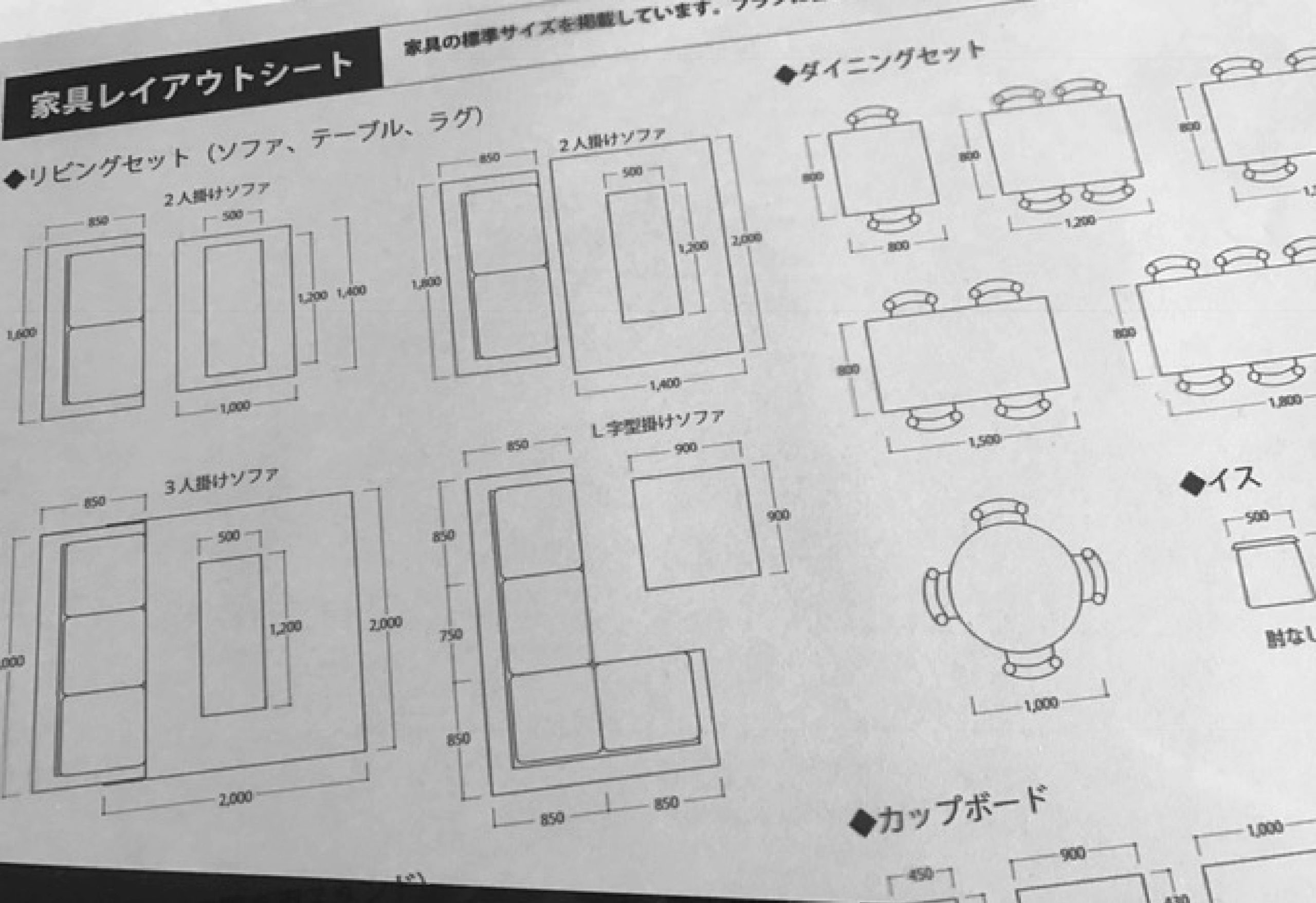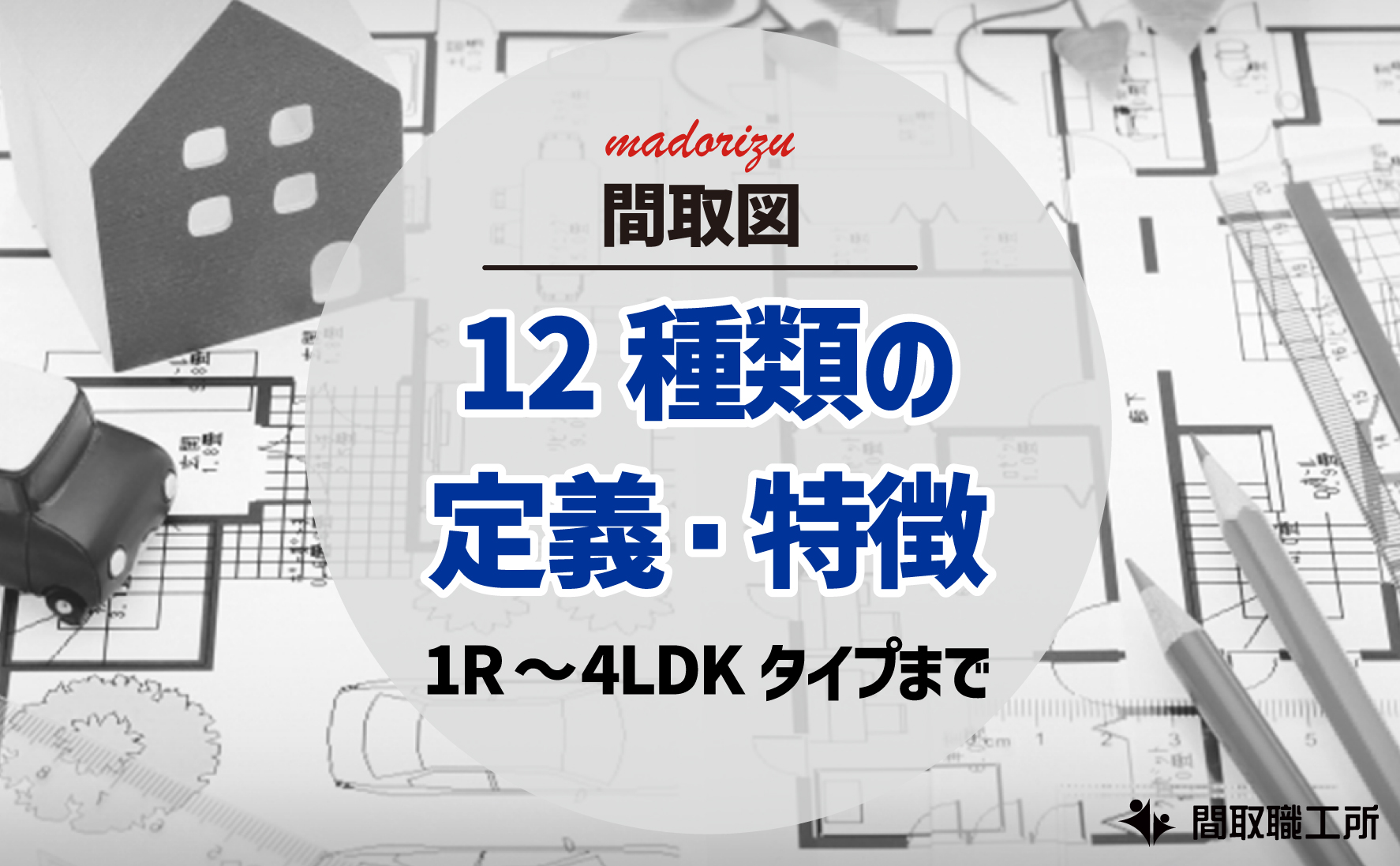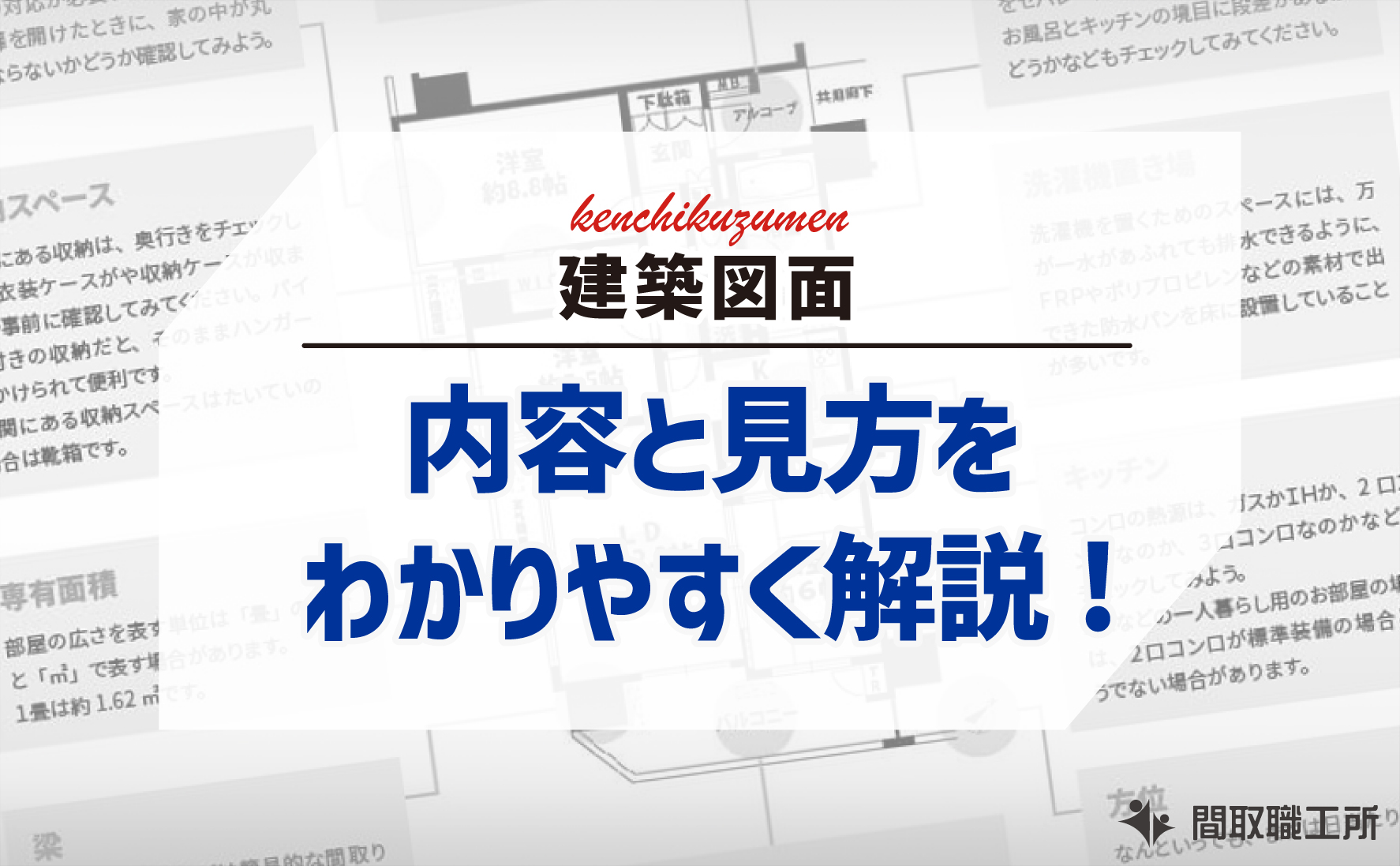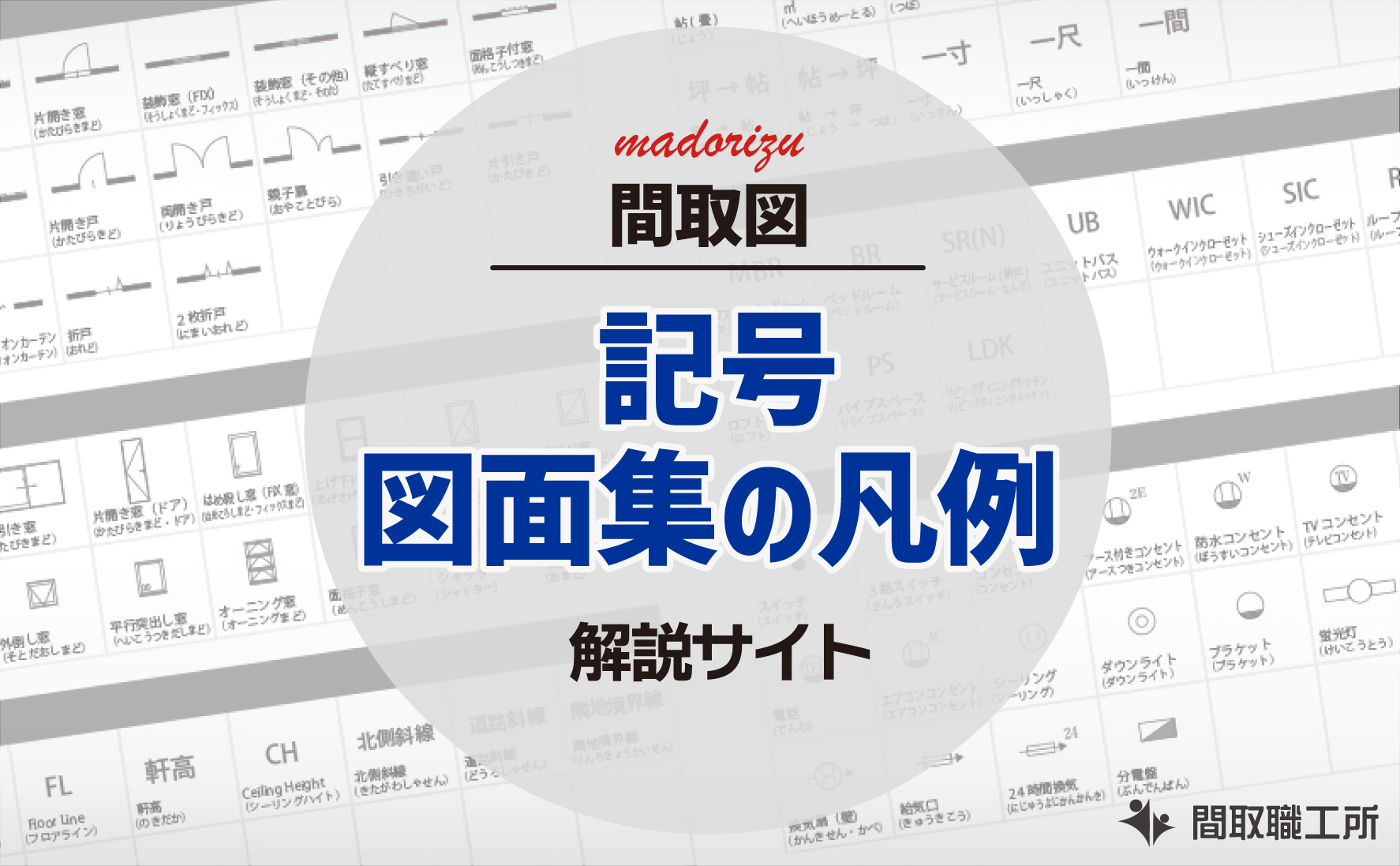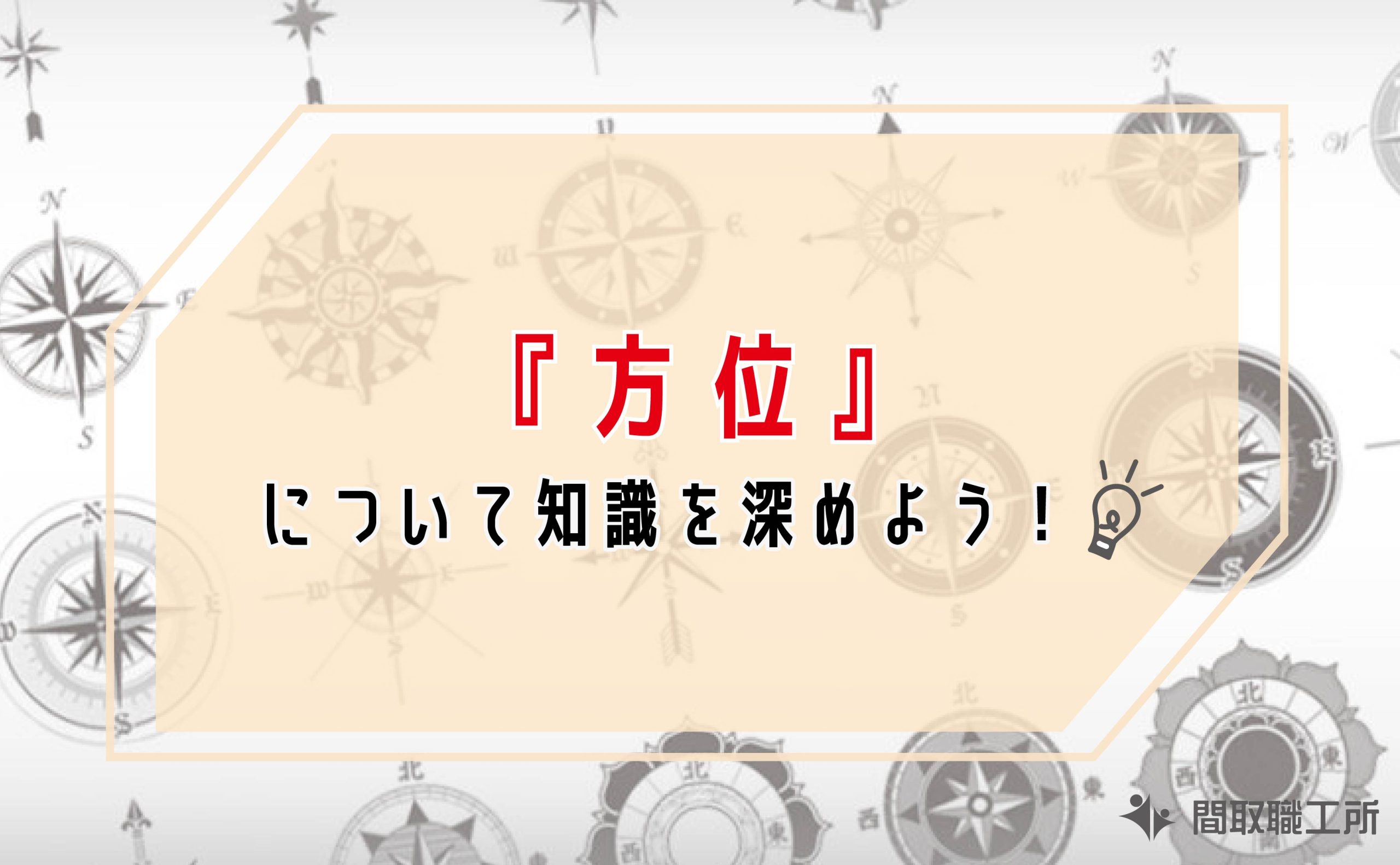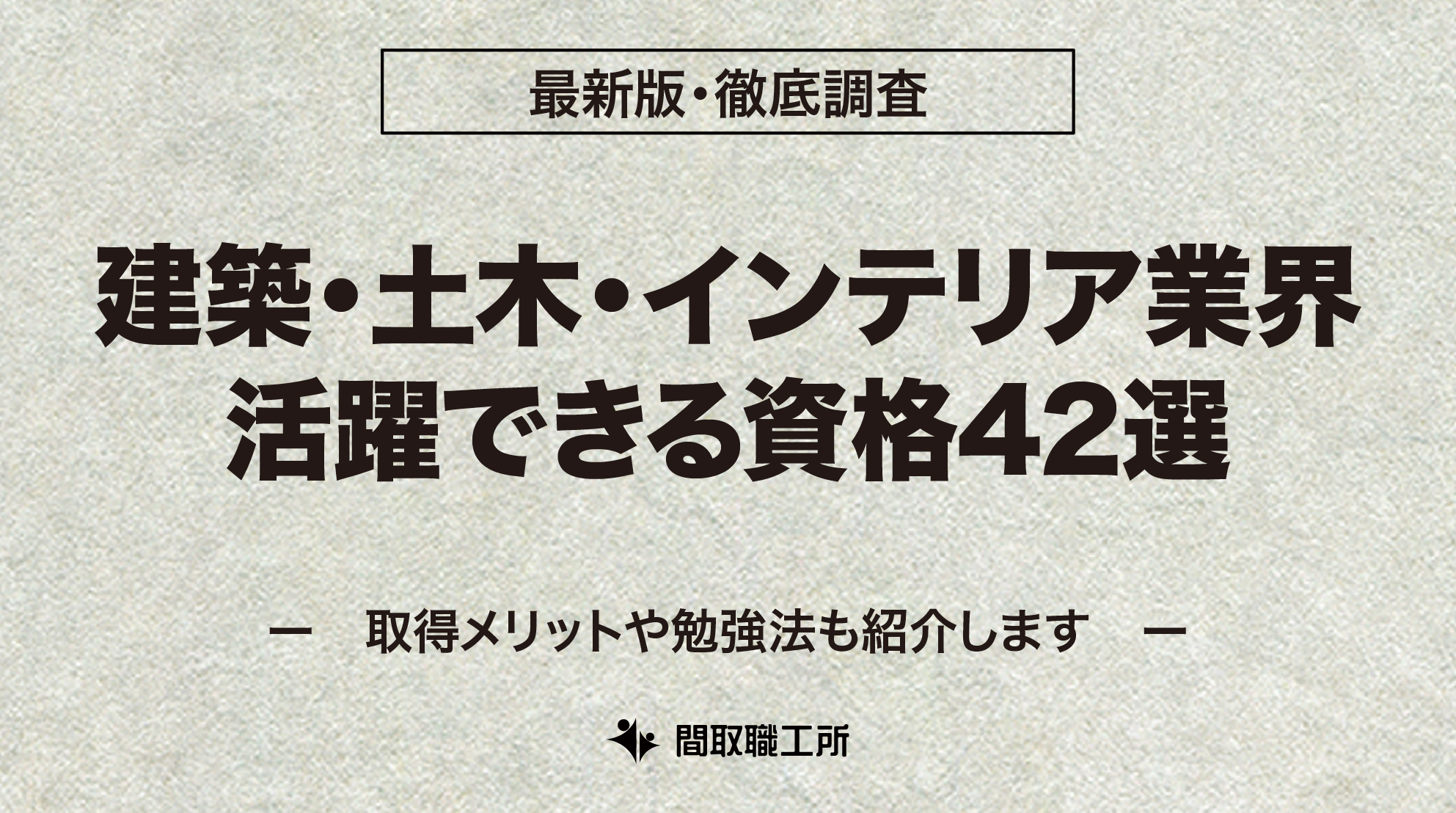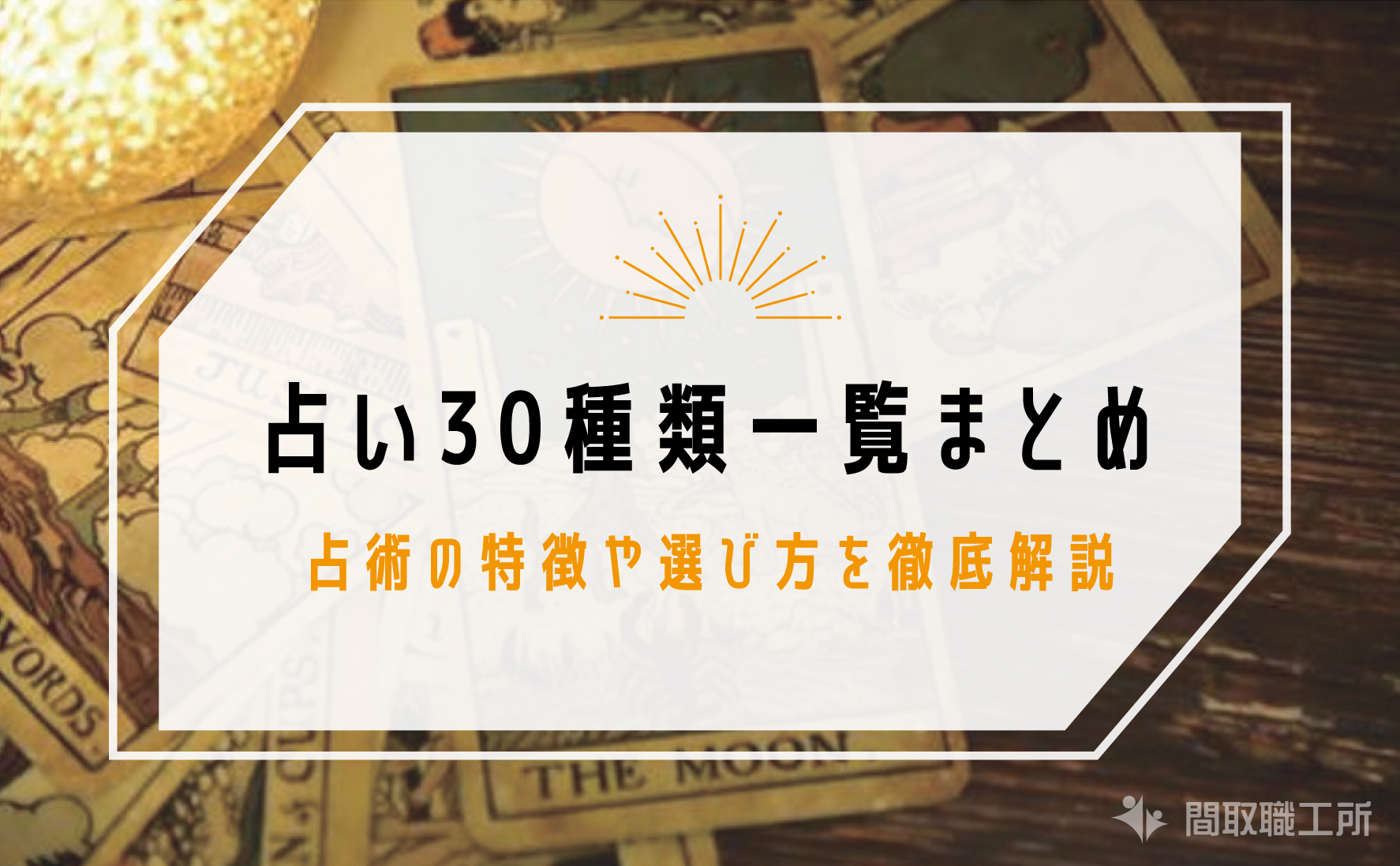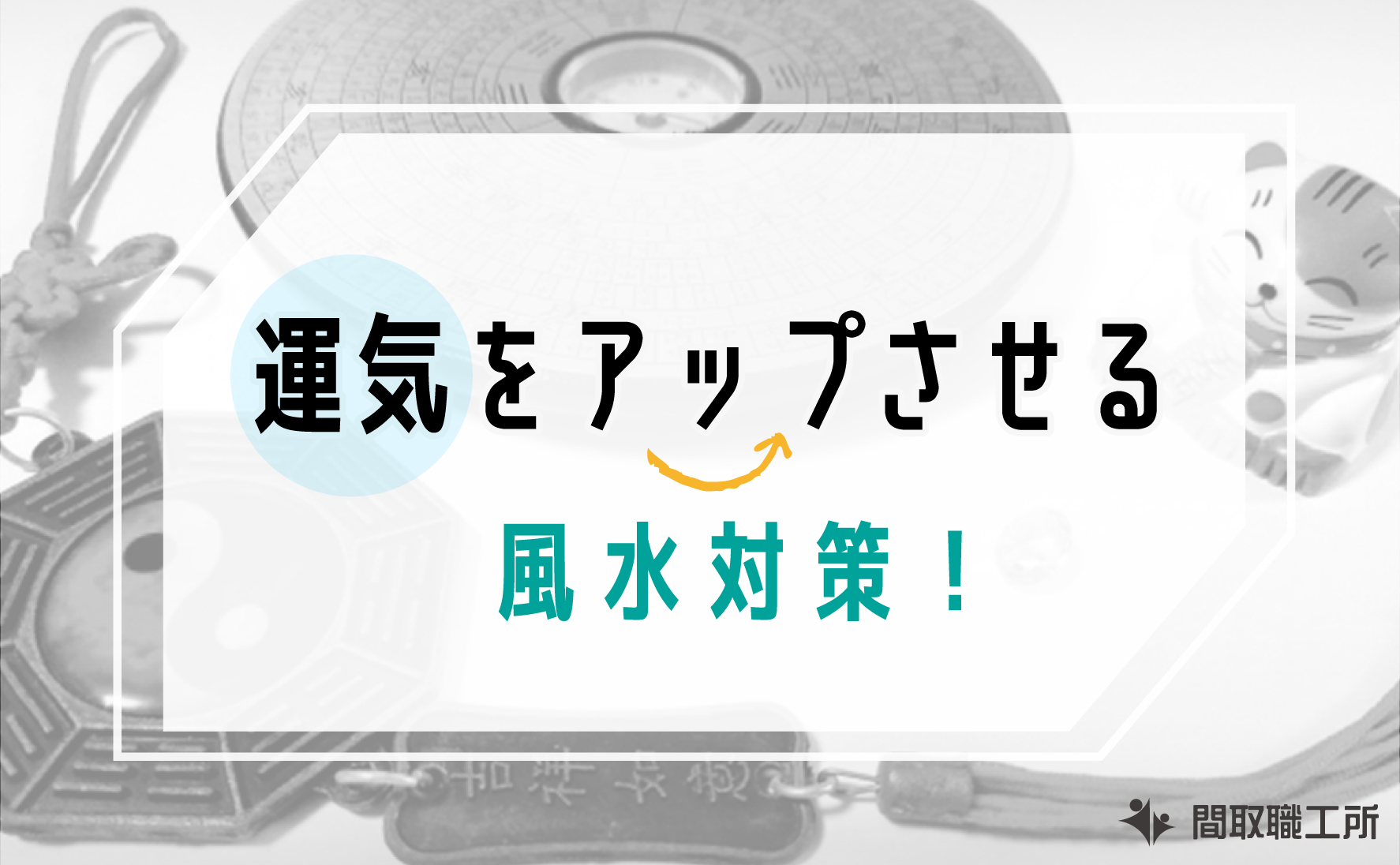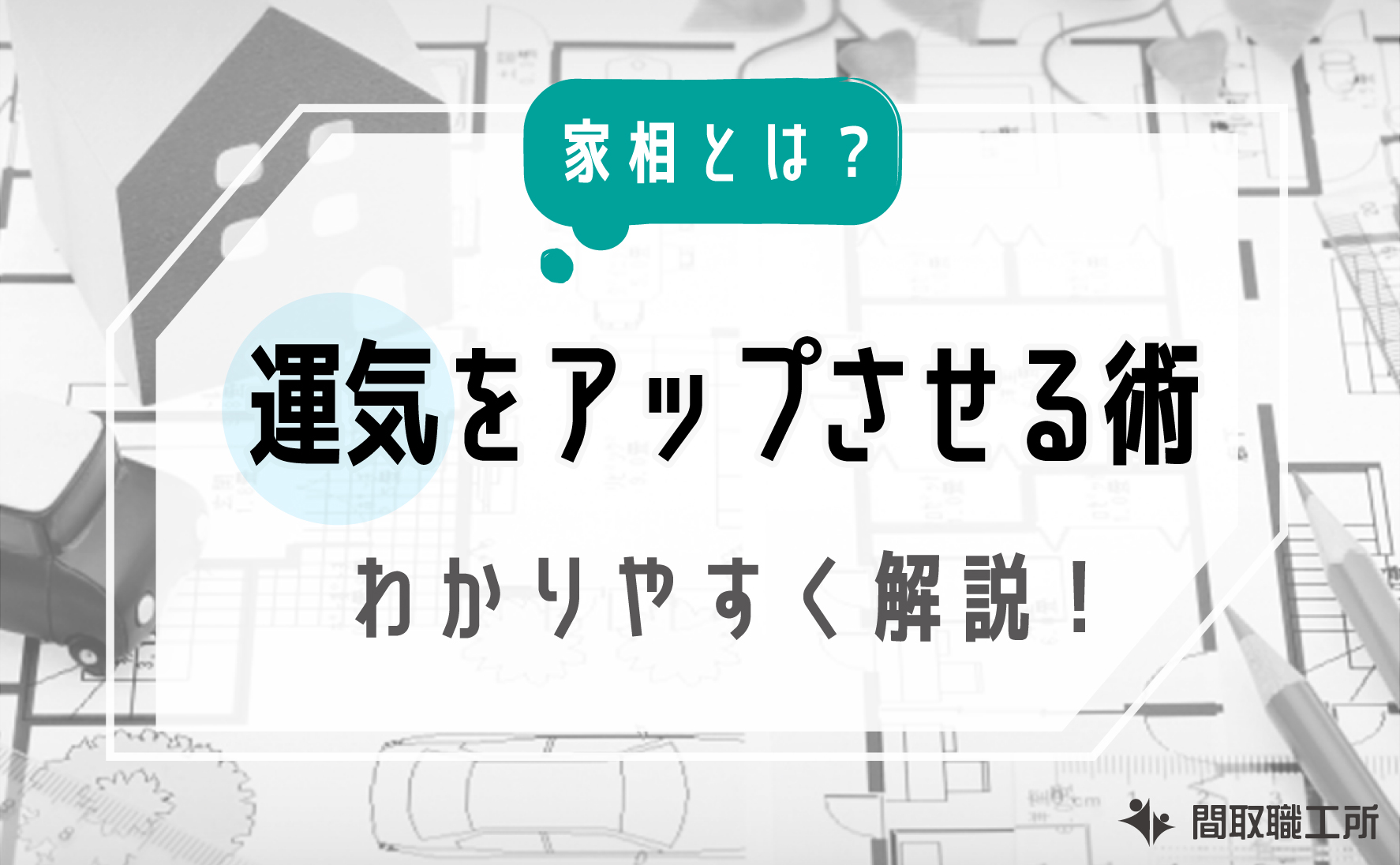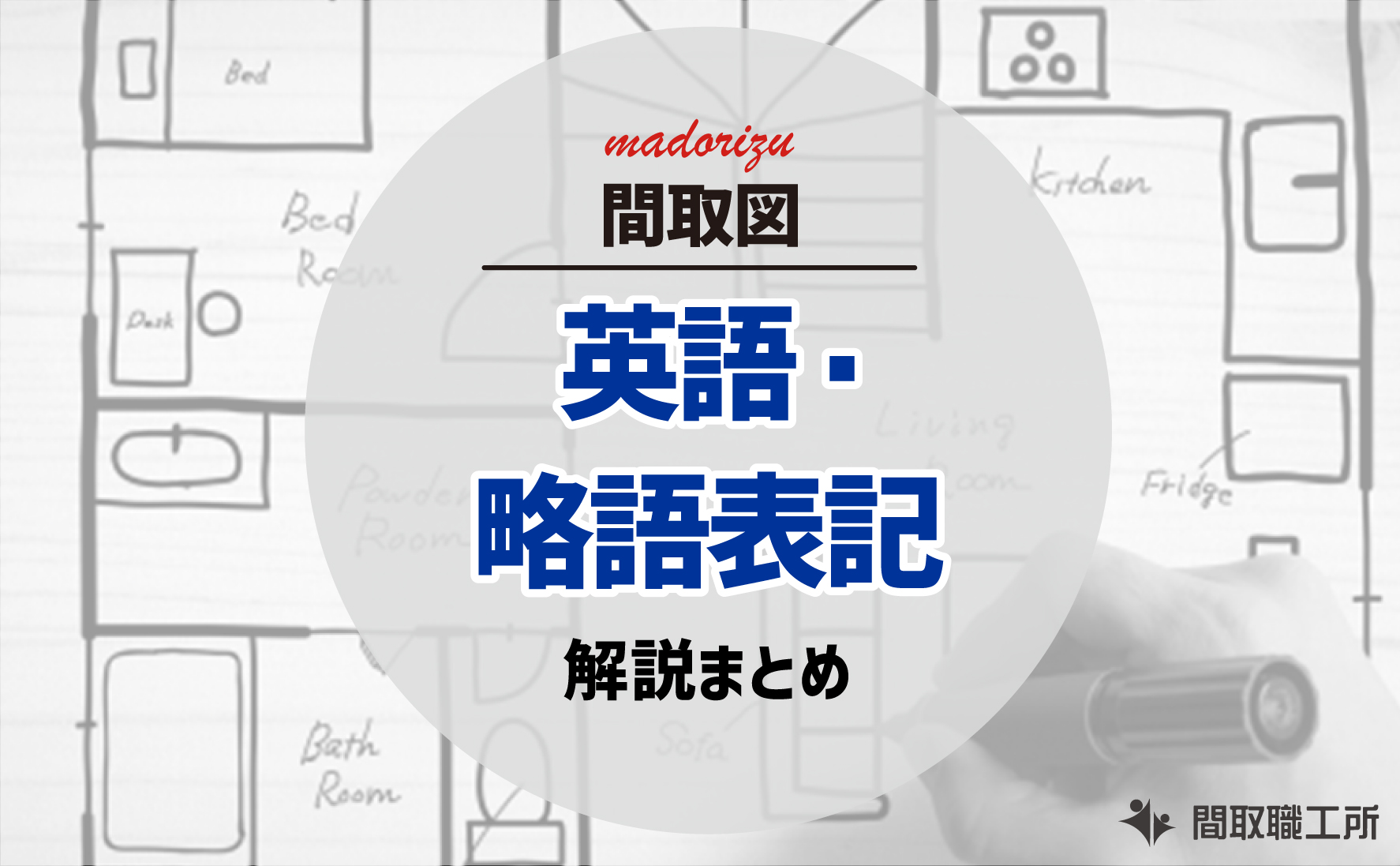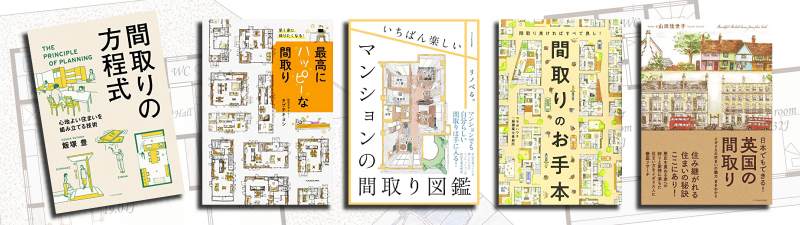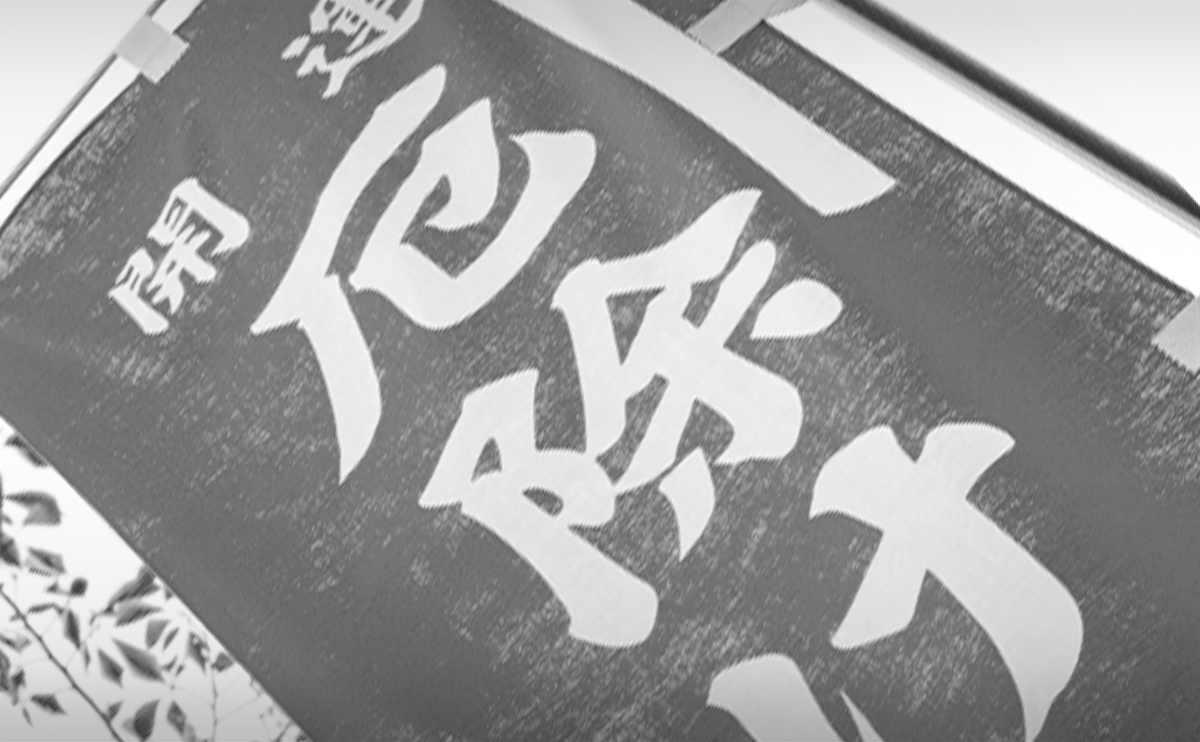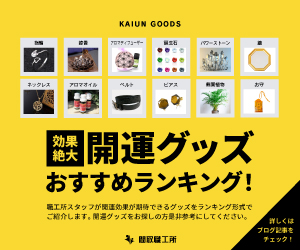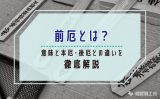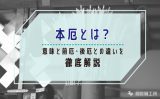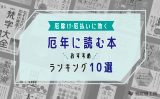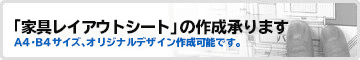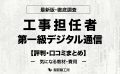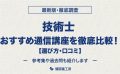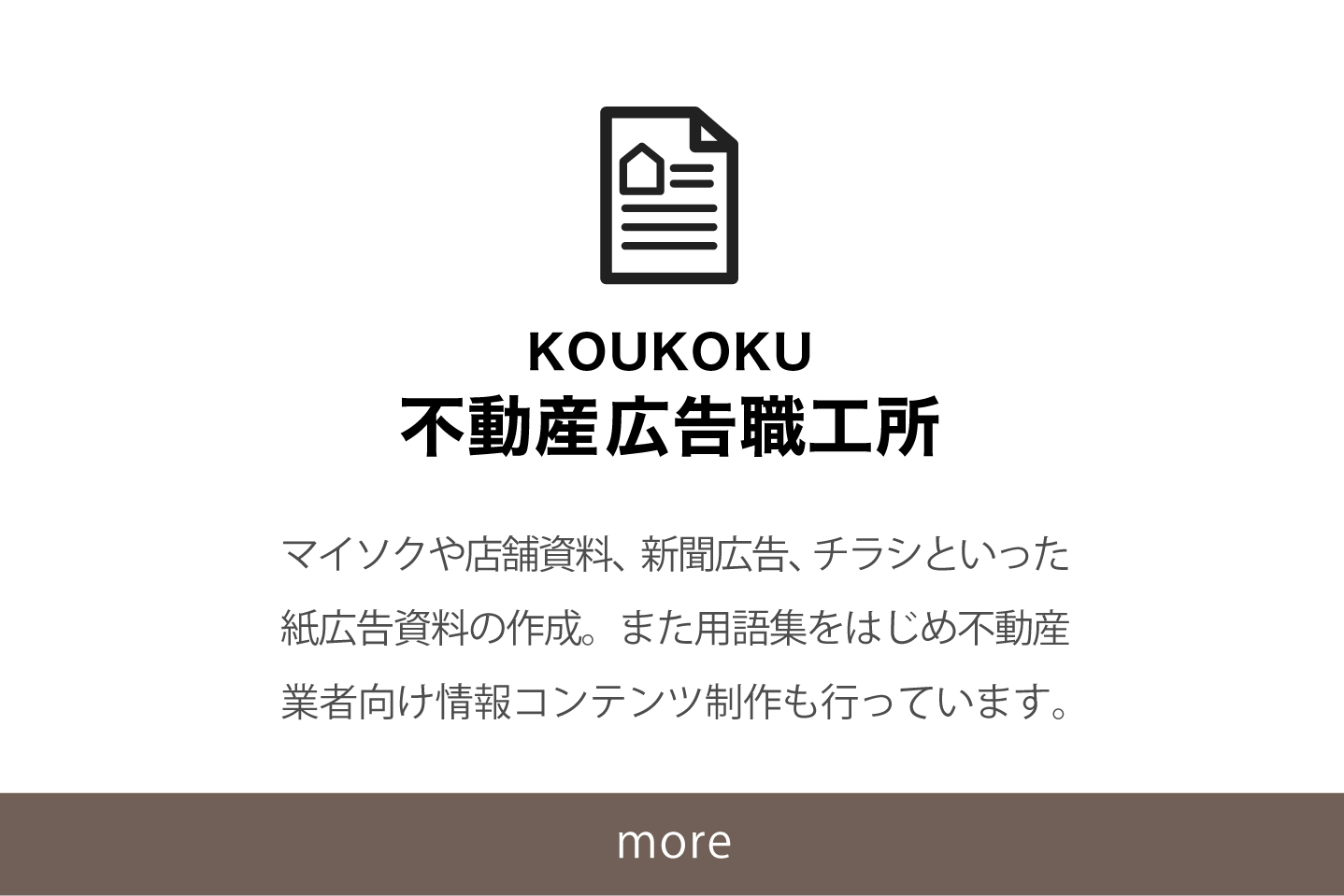厄年と聞くと、「大きな災いが降りかかるのでは?」「新しいことを始めるのは避けるべき?」と、誰もが一度は不安を感じてしまいがちです。しかし、厄年の本当の意味は、単に悪いことばかり起こる年ではありません。私たちが人生において迎える心身の大きな変わり目、つまり社会的立場や健康状態が変化しやすい節目の年齢を指しています。厄年とは、自分自身の状態を見つめ直し、人生の転機を慎重に乗り切るための貴重な注意信号とも言えます。
この記事では、厄年の基本的な知識から、厄年を前向きに乗り越えるための具体的な過ごし方まで徹底的に解説します。厄年を正しく理解し、過度に恐れることなく、人生を豊かにする機会として活用していきましょう。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
厄年とは?
厄年の定義と古来からの役割を説明しましょう。まず、厄年とは、災難や不幸が多く降りかかりやすいとされる特定の年齢を指す、古くから伝わる習俗です。特に、病気や事故、怪我など、心身のコンディションに注意が必要な時期とされています。この習慣が現代まで受け継がれているのは、単なる迷信ではなく、人生の大きな節目の年として、「慎み深く、自己を見つめ直す」ための「身体と心のバランスの指標」として意識されてきたからです。厄年が男女で異なる年齢設定になっているのは、それぞれの性別におけるライフステージの変化を反映しているためです。
厄年の意味と由来
厄年の概念は、日本の陰陽道(おんみょうどう)や神道、仏教といった複数の信仰が融合して形成されたと考えられています。その歴史は古く、平安時代の文献にも既に厄年に関する記述が見られます。厄年で災いが起こりやすいとされる根源的な理由は、体力・気力の低下や社会的立場の変化が大きい年齢に集中しているためです。
- 男性の大厄(数え年42歳):仕事で責任のピークを迎え、無理が蓄積しやすい年齢。
- 女性の大厄(数え年33歳):結婚、出産、育児など、人生の環境が大きく変化し、体調を崩しやすい時期。
厄年は、このように人生の負荷が高まる時期を正確に捉え、その時期を乗り切るために「無理をせず、用心しなさい」という先人たちの知恵が詰まったメッセージなのです。
なぜ厄年があるのか
厄年が存在する最も重要な理由は、私たちに人生の大きな転機への「心の準備」を促すという目的があるからです。特に恐れられてきたのは、男性の大厄(数え年42歳)が「死に(しに)」、女性の大厄(数え年33歳)が「散々(さんざん)」という語呂合わせを持つ点です。これらの年齢は、肉体的にも精神的にも余裕がなくなり始める時期と重なります。
【厄年の役割】
- 体調管理のリマインド: 若い頃のように無理が効かなくなる時期を教え、健康を省みるきっかけを与える。
- 人間関係の見直し: 社会的責任が増す中で、対人関係や生活態度を見直す機会を与える。
- 人生の目標設定: 節目の年として、これまでの人生を振り返り、これからの目標を立てるための時間を与える。
厄年を意識することは、単なる不安ではなく、人生の設計図を点検し、より良い未来のために行動するためのポジティブなきっかけになるのです。厄年の中でも最も注意が必要とされる「本厄」。その意味合いや、前後の年にあたる「前厄」「後厄」との関係性、重要性の違いについて、下記で深く掘り下げて解説しています。
厄年の種類と違い
厄年の期間は、「前厄」「本厄」「後厄」の3年間にわたります。災厄の注意度は、この3年間を通じて徐々に高まり、ピークを経て、そして落ち着いていくという流れがあります。厄払いを行うタイミングや心構えも、この3年間の流れを理解することでより明確になります。
| 厄年の種類 | 期間 | 意味合い |
|---|---|---|
| 前厄 (まえやく) |
1年目 |
厄の兆しが現れ始める準備期間。徐々に慎重な行動を心がける。 |
| 本厄 (ほんやく) |
2年目 |
最も災難が起こりやすいとされる年。最も注意が必要で、厄払いの適期とされる。 |
| 後厄 (あとやく) |
3年目 |
厄の影響が徐々に薄れていく年。油断せず、穏やかに厄が完全に抜けるのを待つ。 |
大切なのは、この3年間で心身の状態を整えることです。
前厄・本厄・後厄の違いを解説
厄年の3年間は、それぞれ異なる役割を持っています。
前厄(まえやく)
厄の「前触れ」を感じ始める時期です。この期間に生活習慣の改善や、厄払いの計画を立てるなど、本格的な本厄への準備を始めることが推奨されます。
本厄(ほんやく)
厄の影響が最大限に高まるとされる年です。この時期は、特に体調の異変や突発的なトラブルに注意を払い、大きな決断や環境の変化は避けるよう心がけるべきです。
後厄(あとやく)
厄の影響が緩やかに収まっていく時期です。まだ厄が完全に抜けたわけではないため、本厄ほどではないにしても、引き続き謙虚な気持ちで過ごすことが大切です。厄払いの「お礼参り」を行う人もいます。
厄をピークとした3年間を、どのようにコントロールするかが重要です。
厄年と年齢の関係(男性・女性)
厄年の年齢は、日本の伝統的な数え年で計算されます。数え年とは、生まれた年を1歳とし、元旦を迎えるごとに1歳加算する数え方です。ご自身の厄年がすぐにわかる、男女別の一般的な厄年年齢と大厄の年齢を確認しましょう。
| 性別 | 前厄(数え年) | 本厄(数え年) | 後厄(数え年) | 大厄(特に注意) |
|---|---|---|---|---|
| 男性 |
24歳 |
25歳 |
26歳 |
25歳、42歳、61歳 |
| 女性 |
18歳 |
19歳 |
20歳 |
19歳、33歳、37歳、61歳 |
2026年の厄年については、すぐに確認できる【2026年 厄年早見表】をご覧ください。【2026年 前厄】【2026年 後厄】の年齢やその影響についてもチェックしておくと安心です。
厄年の過ごし方と注意点
厄年とは、「災いが起こる年」ではなく、むしろ人生の転機に心身のバランスを見直すための大切な期間です。この前向きな心構えこそが、厄年を平穏に乗り切るための第一歩となります。過度に恐れて新しい行動をすべて避けるのではなく、いつも通りの生活をいつも以上に丁寧に送ることを意識しましょう。特に、無理な挑戦や不摂生な生活は、心身のバランスを崩しやすいため避けるべきです。
そして、古来からの知恵である厄払い(厄除け)を有効に活用しましょう。これは単なる儀式ではなく、厄年に際して自らを律し、慎重な行動を誓うための決意表明でもあります。厄払いと、日々の丁寧な生活を組み合わせることで、心穏やかにこの節目を乗り越えることができるでしょう。
厄年にやってはいけないこと
厄年にまつわる俗説は数多くありますが、その本質は大きな変化や無理な挑戦を避けることにあります。特に避けるべきなのは、心身のバランスを崩すような行動です。
厄年に慎重になるべき行動
体調を崩すほどの無理な挑戦
転職、起業、無謀な投資、引越しなど、環境や生活基盤を大きく変える行動は、精神的・肉体的ストレスが大きいので極力避けましょう。
不規則・不摂生な生活
体調の変化が起きやすい時期だからこそ、暴飲暴食、夜更かしなど、健康を害する行為は厳禁です。
人間関係のトラブル
感情的な衝突や、金銭が絡む大きな貸し借りは、さらなる厄を呼び込む原因になりかねません。
厄年に関わらず、これらの行動は健康的な生活を脅かす原因になるので常に注意すべきです。その上で、動かないことが目的ではなく、十分な準備と計画なしに動かないことが重要です。十分な計画があれば、ライフイベント(結婚や住宅購入など)は進めても問題ありません。運気を下げずに穏やかに過ごし、開運に繋げるための方法を【厄年にやってはいけないこと】で具体的に10項目解説しています。
厄払い・お祓いの基本
厄払い(やくはらい)は、神社や寺院で神職や僧侶に祈祷してもらい、自分に降りかかるとされる災厄を祓い清めてもらう儀式です。厄払いを受けることは、厄年に向けて自らを律するという決意表明にもなります。
| 時期 | 本厄の年の正月(松の内)から節分までが最も良いとされています。前厄の年に行うのも有効です。 |
|---|---|
| 場所 | 神社では「厄払い」、寺院では「厄除け」として行われます。信仰に応じて選びましょう。 |
| 服装 | 正式な儀式ですが、最近は平服で問題ない場合が多いです。ただし、清潔感のある服装を心がけましょう。 |
最も大切なのは、厄払いを受けたことで「もう大丈夫」と油断せず、その後の生活で慎重な行動を継続することです。【2026年 厄年早見表】では、前厄・本厄・後厄の対象者がわかる男女別の一覧表に加え、厄払いの時期や方法、基本的なマナーまでをまとめて解説しています。
厄年とライフイベント
厄年が、結婚や出産、引越しといった人生の大きな慶事と重なることは少なくありません。「厄年に新しいことを始めるのは不吉ではないか?」と不安に感じる方もいますが、一般的に、おめでたい出来事は厄落としになると考えられており、避ける必要はないとされています。
【厄年における慶事の考え方】
| 慶事の種類 | 厄年との関係 | 心構え |
|---|---|---|
| 結婚・入籍 | 吉。厄を分け合えるパートナーを得るため、厄を弱める。 |
準備は無理なく、計画的に。 |
| 出産・妊娠 | 大吉。「厄落とし」であり、神様からの授かりもの。 |
優先的に健康管理を徹底。 |
| 新築・引越し | 中吉。生活基盤の変化は吉だが、無理な資金計画は避ける。 |
資金と計画に十分な余裕を持つ。 |
大切なのは、これらのイベントを慎重な準備と感謝の気持ちをもって迎えることです。過度な心配はせず、人生の喜びを前向きに捉えましょう。
厄年の結婚・入籍
厄年と結婚・入籍が重なっても、まったく問題ありません。結婚は新しい門出であり、運命を大きく変える吉事と考えられています。また、厄を分かち合えるパートナーを得ることで、かえって厄の作用が弱まるとも解釈されます。ただし、結婚の準備や引っ越しは、心身に大きな負荷がかかるイベントです。厄年で体調を崩しやすい時期だからこそ、無理なスケジュールを組まず、計画的に準備を進めることが何よりも大切です。厄年と結婚のタイミングが重なって不安な方へ。【厄年の結婚】で、入籍は避けるべきか、縁起の良い時期はあるのかといった疑問に答え、安心して新たな門出を迎えるための厄払い方法を解説しています。
厄年の出産
女性の厄年(特に大厄の33歳)と出産が重なることは非常に多いですが、出産はまったく問題ありません。古来から、出産は厄を落とすとも言われるほどの大吉事です。赤ちゃんは厄を祓う存在、天からの授かりものとして歓迎されます。厄年だからといって出産時期をずらしたり、不安に思ったりする必要は一切ありません。むしろ、妊娠・出産を機に、生活習慣を改善し、健康管理を徹底することが、厄年を平穏に過ごす最良の厄落としとなります。厄年の出産が縁起が良いとされる理由や言い伝え、注意点、そして母子の健康を願う厄払いと安産祈願について、【厄年の出産】で詳しくご紹介しています。
厄年を乗り越えるために
厄年は、過度に恐れるのではなく、人生の大きな転機と捉え、自分自身を見つめ直すための貴重な機会として活用しましょう。厄年を無事に乗り越えるカギは、ずばり普段の行いと心の持ち方にあります。この時期は、何よりも健康のため体調管理を優先し、無理や不摂生を避けることが重要です。また、厄落としとして、人のために尽くしたり、読書や自己啓発といった内面的な学びを深めたりするのも良いでしょう。心と体を整え、前向きな気持ちでこの期間を過ごすことが、最高の厄除けとなります。
厄年の運気を上げる方法
厄年にこそ運気を上げるために積極的に行うべきことは、日々の生活を丁寧に送るという基本に立ち返り、心身を整えることです。
厄年の運気を高める行動
体調管理の徹底
規則正しい生活、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠で、健康という土台を固める。
人のために尽くす
慈善活動や寄付、ボランティアなど、他者への親切を「厄落とし」として積極的に行う。
内面の成長
語学や読書、習い事など、自分を高めるための小さな学びを始める。
笑顔と感謝
笑顔を心がけ、日常の小さな幸せに感謝することで、ポジティブな運気を呼び込む。
自分を大切にする
善い行いをするには、まず自分が満たされていないとできない。
「病は気から」という言葉もあるように、前向きな心の持ちようが、最大の厄除けになります。そして、自己犠牲が前提の行動と親切は違います。心身ともに、まず自分を大切にしてあげましょうね。
厄年に読むべき本
厄年という時期は、自分自身とじっくり向き合う絶好のチャンスです。古人の知恵や、生き方のヒントを得られる本を読むことで、心の平穏を保ち、人生の指針を見つけることができるでしょう。
- 自己啓発書: 人生観や仕事、人間関係について深く考えるきっかけを与えてくれる本。
- 健康に関する本: 体の仕組みを理解し、体調管理のノウハウを学ぶ本。
- 古典・教養書: 厄年という習慣の背景や、古来からの知恵を学び、精神的な落ち着きを得られる本。
読書を通じて知識と教養を深めることは、内面を整えるという厄年本来の過ごし方に深く合致しています。不安な気持ちを和らげ、厄年を乗り越えるためのヒントを与えてくれる本を【厄年の本ランキング】でご紹介。自己啓発からスピリチュアルな一冊まで、心の支えとなる本が見つかりますよ。
まとめ|厄年を正しく理解して過ごす
厄年とは、決して恐れるべき不吉な年ではありません。それは、人生の設計図を点検し、心身のバランスを見直すための大切なリセット期間です。厄年を平穏に、そして有意義に乗り切るための最終的なポイントは、以下の通りです。
- 知識を力にする: 前厄・本厄・後厄の違いや、ご自身の厄年年齢を正確に把握する。
- 変化より安定を重視: 大きな環境変化や体調を崩すような無理は避け、健康管理を徹底する。
- 行動で厄を落とす: 厄払いを受け、他者に親切にする、学びを始めるなど、前向きな行動で心の平穏を保つ。
厄年を正しく理解することが、人生を豊かにする機会へと繋がります。厄年を機に、日頃の生活態度や健康、人間関係を見直すことで、厄年を乗り越えた後の人生は、きっと以前よりも豊かに、そして力強く歩んでいけるはずです。この3年間を、あなたの人生の「黄金期」を迎えるための準備期間として活かしましょう。厄年とは、いわば自分自身と深く向き合って、より良い人生を歩んで行くためにあるものと捉えれば、前向きに過ごしていけるのではないでしょうか。
関連記事【2026年版】前厄とは?男女別早見表と厄払いのタイミング
関連記事【2026年版】後厄とは?男女別早見表と注意すべき過ごし方
関連記事【2026年版】厄年早見表|男女別一覧と厄払い方法まとめ
関連記事厄年の結婚・入籍は大丈夫?避けるべき時期と厄払いの方法
関連記事厄年にやってはいけないこと10選
2026年(令和8年) 厄年早見表
この早見表は、新年を迎える元旦に年をとる「数え年」で記載しています。
※満年齢は、2026年中にお誕生日を迎えた後の年齢です。
| 性別 | 厄の種類 | 数え年 | 満年齢 ※ | 生まれ年(西暦) | 生まれ年(和暦) |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 |
前厄 |
24歳 |
23歳 |
2003年 |
平成15年 |
|
本厄 |
25歳 |
24歳 |
2002年 |
平成14年 |
|
|
後厄 |
26歳 |
25歳 |
2001年 |
平成13年 |
|
|
前厄 |
41歳 |
40歳 |
1986年 |
昭和61年 |
|
|
大厄(本厄) |
42歳 |
41歳 |
1985年 |
昭和60年 |
|
|
後厄 |
43歳 |
42歳 |
1984年 |
昭和59年 |
|
|
前厄 |
60歳 |
59歳 |
1967年 |
昭和42年 |
|
|
本厄 |
61歳 |
60歳 |
1966年 |
昭和41年 |
|
|
後厄 |
62歳 |
61歳 |
1965年 |
昭和40年 |
|
| 女性 | 前厄 |
18歳 |
17歳 |
2009年 |
平成21年 |
|
本厄 |
19歳 |
18歳 |
2008年 |
平成20年 |
|
|
後厄 |
20歳 |
19歳 |
2007年 |
平成19年 |
|
|
前厄 |
32歳 |
31歳 |
1995年 |
平成7年 |
|
|
大厄(本厄) |
33歳 |
32歳 |
1994年 |
平成6年 |
|
|
後厄 |
34歳 |
33歳 |
1993年 |
平成5年 |
|
|
前厄 |
36歳 |
35歳 |
1991年 |
平成3年 |
|
|
本厄 |
37歳 |
36歳 |
1990年 |
平成2年 |
|
|
後厄 |
38歳 |
37歳 |
1989年 |
平成元年 |
|
|
前厄 |
60歳 |
59歳 |
1967年 |
昭和42年 |
|
|
本厄 |
61歳 |
60歳 |
1966年 |
昭和41年 |
|
|
後厄 |
62歳 |
61歳 |
1965年 |
昭和40年 |

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.madori-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)